| 08 熱帯植物が野生化し大株に育っている、ゴクラクチョウカ(極楽鳥花)の花 | ||||||||
|
所在地 | 横浜市港北区日吉2丁目 小公園「日吉2丁目公園」 | ||||||
| 科・属など | バショウ(芭蕉)科ゴクラクチョウカ(極楽鳥花)属 多年草 | |||||||
| 見どころ | 別名はストレリチア。バショウ(芭蕉)科ゴクラクチョウカ(極楽鳥花)属。植物園の温室でよく見かけたこの花が編集室の町内で見られるとは……?! 熱帯植物がこの寒い中、育っていることに驚きました。しかも、根元を見ると、20株以上の大株に生長、立派に野生化し鳥の口ばしのようなオレンジ色の花を咲かせています。「極楽鳥」は ”風鳥(ふうちょう)”という鳥の別名で、 金色の美しい飾り羽を尾の部分にもつ野鳥。この鳥に似ている花、ということで「極楽鳥花」と命名されたそうです。「ストレリチア」はイギリスのジョージ3世の妃の名に因むようです。 | |||||||
| 撮影者 | 岩田忠利 | 撮影日 | 2012.1.1 | |||||










_thumb.jpg)









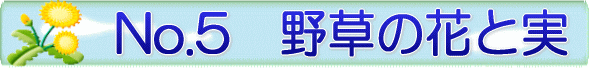


































_thumb.jpg)














