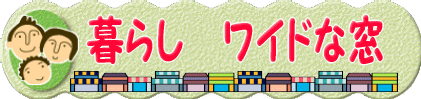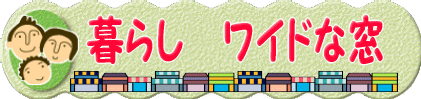|
|
晩年になると月日の経つのが早い。
明けて一月四日九十歳、世にいう卒寿である。
|
|
新聞の訃報欄が目につくようになった。そして、気になるのは故人の没年齢である。それが私の歳より若いケースが多くなった。
若い頃には傍にも近づけなかった大先輩の享年を調べてみると、その殆どが私の年齢に及ばない。思えば知らぬ間に歳をとったものである。
よく「長寿の秘訣は?」などと質問される。
「歳を意識しないことだよ」と答えることにしている。
質問した方も、それぞれ思いあたることがあると見え、「なるほど」と納得してくれる。
私も六十代、七十代の頃は自分の歳を意識することがなかった。気障な言い方だが、「意識する暇がなかった」ということになる。
|
|
|
|
ところが世間は、年寄りが意識せざるを得ないように、長寿祝いにこと寄せて、ヤレ喜寿だ、ヤレ傘寿だ、米寿だ、卒寿だと騒ぎたてる。しかし騒がれる当の本人にとっては別に目出度くも何もない。……よくぞ、ここまで生き延びたもの……という感慨があるだけ。
「ナニ、卒、卒えるとはナニゴト!」。いや、卒えるではなくて、卒の略字「卆」を分解すれば「九十」になるというだけ。
そういえば、喜寿の喜も「㐂」で七十七、傘寿の略字が「仐」で八十、米寿の「米」の書き順が八十八で、すべて閑人の文字遊び。
百から「一」を引いて白寿、すなわち九十九と数字遊びまである。
大分毒づいたが、しかし、これも年寄りに自分の歳を意識させ、世代交代を促すという、言わば“生活の知恵”といえよう。
ところで小生、十年前、八十の声を聞いてから、さすがに自分の歳を意識せざるを得なくなった。意識したとたん、脚が弱くなった。
菊名駅から自宅まで約2,300メートルの道、極めて緩やかな坂になっている。過去十数年間、殆ど気にならなかった傾斜であるが、これが最近億劫になった。
この道を若い女の子がスイスイと追い抜いて行く。「ナヌッ!」と力むのだが、とても追いつけない。力むという意識だけが過去の栄光の名残である。
最近はオバサン連中にまで追い越されている。
|