神奈川熊野神社・宮司自作、ゆかり唄
神奈川熊野神社の宮司・照本力さんが自作の「神奈川宿」ゆかり唄49首にコメントを添えて編集室に送ってこられた。その中から特集地に関するものだけを紹介しよう。
こんこんと今も湧き出る御膳水
神奈川区斉藤分町の善龍寺の横町を左に入った所に、今も満々と清水が湧き出している。
幕末、神奈川本陣の石井源左衛門が、木管で水道を引き、明治元年10月11日、明治天皇の東幸のみぎり、この本陣にご宿泊し、ご料の水に供されたため「御膳水」という。またその昔、太田道灌がこの場所に黄金を埋めたと伝えられ、またの名を「黄金水」ともいった。
夕暮れて鳥越渡る雁の群
鳥越の地は、東白楽の東の丘、現在の孝道教団の山続きである。文政7年(1824)記された「金川砂子」にも歌われている地。つい最近まで、横浜の港を一望し、近くは本牧の岬、遠くは房総を眺める絶景の丘であった。ここは浦島伝説の浦島山に続いている。
この眺望にひかれ、清純女優で鳴らした川崎弘子と戦後のラジオ番組「笛吹き童子」でお馴染みの笛の名手・福田蘭童が丘の中腹に住んでいた。また、文化功労者で万葉学者の犬養章先生も神中奉職時代の若き日にお住いであった。今も当時の教え子たちが「鳥越会」をつくり、往時を偲んでいる。
白楽の清水飲みつつ馬子の唄
先代新羽屋の当主・中村源兵衛さんから聞いた話だが、白楽は「伯楽」であり、馬の意。中国上代、馬のよしあしを相するに巧みであった人、転じて馬喰(ばくろう)。
江戸時代、神奈川宿に駅馬・伝馬の制度がしかれ、近郷より荷馬が集りたむろし、この辺りの清水で喉を潤す光景がよく見られたという。
平尾前 中川とりて平川町
東白楽駅と反町駅の間に平川町通りが走っている。そこに以前、東横線の「新太田駅」があったが、戦後廃駅となった。
西方の旭ヶ丘に「平尾内膳(地頭)の物見の松」という塚があって、俗に「一本松」といった。この地の字名「平尾前」と町名「中川町」が合併して平川町に。
平尾塚は昭和57年頃取り壊され、住宅地となる。なお、町名「広台太田町」の「ひろだい」は、「平尾台」から転じたものといわれている。
(東神奈川熊野神社宮司・熊本力)
お稲荷様がこんな変わり果てた姿…
白楽駅東口の駅前通りを一歩出ると、賑やかな商店街とは打ってかわって高台の静かな住宅地。その南東に無人のお寺「吉祥寺」がある。明治後期の頃は、“番外弘法大師霊場”として多くの信者を集めたが、あの戦争の傷跡深く、今は訪ねる信者はほとんど皆無。
本堂をお参りし、右を見ると、なんとも哀れなお稲荷様のお堂…。
屋根はいまにも落ちそう、柱は大声を出せば風圧で倒れそうだ。近づいてその中の祠をまじまじと眺めると、銅葺きの屋根は緑青色、本体は龍の透かし彫りなど精巧な芸術品。どんな名工が作ったものか、機械文明の現代でも作れるのだろうか、と疑ってしまうほどの傑作とみた。
|
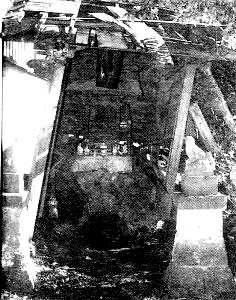
吉祥寺境内の憐れなお稲荷さん
|
|
|
|
そんな境内に、作業着姿で独り黙々と植木の手入れをする人がいた。聞けば、熱心な真言宗の信者の方で近所に住む、伊藤 正さん(70)。
「境内の稲荷は、昭和15年のものですよ。いまじゃあ、お参りする人もいないねぇ」と、寂しそうにつぶやいた。
それにしても、崩壊寸前の祠を辛うじて突かい棒で支えるこの有様は何とも遺憾! お稲荷さんといえば五穀豊穣、商売繁盛の神様。
この際、白楽の皆さんが力を合わせ、再建基金を募ってみてはいかが……。 文:佐藤由美(日吉)
平成時代にもあった御膳水
一片の畑も野原もないこの白楽地域に今でもこんこんと湧き出る「御膳水という清水」があるとは……。早速、この所在地を照本宮司に尋ね、探訪することに。
坂を上り、善龍寺という寺の前の急坂を下り切った所の横町に、ホントにあった。
だがここは、山田 一さん(斎藤分町115-13)なる家の私有地。ご主人にワケを話すと、快くその湧水を案内、説明してくれた。南向きの母屋の軒下、1メートル四方ほどのコンクリートの水槽に清水が、勿体ないほど塩ビ管の中からどんどん流れ込む。
「そう、みなさんが『流しっぱなしで勿体ない』っていうんですが、年中出ているんですから、汲め溜めする必要もありませんしね」と、山田さんは笑う。
「孫たちはいつも水風呂にはいっていますよ」というほど冬場は水温が高く、逆に夏は「10分間と手を入れていられませんよ」というほど冷たい。お祭りの時などは近所の人たちがスイカやラムネを冷やしたりするそうだ。保健所の水質検査でもお墨付きの「湧水」。もちろん、山田家の家庭用の水は一切この御膳水で賄われる。
水道料金もお高いご時世に羨ましい話だ。まさにご当家にとっては、〝黄金水″。
|

山田家で生活用水としている御膳水
|
|
ここにも〝命の泉″が…
――白楽5番地。深川貞一郎さんというお宅の塀から清水がじゃんじゃん湧き出ている。しかも、美味しい水と評判。お茶好きな人が遠方からわざわざ汲みに来るって――こんな口コミを耳にした。
現地に急行してみる。場所は東白楽駅から歩いて2~3分、白楽ボウルの裏の旧道沿い。カイズカイブキの垣根の下から突き出たやや太目のパイプ、そこからちょろちょろと…。
水源をたどると、この辺りの地主・新井一夫さん宅の古井戸。じつはこの水、明治時代、祖父の忠兵衛さんが家作人たちの洗い場として引いたもの。関東大震災や横浜大空襲のとき、焼野原のなか命からがら逃げ惑う重傷の被災者たちの喉を癒し、多<の人々の命を救ったのである。平和になってからも、横浜駅近くの青木橋あたりから大八車を引いてこの水を汲みに来る人が絶えなかったという。
ヤカンを下げた主婦がよく水を汲む姿が見られたのは、ごく最近まで。ここで洗車をしたり、ゴミを平気で捨てたりする心無い人の存在や、市の厳しい水質検査もあって、今年の春、やむなく水口を閉鎖…。
明治から1世紀、苦しむ人々を助け、世の移り変わりを見つめてきた〝歴史の泉〟、なんとも残念なことだ。
文:佐藤由美(日吉))
|