東京都立大学が今年3月八王子に引っ越したとはいうものの、都立大学駅の朝は、学生服姿のちびっ子や女の子でごった返す。都立大学付属高校・トキワ松学園・八雲学園女子高があるからだ。これは目黒区内にある高校13校のうち3校の高校は区内で最も多い地域である。
このほか、駅周辺に八雲・宮前・東根・中根・大岡山の5つの小学校、目黒第十中、目黒第八中の2つの中学校、と合わせて7つもの公立小中学校がある。
小学校といえば、なかでも目黒区立八雲小学校は創立が明治4年、区内でも最も古い学校である。
当時の同校は、現在の世田谷区太子堂に村民の熱意で設立した〝太子堂郷学所″という私学の分校としてスタート。現在地の西隣にある金蔵院というお寺の中での授業だった。なのに、翌5年には近隣から通う生徒が男子53名、女子68名、計121名もの多数に及んだ。
明治初期のこの時代、この地域で学校がいち早く開校したこと。男子より女子生徒が多かったこと。この点からみても、地域住民の文化水準の高さがうかがえる。
|
|
|
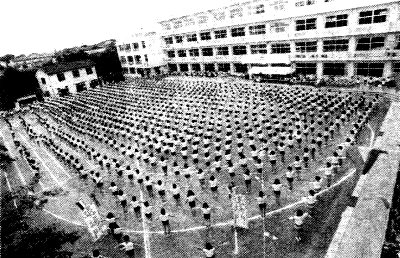
八雲学園女子高の全校運動会
|
|
こうした教育文化に対する地元の理解、とくに地主さんたちの協力があったからこそ、八雲の地に東京都は昭和4年東京都立大学(当時は府立高等学校)を開校させることができ、また私立高校や公立小中学校もその建設用地を確保することができたのであろう。 文:岩田忠利
|
国木田独歩の小説に八雲小登場!
|
明治期の詩人で小説家である、あの有名な国木田独歩が八雲小学校を登場させる短編小説『酒中(しゅちゅう)日記』を書いているのを、皆さんはご存じ?
この作品は、明治35年(1902)の文学雑誌『文学界』11月号に発表されたもので、瀬戸内海に浮かぶ馬島(山口県熊毛都田布施町馬島)に移住した少々気弱な主人公〝大河今蔵″が八雲小学校で教鞭をとっていた当時を回想した手記である。
「酒を呑んで書くと、少々手がふるえて困る。然し酒を呑まないで書くと心がふるえるかも知れない」
という一節から、題名の通り主人公が洒を飲んでからこの日記を書いていたことがわかる。
内容は学校改築問題にからむ八雲小学校時代の話。
主人公の自身のこと、その母親、そして妻子の話へと進展していく。
作者の独歩はこの作品について『文学界』の中で、次のように述べている。
「かつて窮迫して原宿にありける際、かの主人公の如き小学校教師を知れり。酒屋の隠居、学校の改築寄付金募集などすべて事実なり。唯余はその小学校教師の性格を配するに半ば自己の性格を以てせり」。
文中「原宿にありける際」と書いてあるが、この〝原宿″とは、独歩がこの作品を発表する前の明治29年9月から翌年春まで住んでいた豊多摩郡上渋谷村(現在の渋谷区宇田川町)のことを指すのであろう。
|
|
|

著者の国木田独歩
明治4年~41年 享年37歳 |
|
八雲小学校改築のときの寄付金募集は、彼が知り合った同校教師から聞いた話であることは間違いないが、主人公・大河のモデルは作者の独歩自身であり、作品中で触れるさまざまな出来事――日清戦争中の従軍記者としての経験をもとにした話や妻子の死(独歩は渋谷に移る直前に離婚)に至るまで、彼の人生そのものを物語っている。
まず私たちに興味を抱かせるのは、現在の目黒区八雲小学校が荏原郡衾村立だった遠い明治期に一教師が同校改築の裏方として苦労された様子。つぎはここに登場する酒屋「升屋」が氷川神社前に現存する″益屋酒店″をもじったものか、それとも、文中の「学校前の酒屋」とあるように八雲小学校の東隣りで終戦まで酒店を営んでいた現在のタバコ屋〝伊藤商店″がモデルなのかということ。
|

現在の八雲小学校
撮影:岩田忠利 |
|
明治期まだ純農村だった八雲小学校周辺。それが文豪の手により後世に残され貴重な作品である。
文:木村敦郎
(★なお、この『酒中日記』は大正10年、松竹蒲田撮影所で監督・賀古残夢が映画化し日本のサイレント映画となった。)
|
|
この地が気に入った 住人あの人この人
|
都立大学駅周辺は目黒通り・駒沢通り・環七通りが走り、どこへ行くのも便利。そのうえ、緑が濃く、小高い丘のある静かな住宅地である。その魅力に惹かれて古くから、各界の著名人が多く住んでいることでも知られている。
東横線の南側には、〝世界のホームラン王″の王 貞治さん(元巨人軍選手)、平町には新国劇の大御所・島田正吾さん、お隣に佐藤栄作元総理の子息で大臣経験者の佐藤信二衆議院議員、またそのお隣に評論家・秋山ちえ子さん、清元節浄瑠璃の人間国宝の清元志寿太夫さん、元衆議院議長の福田 一さんら。
環七通りを渡った碑文谷地区にはフジテレビの〝笑いのプロデューサー″横沢 彪さん、本誌7号から27号までの表紙絵の作者で漫画家・井崎一夫さん。
|
|
東横線北側には大企業の役員や大学教授などが多く住んでいるが、その名がより身近に感じられる人たちでは……。柿の木坂には生まれも育ちも同所の歌手・松島トモ子さん、宇野重吉さんも長く住んでいたが亡くなり今は息子の俳優で歌手・寺尾聰さん、日航機事故で惜しまれた坂本九ちゃんも住人だったが、夫人の女優・柏木由紀子さん、その近くに歌手の青江三奈さんやタレントの前田武彦さんなど。八雲には売れっ子タレントの〝タモリ″こと森田一義さんと最近移転して″目黒のサンマ″で話題の明石家さんまと大竹しのぶ夫妻、俳優の佐野浅夫さんなど芸能関係者が多い。
ほかには東洋大学元学長の磯村英一さん、軍事評論家の海原治さん、漫画家・小池一夫さん、女性史研究家の山崎朋子さん、作詞家の山口洋子さん、音楽家の岩崎 淑さんなど。 文:岩田忠利
|
|
|
|
目黒区内に〝炎の里″があるとは、全然しらなかった。しかも、美術年鑑の陶芸の部で上位にランクされている陶芸家・井高帰山という先生が、こんなに身近にいらっしゃるとは‥…。
自由通りを駒沢公園へ向かい、左折すると公園のすぐ隣、世田谷区境の目黒区東が丘2丁目。樹木の多い静かな住宅街に〝井高窯″があった。
奥様に奥の和室に案内されると、そこには帰山作の作品の数々……。黄玉磁をはじめ、白高麗、青磁、色絵、金彩と鑑賞陶芸風の作品が目立ち、その作域の広いことがうかがえる。眺めていると、いずれにも心和む楽しさが漂っている。
しばし待つほどに、「いや~どうも、どうも。専用駐車場へ案内しましょう」と井高帰山先生(63歳)が現れる。
じつに如才なく、明るい先生だ。聞けば、先生は鬼才といわれた初代・井高帰山氏のご長男で、父上に仕込まれてその技法を受け継がれた2代目という。
陶芸に疎い当方でも目に付くのは、黄玉磁。慎み深く、それでいてあでやかな黄地紅彩。そのルーツをたどると、日本の近代陶芸が歩んだ一筋の道と重なるのだそうだ。
|
|
|
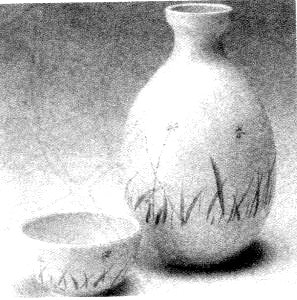
井高帰山作 青磁紅影酒注盃 |
|
その道とは、先生の父・初代井高帰山~母方の祖父で金沢の陶芸家・友田安清のたどった道であり、その行き着く先に明治元年に来日し明治期の陶芸家を指導し日本の近代窯業の父といわれたドイツ人のワグネル(東工大学構内にワグネル記念碑がある)の姿があった。
文:岩田忠利
住所:目黒区東が丘2-14-24 帰山窯℡03-3411-0996
|
|
世界の民芸品の殿堂「グラナダ」の社長
90歳で活躍中の世界的収集家 河村幸次郎さん
|
駅前のアートコーヒーの横を線路沿いに自由が丘方面へ向かった住宅街の一角、そこにひときわ目立つ白タイルの壁面に等身大もある壷や民芸品が飾られた白亜の殿堂グラナダ――。
預金通帳持参のOLも多い…
150平方メートルほどの店内の1、2階はスペインを中心とした∃-ロッパや中近東などの民芸品が約5000点。
店頭に並ぶ庭園用噴水・灯篭・置物、店内には中世ヨーロッパの甲胃、ぶどう酒の大瓶、いかにも年代物らしいオルゴール、数え切れない陶磁器の数々、家具類……。
一品一品見ていたら丸一日かかりそう。皇族の島津貴子様や三笠宮妃殿下もよく見に来られ、とくにオスタちゃんは何時間もご覧になるとか。100万円単位のお金を持ってこなければ欲望をみたせないと預金通帳持参のOLも多いそうだ。
店内に現れたのは、収集家で有名な社長の河村幸次郎さんご本人。話は美術・文学・歴史・世界の地理そして人生観と多岐にわたり、淀みない。お歳を訊いて驚いた。昭和天皇と同い歳で、まもなく〝満90歳″のご高齢。今でもヨーロッパなど世界各地を訪ねて民芸品の収集と買い付けに歩かれるスーパーマン。
河村さんはグラナダの顔だけでなく、竹久夢二の作品240点を所有する(河村コレクション〉の顔としても知られている。最近その作品集を美術書として発刊したが、みずから筆をとり、レイアウトまで手がけた編集者でもある。
|
|
|

等身大ほどもあるブドウ酒の瓶など珍品がずらっと並ぶ店内。河村社長の話は尽きない… |
|
コレクションは「執念でやるもの」という河村さん、変わったところでは毎日新聞(明治9年)と朝日新聞(明治12年)の創刊号や日露戦争(明治37年)の号外まで持っていらっしゃる。
漁港下関生まれの河村さんの夢は、世界の漁船50隻を集め、故郷に〝博物館″を造ること。すでにグラナダの店頭にインドネシアとボルネオから丸木を切り抜いた舟(長さ5メートル)3隻が飾られた。
若さとは年齢ではない。夢を持ち、それに向かって生きる意欲なのかな。 文・写真:岩田忠利
本店:目黒区中根2-15-20 ℡3724-0005
|
|
日本一の遊園地の仕掛人集団 トーゴ(旧社名:東洋娯楽機㈱)
|
〝よみうりランド″や〝向ヶ丘遊園″などの遊園地へ行くといろんな楽しい施設が一日を満喫させてくれる。地上100メートルを超す大観覧車が大空の中にゆっくり回り、宙返りコースターからはつんざくような叫び声、水上コースターでは素っ頓狂な歓声があがる。メリーゴーランド、飛行塔、豆自動車も子供たちに人気がある。
乗り物だけでなく、お化け屋敷・水族館・水中劇場なども見学でき、モグラ叩きなどいろんなゲームで遊ぶこともできる。そしてそれぞれの施設に制服を着た係員が見守っている。
これらの施設は殆ど鉄道会社などがオーナーで、営業は外部の会社が委託を受けているものだ。この営業形態を「受託営業」といい、制服の係長は外部の会社の者が多い。
目黒通りの八雲1丁日にある8階建ての「トーゴ」というビル。ここが、㈱トーゴ(旧社名・東洋娯楽機)の本社。あの遊園地の施設を製造したり、全国各地にある遊園地の受託営業、さらに直営までをやっている本拠地だ。
とくに浅草楽天地は昭和24年から園名を〝浅草花やしき″に戻し、直営している。東急沿線の子供たちに親しまれてきた遊園地〝多摩川園″や″二子玉川園″も、もちろん同社の受託営業だった。
トーゴの創設は、昭和10年東京・向島のタクシー会社の社長だった山田真一が″歩く象″の製作に専念したのがきっかけ。
|
|
|
以来、同社は戦時下と終戦後の動乱期を乗り切り、日本の経済成長とともに躍進、全国はもとより、ソ連・中国・キューバの遊園地に遊戯施設を設置するまでに成長し、今や全国に営業所37か所・工場2か所・社員400人・売上げ100億円の業界最大手の規模だ。
娯楽機の輸出というのは、社員が現地まで出張し、据え付け工事をし、試運転を完了させ、現地の管理者に引き渡してはじめて輸出したということになる。
|

トーゴ直営「浅草花やしき」の45mタワー |
|
キューバに初めての遊園地をつくったときは、工事進行中から連日新聞が取り上げるなど大変な関心を呼び、トーゴの社員は〝国賓待遇″を受けたほど。
それほどまでにトーゴの娯楽機が大人にも子供にも楽しさと喜びを与えるとは、仕事冥利に尽きるというもの。週休二日制の普及で我が国のレジャー産業、まだまだ伸びる。 文:岩田忠利
本社:目黒区八雲1-5-10 ℡3718-6461
|
こちらは信用金庫の日本一 城南信用金庫
|
|
昭和25年当時の昔の町並(本号55ページ)にも載っている城南信用組合は、その前身を碑衾信用組合といい、大正11年3月碑衾町(目黒区となる前の町名)の有力者・角田光五郎氏らが設立、同年6月末の貯金総額は僅か1万7千円余だった。
その碑衾信用組合は昭和20年8月、都内の城南地区14の信用組合、つまり大崎・品川・大井・大森・入新井・馬込・池上・蒲田・六郷・矢口・羽田・荏原・駒沢・砧の各信用組合と対等合併し、名称を<城南信用組合>と改め、再スタート。
明治35年創立の入新井信用組合など地域に根ざしだ実績と伝統あるこれらの15も多くの最良信用組合が一挙に合併することは、日本の産業組合史上だけでなく一般金融史上でも例を見ないものといわれている。
昭和26年10月、信用組合が〝信用金庫″に改組。城南信用金庫は都内最多の中小商工業者が密集する城南地区をバックにその金融相談窓口として躍進に躍進を重ね、今日に至る。
|
|
平成3年5月現在、同信用金庫の実績と規模は預金高・2兆3583億2700万円、店舗数は東京都と神奈川県内に81店舗、職員数・2956人。
その数値はいすれも全国448の信用金庫の中で群を抜き第1位、文字どおり我が国信用金庫の代表選手である。
文:岩田忠利
|

五反田の城南信用金庫本店 |
|
|
東急沿線に同業はない ワールド避雷針工業
|
|
先日もアメリカでゴルフのギャラリーが落雷に遭って死傷した。やはり怖いのは、地震・カミナリ・火事・親父。いや、最近の親父だけは別だ。
その落雷防止のため、建設基準法では高さ20メートルの建物には避雷針設置が義務づけられている。
|

イラスト:俵賢一 |
|
そんな雷恐怖症の強い味方が目黒通り沿いの八雲2丁目にあるこの会社。雷よけの避雷針、それを製造施工する同業者は都内に5社、全国に18社だそうだ。
|
|
なかでも同社が最も後発だが、トップを猛烈なピッチで追走する業界ナンバー2。
社長の大西由恭さん(40歳)は明治学院大の文系出身、「人のやらないことをやる」と脱サラ、この会社を創業して12年目。現在は社員37名で年商11億円。毎月都内には500個所の施工現場をもち、社長の陣頭指揮で社員は奔走している。
「軌道に乗せるまでには人の3倍は働きました。朝は7時前には自宅を出て、深夜まで。今は朝7時半に出勤すると、もう社員のほうが出社しているよ」と笑顔。
文:岩田忠利
本社:目黒区八雲2-8-3 ℡3724-7281
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
|
次ページへ |
|
 |
「目次」に戻る |
 |
|
NO.877 田園調布へ |
|