|
�@�]���̓��X�A�y���Ȃ�N�E�F�[�g���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�c����Y�i�N�E�F�[�g�ݏZ�j
�@�@�@�@�@�@�@
|
|
|
|
�@�����ƐΖ��̍��N�E�F�[�g�֗��āA�͂�P�N�B���������������A���z�l�j�R�j�R�B�J�́A��H���Ȃ��B���̂��߂��A�ЂƂ�����̐�������Ȃ���A��̐�������炸�B����͕̂�����ɂ��āA�����ɑ�����������B�n�����ɒ��ޑ��z�߂�A�₵������Ȃ��A�]���̔O�����B
|
|
�@
�@����Ȏv���ł���������A�y���ޕ��A���{�̍Ȃ�著��ꂽ�w�Ƃ��悱�����x�U���g�|�h�B�y�[�W���߂���̂����ǂ������A��C�萬�ɖڂ�ʂ��B�ڂɓ���n����w���B�ǂ��������A���S��������茩�o���A�����o�������̂���ɂĉ�������������Ȃ��A�S���炮���Ƃ�����B
�@��������̂͂��B�v���A���a16�N����s����w�E�G�ɋ����\���邱�Ɩ�40�N�B�o���n�ł͂Ȃ����A����䂪�ӂ闢�B�ӂ闢����肠����������ǁA�����͗]��ɂ������A���F���Ȃ��B�F�Ȃ��Ƃ��A�y���Ɉ˂��邱�ƉȂ�Ǝv���A�ٕM���Ƃ�B
�����́u�ې�̐̂ƍ��̃A���o���v�A�Ƃ�킯�����[���B
�@�����~�̒��A���̂����Ƃ��猩�����x�m�̔�����v���o���B����A�V�����̎��ɉB��A�x�m���������ꂵ�Ǝv���B
�@��������̗���Ȃ肵���B�Ȃ�著���ė���\��̎�����҂��A�ٕM��u���B
|
|
�@�@���g�w�ł́A����o����
�@�@�@�@�@�@���R�ߎq�i���C�^�[�@�_�ސ��_�厛���j
|
|
|
�@����11���X���̖�A10��30���������߂������炢�̓��g�w�ł̂��Ƃł���B
�@����z�[���͒���������̓��g�~�܂肩��~�肽�l�ł����ς��������B
�@�z�[���Ɋ��荞�ޓd�ԁB
�@�@�@���O�ɐ������������H�ɗ������c
�@�u�Ԃ��Ȃ���Ԑ��Ɋe�w��Ԃ̍��ؒ��s�����Q��܂��B�����܂ʼn������Ă��҂����������v�̃A�i�E���X�B
�@���̎��������B�z�[������ЂƂ�̐����ς炢�����H�ɗ������̂ł���B�d�Ԃ̌x�J���������܂��������A���C�g�͂������������Ɍ����Ă���B�z�[���̂�����������ߖ����������B�������A�N������������œ����Ȃ��B������l�A���H�ɔ�э~��Ă��̐����ς炢����H�����������o�����l������B���g�w�̉w���ł���B
|
|
�@
�@�d�Ԃ͂P�A�Q���[�g����O�ŋ}��Ԃ��A�K���ɁA���ƂȂ����B���ɒ�Ԉʒu�����̌�����߂��Ă����Ƃ��Ă���������o���ꂽ�ꏊ���猩�Ď��̂ɂ͂Ȃ�Ȃ������Ǝv���B
�@�@�w���̗E���ȍs��
�@�w���̗E�C�͂��炵���I�@������E���Ƃ͂����A���������ɓd�Ԃ����Ă���̂ł���B�ق�̈�ċz�̍��Ő����ς炢�Ƃ��ǂ�����ł��������m��Ȃ��̂��B�w���̎d���Ƃ����ƁA���i��ɂ��Ă������ł́A�ǂ��炩�Ƃ����̂�т肵�����̂��v�������ׂ�B���ꂪ�Ƃ�ł��Ȃ��ԈႢ�ł��邱�Ƃ��v���m�炳�ꂽ�̂ł���B�����Ƃ������ɂ͎��Ɨׂ荇�킹�̗E�C���ł��邱�Ɓ\�\����ł����v���Ƃ����̂ł��낤�B
�@�������A���̔��ʂȂ�Ƃ������Ȃ�����Ȃ����S�Ɋg�����Ă���B
�@�������g���R���g���[���ł��Ȃ��Ȃ�قǐ����ς���āA��͖�ƂȂ�R�ƂȂ�A�ł͂��܂�ɂ��Â��߂��Ƃ������̂ł͂Ȃ����B
��̂ɁA���{�l�͇������ɂ͊��e���Ƃ�����B����ȐU�镑�����\�����A�����̏�ł̂��Ƃ����燁�̈ꌾ�ł���ނ�ɂ��Ă��܂��B�Ⴍ����𗧂Ă��肵�悤���̂Ȃ�t�ɇ���l���Ȃ����Ȃǂƌ���ꂩ�˂Ȃ��B���������������������܂���܂������A�ǂ��������ʂ��܂˂����c�c�B
�@���̖�A���̏o������ڂ̓�����ɂ��āA�䂪�g�ɏƂ炵���킹�]�b�Ƃ����l�����Ȃ��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@�܂����Y�N��̃V�[�Y���B�N�ɂƂ��Ă����l���ł͂Ȃ��͂��ł���B
|
|
�@�@�ӂ��^���ɏ�M��R�₵��
�@�@�@�@�@�@���|�`���i��ʌ��k�����S�g�쒬�@���E�@71�j
|
|
|
|
|
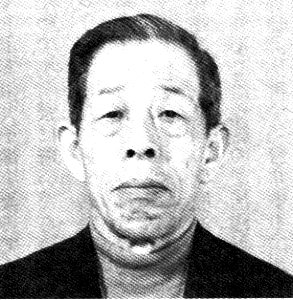
�M�ҁE���|�`������
�@
|
|
|
�@
�@�݂Ȃ���A����ɂ��́I�@�u�������Ƃ͎������J�����ƁB�����ăo���o���ɐ����Ă���l�ƁA�S���Ȃ��v����́w�Ƃ��悱�����x�̓��e���ʇ��v�����܂܁��̃��[�h���ł��B�z���g�ł��ˁB
�@����71�ł��B�d���𗣂�ĂR�N�ɂȂ�܂����A���A�ǓƂł͂���܂���B����͖����A�n�K�L�A�莆�A�ʕ��������Ă��邩��ł��B���╶�͉���ł��A�Ƃɂ����������A�̍ق����炸�A�v�������ƁA�����Ă������Ƃ�����̂܂܂ɏ����B����ȃO���[�v�Ŏ��͐l���̂�������̊D�F���o���F�ɕς��Ă��܂��B���ꂪ��X�́u�ӂ��O���[�v�v�ł��B
|
|
�_�ސ쌧���ɂS�A�k�C�������B�ƑS���Ɍ���26�̃O���[�v���_�݂��Ă��܂��B�e�n�O���[�v�ŁA���ꂼ�����́w�ӂ����x���o���āA���������������Ă��܂��B
�@�e�O���[�v���Ɨ��͂��Ă��Ă��A�Ǘ����Ȃ��B�n�K�L��w�ӂ����x�Ō𗬂��Ȃ���A20�ォ��90��܂ł̒j���́g���F�h���S��ʂ��Ȃ��當�������B�u�F�A���߂�藈��A���y�����炸��v�ł��B
�@���X�֎�A�|�g���A�����͉��ʂ��i�A�������遍�B���̂ӂ��O���[�v�n�n�҂̋��{�`�v���́A������80�A�u�����ĉԍ炭�N�w�i�݂��j�v�u�N���������镶�́v�Ȃǒ����������B
�@�u���ł����������A�F����ɂ�������v�u�����̉�X�́A����ł����B�����������c�����v�ƁA�ӂ��^���ɏ�M��R�₵�����Ă���܂��B
�������ŕ��F�́A���肾�A�_�����́A�����Ȃ��Ȃ�A�u�����j�v���̖{�����X�Ɛ��܂�āA���₩�ł��B
�@����������A�����킹�͎����œw�͂��ċ��߂���̂ł��B�������瑫������A�O�֏o�����Ƃ��Ǝv���܂��B���ւ肭�������B���ɕ����Č��܂��B
|
|
�@�v���o�����̇�������聍������
�@�@�@�@�@�@�@�@�n���s�q�i�`�k���]���j
|
|
|
�@�w�Ƃ��悱�����x�V����q�����܂����B�Ȃ�ɂ�����`���o�����\����Ȃ��v���Ă���܂��B�����{���Ɋy���݂ɓǂ܂��Ē����Ă���܂��B�����̃u���C�_�����W�͓��ɖʔ����q���������܂����B����34�N�O�̌����̓������݂��݂Ǝv���o���Ă���܂��B
�@���J�~����A�V�Y�͒�����z�n�֓��z�̑���o���ɁA�V�w���́A��A�f��A�o�����Ŏ藿���̏����A�ꏡ���z���̓��{�������Q�œc�����z�̒��l�����Ō������������܂����B
|
|
�@�e�Z��o�������o�Ȃ��A���͉��^�ł��Ȃ��w�ւ��������A�����l����́u�����v�A��́u�璹�v�̋Ȃ����ꂼ��ڔ��ŁA���Ƃ͏o�Ȏ҂̊����A�������̗�����Ղ��܂����B
�@�ʐ^�͐V�ێq����ʐ^�������]�Ԃŏo�����Ă���܂����B
�@�����I����āA�V�ێq�̉�Ђ̗��܂Ōς̉œ���Ȃ�ʁA�����l�A�V�Y�V�w�A���e�A�킪�P�������ăg�{�g�{�ێq����n���Ă��ꂽ�̂ł��B�V���̗��ɒ��������d�ŁA���[�\�N�̓��Ɍ}�����܂����B
�V�ێq�����q�R�ֈڂ荡�܂ł����Ɖ����Ƒ��ł��B
�@�@���ꂩ����Z�݂悢�����̔��W��]�݁A�w�Ƃ��悱�����x���̂�����Ɣ��W��S���F���Ă���܂��B
|