|
�@�������́A���̐g�̂ł����Ȃ�A�����̂悤�ȑ��݂ł��B���a�T�N�A�����̋߂��̑�n�ł��Ԑ��������A���y�̋߂��̘Z�p���ň炿�A�������Č��݂̑�q�R�ɏZ���27�N�ɂȂ�܂��B
�@�펞���̓d��
�@���w�Z�͔����ɂ���_�ސ썂���i���݂̐_�ސ�w���j�ŁA�푈���͊w�k�����œc�ޕ�������⋋���i���݂̂��ǂ��̍��j�Œe�ۍ������܂����B�I��܂Ŗ����A�e���ʼn��l���ɏ抷���Ē��Óc�܂Œʂ������̂ł����B�������y�Ƌe���Ƃł́A�J�����̍��E���ς��A�l�̒��������킯�A�����킯�~��邱�Ƃ́A��ςȂ��Ƃł����B���Ɏ��̂悤�ȏ����Ȏ҂́A�����Ԃ��ꂻ���ł����B
�@�@���a30�N��̑�q�R
�@�������đ�q�R�ɋ����\�����̂͏��a31�N�̂��Ƃł��B�w�O�ɂ͂��X���V�A�W���قǂ����Ȃ��A�w�O�ʂ�������s���Ƃ������ʂ���ڂł����B�Ăɂ͗[���Ƃ��Ȃ�ƐH�p�^�̑升���A�H�ɂ͉����F�̈�䂪���ɂ�炢�ł����������A�~�ɂ͉����ɕx�m�̔����]�ނ���ڂɔ��낪�����A�܂�ňꕝ�̕��i�������悤�ł����B�����ďt�ɂ͋߂��̔~�т���E�O�C�X�����ł��ẮA�u�z�[�z�P�L���v�Ɣ��������ł��������Ă��܂����B��q�R�̔~�т́A��l�Ə��߂ăf�[�g�����v���o�̏ꏊ�ł�����܂��B
|
|
�@�@�����č��́c
�@�⎩�R�������ς����Ă������̊X���A�V�����J�ʂ��@�ɋߑ�I�ȊX�ւƕϖe���Ă䂫�܂����B�q���������D�܂݂�ŗV��ł�������͈Ë��Ɖ����A����ڂ͂���̂悤�ȃ}���V�����ɐ��܂�ς��A���ł͐̂��ÂԂ��ׂ�����܂���B
�@����ł����Ă̖K��ƈꏏ�Ƀc�o������������w���ӂɂ���Ă��ẮA����ꂩ�����Ñ����Ȃ����Ă��킢���q�i���������܂��B�ǂ����u���܂ł����Ăˁv�Ɗ肤�͎̂���l�Ɍ��炸�A��q�R�����ē��������ɏZ�ފF����̊肢�ł͂Ȃ��ł��傤���B
|
�@�N������x�͎����̑c��ɂ��Ďv���߂��炷�ɂ������Ȃ��B
�@�����̏����i������j�͕�������A���ʂȐE�l�Ƃ��Ĉҋ��i���ꂽ���j�e�����炢�����������ł���Ƃ���Ă���B
�@�u�����v���̐�c�́g�ؒn�t�h
�@���̐E�Ƃ����̂́A�l�����ꂽ�R���Łu�ؒn�t�i�������j�v�Ƃ��Đ������Ă����l�����ł���B�ؒn�Ƃ͐H��Ȃǂ̎M�A�~�A�o�̎d�グ����O�̌��^�ŁA���ʼnƓ��̇����N�������g���A���̌������o���B���̐����́A�قƂ�ǎR�����肪�����B���։����̂́A��i��l���։^�Ԏ������������B
�ȑO�A����蕷���Ă����c��̌̋����A�Q�N�O�̏t�A�Z�Ɠ�l�ŖK�˂ĉ�邱�Ƃɂ����B
�@�@���K��S���R�������̐��̑c��̒n�ŁA���䌧�Ǝ��ꌧ�̌����ɂ��߂��ΖL���ȐÂ��ȎR���������B�ɐ��p�ɗ��ꍞ�ޗK���̌��������̑��X�̐����������Ă����B
�@�@�ؒn�R�̋��_�ł��������̑��́A������ς��A���̎d���ɏ]������҂͒N��l���Ȃ��Ȃ��Ă����B
���̖ꂳ��͂��̑��Ő��܂�A�c�����A�k�C���֊J��ɓn�����������B�����̂����ƂɌ����Ă��铿�R������ŏ��Ж���ׂĂ��邤���Ɏ��̐�c�̖����o�Ă����B���͖S���ꂳ��x�ƌ��邱�Ƃ��Ȃ������̋��B���̖]���̔O�����̋��ɔ����Ă���v���ł������B
|
|
�@�@�_���ɒ��ޓ��R�����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Z�����̖{���f�扻
�ؒn�t�����͖���30�N������A���Ȃ��B�����̐l�X�̌̋��ł��邱�̑��͋߁X�A�傫�ȃ_���̒��֒���Ŋ��S�Ɏp�������^���ɂ���̂ł���B
�@�������A���R�ɂ��A������ɂ����f�悪�ŋߊ��������̂ł���B�_�R�i������܁j����Y�ḗw�ӂ邳�Ɓx������ł���B����A�V�h�̈��c�����z�[���ŁA���̎��ʉ�������̂ŁA�������ɍs���Ă����B�ƂĂ��f���炵����i�ł������B
�@���R���̕��Z�̋������������{�w�����ƎR�̃R�{�����x���f�扻�������́B�F�m�ǂ̘V�l���ׂ̉Ƃ̏��N�ƒނ����Đe�������ʂ�`���Ȃ���A���R���̔������l�G�̎��R�����\������B
�@���̏H�Ɉ�ʌ��J�̗\��ł��邩��A�F�l�ɂ����Ђ������߂������B
|
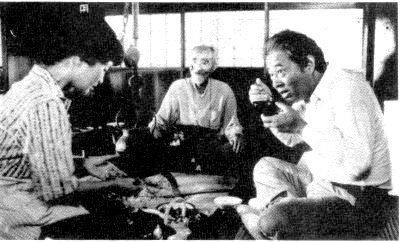
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�f��w�ӂ邳�Ɓx�̼��
�������F�m�ǖ��̎剉�E�����ÁA�E�ɑ��q���̒���T�V�A�������q�̉Ŗ��E�~�R���} |
|
�@��1983�N�i���a58�N�j����̂��̉f��́A�̂��������D�G�f�揧��܂���܁B�剉�̉����Â̓��X�N�����ۉf��Ղ̍ŗD�G�j�D�܂��l�����Ă���
�@�@
|
|
�@���@���w�̓����z���āA�s��Ƃ̊p�����܂���ƁA���@�������e�̍⓹�ɏo��B���̍⓹�����͂��߂āA���艓�����@�������̕�n�z���ɁA�{���Ə��Ƃ̒��a�����G��I�i�ς߂Ȃ���A�����E��̃R�[�q�[�X�ɗ������B�X���ɗ����o���b�N���y�A�Y�ΐ���̃R�N�̂���R�[�q�[�̖����y���݂Ȃ���A�Y��̈ꎞ�����������Ƃ��ł���B
�@���̓X�̖��́u�g���G�����v�B�h���L�z�[�e���̕��e�̃}�X�^�[�͒��}�l�B
�@�ӊw�Z�̒ʊw�H�Ƃ��āA�ӊw�Z�ɂƂ��Ă͊i�D�̃I�A�V�X�B�}�X�^�[�Ɩӊw���Ƃ̗F�������������ŁA�����Ղ̏����ō��킹������ӊw���̑��k���ƂȂ�A�ʂĂ͕����Ղ̓����A������X���x��Ŗӊw�Z�̖͋[�X�̘]���l�Ƃ��āA�o�[�e���_�[�����Ă�������B������A���X�̃R�[�q�[�Z�b�g�����Q���Ă̑��͕�d�������̂ł���B�ނ���A���P�l�Ƃł������ׂ����H
�@
|
|
�@
������A���̓X��������t�@���͑����A�������C�����̃}�X�^�[�̂��ĂȂ��́A�������q�ɗǂ��R�[�q�[�Ɨǂ����y����悤�Ƃ������Ƃɐs����̂ł���B
�ǂ����A���̂悤�Ȑl�m�ꂸ�炭�J�Ԃ̃����̂悤�ɁA�Ђ�����ƃq���[�}�j�Y�����������āA�ӊw��������Ȃ�����������X�̂��邱�Ƃ��A���������̐l�тƂ͊o���Ă����Ăق����B
|