雪の生みだした思想
北陸の冬は雪とのたたかいであり、外との行き来もとだえて、コタツやイロリをかこんで冬ごもりするのである。
ひとびとは自然無口になり、思索的となる。したがって金沢を中心とする石川県から、わりあいに多く文芸家や学者がでている。
泉鏡花も加能作次郎も徳田秋声も石川県の出身である。三宅雪嶺も木村栄(ひさし)も西田幾多郎(きたろう)もやはり郷土の出身だ。
明治は遠くなって、これらの人たちも、若い人から忘れ去られている。で、ちょっとそのグリンプスを。

晩年の泉鏡花 |
|
泉鏡花。17歳で上京。尾崎紅葉の門に入り、ロマンティシズムのあふれる名作『滝の白糸』 『高野聖』 『婦系図(おんなけいず)』 『歌行燈(うたあんどん)』などを生んだ。
加能作次郎。自然主義的作品『厄年』『篝火(かがりび)』を出す。
|
徳田秋声。鏡花と同じく紅葉の門に入ったが、鏡花らのロマンティシズムとたもとを分かち、『新世帯』『黴(かび)』『爛(ただれ)』などの庶民文学をつくりだす。
彼らの歌碑や記念碑は金沢の卯辰山や犀川のほとりをちりばめている。
三宅雪嶺。雑誌『日本人』『我観』などを発行して、徳富蘇峰流の安易な欧化主義に反対し、日本固有の文化の高揚につとめた。

木村 栄 |
|
木村栄。天文学者で、岩手県水沢緯度観測所長を勤め、緯度変化研究の歴史で画期的なZ項(木村項)を発見して、その名を世界にとどろかせた。
西田幾多郎。『善の研究』『自覚に於ける直観と反省』などの著作をつうじ、「絶対矛盾の自己同一」などの概念を明らかにして、日本独自の西田哲学を確立した。
|
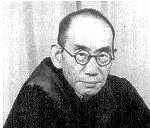
西田幾多郎 |
|
|
|
雪から生まれた雄弁
雪国はこれらの静かな思索にふける思想家などを輩出させたけれども、一転、動的な政界に活躍する二歩日の雄弁家、永井柳太郎を生み落とした。
私がこの政治家に会ったのは、小学校の卒業を間近にひかえた大正9年(1920年)のことである。その思い出をつづってみよう。
| そのころ議会の解散とともに総選挙が行われ、にわかに地方政界も色めきたってきた。それまでの金沢は政友会の地盤で、ほとんど中橋徳五郎の一人舞台であった。そこへ突如として無名の青年、永井柳太郎が憲政会から立候補したのである。はじめは物めずらしさで、ちょっと演説会をのぞいてみた民衆は、若き早大教授の雄弁と熱情にうなされた。 |

若き日の永井柳太郎 |
|
未成年者は選挙演説会にはいれないので、私は店の奉公人のハッピを借りてでかけた。できるだけ大人に見せようと、そり身になって会場へ入りかける肩を、見張りの警官に押さえられて年齢をきかれた。昂然と20歳と答えたが、「子供は帰れ」とつき戻されてしまった。
そのうちパチパチパチと柏手がおこったので、場外にあふれた聴衆にまじって窓から中をのぞいてみた。イガグリ頭の一青年が不自由な片足をステッキに保たせながら演壇に現れるところであった。
弁士は一礼ののち、ゆっくり唇をひらいた。ひらいた唇から流れでる一句一句は詩のような韻律をもって聴衆の感情を高い理想に運んでいった。やがて藩閥、軍閥、財閥の攻撃にうつるとともに、口調は次第に速度と激しさをまし、断罪の舌端がまさに火を吹こうとするとき、突然ピストル型に突きだされた右手が頭上にかざされるとみる間に、サッと弧をえがいて、テーブルにふりおろされる。とたんに感激の柏手が嵐のようにまきおこる。と、また弁士はもとのゆっくりした語調に帰り、悠然として新しい論理の糸をくりひろげていく。そしてまたもや聴衆の感情を感激のるつぼに引きずりこんでしまうのである。
演説会が終わつて弁士の車が動きだすまで、永井万歳の声は会場の内外にとどろきわたった。私は弁士の車が闇のなかに消えていくのを見守りながら、茫然と窓の下に立ちつくした。そして、
「おれも大きくなったら、あのようにやるぞ」
と胸の中でつぶやいていた。
永井はその時には敗れたが、のちに当選8回、斎藤、近衛、阿部の3内閣に、拓務、逓信、鉄道大臣をつとめて郷土出身の政治家の旗頭となった。
|
筆者・越村信三郎
横浜市港北区富士塚2丁目在住。元横浜国立大学学長 経済学博士 本誌『とうよこ沿線』顧問 78歳
|
|