長さが4キロの天然の入江が、伊良部島とその南西に位置する下地島(しもぢしま)とを隔てる境界をなす。島には全部で7つの部落があるが、この人江に沿って佐和田、長浜、国仲、仲地、伊良部といった5つの部落が並ぶ。私はこの長浜で生まれ育った。入江には昔から5つの橋が架かっていたが、潮の引いた時は歩いても渡ることができた。
橋を鉄輪をはめた馬車が行き来していたのを思い出す。下地島へ畑を作りに行くのであるが、珊瑚でできた岩だらけの土地を耕すことは大変な作業であり、作物といっても、あまり大した物はできなかったようである。
|
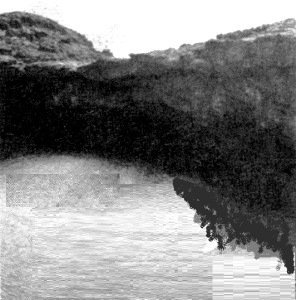
ユナタマ(人魚)伝説をもち、直径50㍍の池が二つ、不気味な自然を満喫できる“通り池” |
|
|
下地島には「通り池」と呼ばれる、直径が70メートルほどの海水を湛えた2つの池がある。両方の池は、その名の示す通り、その下で互いに通じており、また外海にも通じている。
池の周囲は岩壁が吃立し、落ちた者は這い上がれない。底知れず青くよどむ池の端に立つと、吸い込まれそうな感じがしてくる。この神秘的な池には、ユナタマ伝説と継子伝説という2つの物語がある。
継子伝説は次のように伝わる。昔の話です。
――継母が先妻の子を殺す計画を立てました。夕方になって継母は自分の子と継子を、潮干狩に連れて行きました。遅くなったので通り池で一夜を明かすことになりました。継母は、我が子をすべり落ちないようにと、岩のゴツゴツした場所に寝かせ、継子をすべり落ちやすいようにと、池の縁近くのなめらかな岩の上に寝かせました。そして継母は潮干狩に出かけると言って、その場を離れてしまいました。
夜中に戻ってきた母は、子どもたちの寝場所が替わっていることは夢にも知らず、大急ぎで池の縁近くに寝ている子どもを池に突き落とすと、岩のゴツゴツしているところに寝ていた子をおぶって、一目散にその場を逃れ、部落の方角へひた走りに走りました。
東の空には、曙の光が夜明けを知らせていました。
「お母さん、弟はどうしたの?」背中で目を覚ました継子がたずねます。――
この下地島も、昭和54年に3000メートルの滑走路を擁する日本で初めてのパイロット訓練飛行場ができた。
|
|
|
|
|
野鳥サシバの飛来
|
| ※サシバは、タカ(鷹)やワシ(鷲)の仲間で、主にヘビ、トカゲ、カエルといった小動物、セミ、バッタなどの昆虫類を食べる。まれにネズミや小型の鳥等も捕らえて食べる。人里近くに現れ水田などで狩りをする。 |
|
秋になると、サシバ(鴉鳩)の大群が島に飛来する。サシバは鴉鳩科の渡り鳥で、今も伊良部の亜熱帯林は彼らの休息地となっている。寒露の頃ともなると、島の上空は数万羽の鳥で真っ黒になった。
中学生くらいになると、この鳥を捕りに行く。木と木の間にツギと呼ぶ、止まり木を渡しておく。サシバ゙は夜になると、これに止って休むのである。竿の先に着けた輪を、寝ているサシバの首に引っかけて捕まえるのである。一晩に100羽も捕まえる名人もいた。
食用にすると、その味は例えようがないくらい美味しいが、多くは沖縄本島の那覇へ売り、貴重な現金収入となる。昔の人びとは、神様が貧しい島へ与えてくださる10年に一度のごちそうと考えていたようであった。
昭和47年5月15日、沖縄の本土復帰とともに、本土の法律が適用されて、この鳥も捕らえることができなくなった。
私の学んだ伊良部小学校は、ちょうど今年が創立100年に当たる古い学校である。小学校の校庭には大きなガジュマルがあって、この木の下が幼稚園として使われていた。建物のない幼稚園も途中から茅ぶきの屋根ができて、雨の日でも行けるようになった。
男の子は幼稚園に行くようになると、山羊の世話をする責任を持たされた。餌は自分で採って来なければならず、早朝の草刈は子どもたちの日課であった。中学生ともなると馬の飼育が任せられる。こちらの方がたくさんの餌を食べるから、それだけ大変である。
昔はどこの家にも馬がいて、様々な用途に使われていた。島の何カ所かには製糖工場があって、その周りを、目隠しされた馬がぐるぐる回っていた。工場から長く伸ばした棒を馬に引かせて、それで歯車を回し、サトウキビを絞っていた。
伊良部島をはじめ宮古群島にはハブがいない。とにかく、子どものころは仲間たちとよく走り回って遊んだものだ。
島の北方、20キロ程のところに、八重干潮(やえびし)と呼ばれる大サンゴ礁がある。年に一度、幻の大陸のごとく浮上して陸地となる。ここに上陸すれば、サザエ、タカセ貝、タカラ貝、シャコ貝、タコ等の海の幸が獲り放題である。この八重干瀬は浮上して2時間で、また海中に没してしまう。2千年後には、この地の隆起により宮古島に匹敵する広大な島が出現すると言われている。
4年ぶりであろうか、今年は島に帰り、この八重干瀬にも行きたいと思う。今の子供たちは、いったいどんな遊びをしているだろうか。
|
|
|
筆者・豊里 盛泰
沖縄県宮古郡伊良部町出身。横浜市港北区菊名6丁目で、総合建築業「ユタカ住建㈱」を設立、社長。37歳 |
|
|