乾電池、液晶、金属音などに囲まれ、大自然の恵みやあり難さを知らない現代っ子の将来が心配です。
生きとし生けるものの儚さ
テレビ番組「赤っ恥、青っ恥」ではないが、学生や社会人はせめて、この世に生まれ、生き、そして死んでいく生物の感触だけでも知ってもらいたい。そうでもないと、アメリカ人は銃、日本人は刃物、そのトリコになってしまうのではないかと危惧します。
来年古希を迎えるにあたり、私の少年時代の自然とのふれあいの思い出を思いつくまま、記してみます。
◆
雪が溶け、やがて梅がほころび、桜の花に浮かれ、田畑に活気が訪れる頃、水辺に「ホタル」が誕生します。やがて真夏、木々の梢で「セミ」の合唱。ニイニイゼミ、アブラゼミ、ツクツクボウシ、ミンミンゼミが集まり、瞬く間に賑やかに。人間の子供たちは川遊びに興じ、トンボも無言で頭上を行き来します。
時には僕らの麦わら帽子のてっぺんに止まるほどの仲良し。夜になるとホタル以外の生き物たちは表に逃がしてあげます。みな一週間ほどのはかない寿命であることを知っているからです。
夏の風物詩、ホタルとセミ
僕が初めてホタルを見たのは、たしか小学校入学前の6、7歳だったと思います。当時住んでいた神奈川県足柄上郡松田町近辺は、山紫水明という言葉がぴったりの自然環境でした。町内を流れる小川も、丹沢方面からくる川音川も、支流を集めた大きな酒匂川の水も井戸水のように澄んでいました。
6月頃の夜、あの独特の光を放つホタルは満天の綺羅星のごとくあちこちに飛び交っていました。開け放された小田急線の窓から車内に飛び込んだり、家の蚊帳の中に放して遊んだり、それは身近な生き物でした。
夏の風物詩セミ……。近頃はその姿もあまり見られず、その鳴き声すらよく聞こえません。松田町の少年時代は近所の「さくら畑」でメリケン袋を転用した長〜い竿付き用具を手に忍び足で木の下に近づき、時にはオシッコのような液体を掛けられながらセミ捕りに夢中になったものです。昭和15年神奈川区の幸ヶ谷小学校に転校しましたが、その学校の裏山とか浦島山にもたくさんのセミがいて、たまにはカブト虫も捕った覚えがあります。
トンボと人間が共存できる
源は水
酒匂川の上流に「酒水の滝」というのがあり、下流は小田原、中流が松田町付近。その川の流れを一部塞き止めて即席プールをつくって泳いだり、また、水の流れに乗り、下流に向かってフルチンのまま、ゆったり流されるのを楽しんだものです。お腹が空くと、近くの畑で即席おやつを調達。たまには川魚の掴み捕りをして帰りの土産にしたことも。
|
|
|
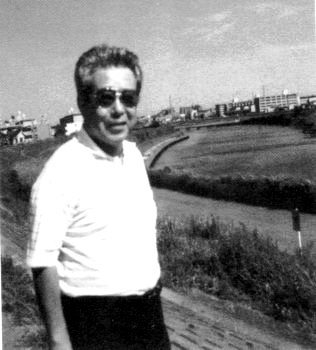
自宅近くの鶴見川岸を散歩する筆者
|
|
トンボ。いまは京浜急行の車両基地になっている神奈川新町一帯は、戦前はかなり大きな原っぱでした。
|
|
草ぼうぼうの所どころに水路や水溜まりがあり、鬼ヤンマ、銀ヤンマなどの大型トンボから麦わらトンボ、塩辛トンボ、茜トンボなどがいっぱい。
|
今でも横浜市内には50種類ほどのトンボがいるとか。トンボの生息には、およそ1キロメートル以内に小さな水溜まりや池が必要だそうです。1キロという距離は都会の公立学校がある間隔ですから、学校には少なくとも1個の池が欲しいものです。こうした僕ら人間のささやかな気配りで、自然の生き物と人間とが共生できる町になるのではないでしょうか。
西湘地区の湯河原で生を受け、幼少時代を相模湾で水浴、雄大な流れや自然がいっぱいの田園地帯で育てられた僕には人口340万の大都市横浜が果たして住み良いと言えるかどうか、自問自答するのです。
ただ救いは、自宅が市内唯一の一級河川、鶴見川に近接していることです。昭和33年9月の台風22号のような氾檻は今後百年くらいまで心配ないらしいという建設省の弁も聞いています。
観見川流域にはたくさんの「流域人ネット」もあり、それぞれの立場からいろいろな活動をしていますが、僕にはいま一つの感があります。それは「2人の孫と一緒にこの川の水に浸かって思いっきり遊びたい!」。そんな日が一日も早くきてくれることを願っています。
|
常盤 義和
湯河原町生まれの69歳。幼少年期を丹沢の麓、松田町と横浜・神奈川区で過ごす。県立神奈川工業高校卒業後、常盤一級建築士事務所を開設し約50年間、建設業界で活躍。港北区民会議の運営委員。余暇は歩くことと旅行。
|
|
|