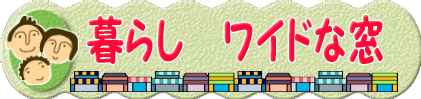食糧難時代の思い出
初土俵は昭和18年。同期生は仲がいいねえ。大晃(元小結、現阿武松<おおのまつ>親方)とか、先年亡くなった大内山(元大関)が同期。戦後の苦しい時期を共に暮らしたからね。
先日、日吉駅前でちゃんこ料理店を開いた大田山(元前頭)も同じ部屋の先輩だった。いろいろと相撲やその世界のことを教えてくれたいい先輩だった。星の点では苦労した人だったが、〝弓取式の大田山〟として毎場所沸かせていたなあ。

初代・横綱若乃花
|
|
先代若乃花(元横綱、現二子山親方)とは、食券をごまかしてメシを食ったりした。その頃は食事1回につきメシ1枚の食券が配られたんだが、何せ若い時だ。トンカツ20枚ペロリ平らげたこともあったくらいだから、1枚ではとても足りない。 |
そこで若乃花とどうやってメシを2杯食べるかって考えたんだ。食堂に行っておばさんに食券を渡さず「今、食券出したろ?」ってね。そのあとでもう1回行って食べる、なんてことやったよ。
また巡業も今とは違って移動はトラックだった。寒いし、寂しいもんだから歌ばっかし歌ってたよ。朝潮(元横綱、現高砂親方)も同じトラックでいつも一緒だった。
若い頃は弱かったけど…
今の相撲取りは、今日稽古すると明日にはもう強くなってないと効果がないと思うみたいだ。ところが俺はと言えば、最初弱くて弱くてしようがなかった。
あるとき、2勝2敗で千秋楽を迎えた。足もけがしていたんで、もう明日負けたら、大阪へ帰るって電話でおふくろに話した。おふくろも帰って来いって言うんだ。
ところが千秋楽をとってみると勝ってしまった。すると勝ち越しで番付も上がるし、相撲に未練が出てくる。それに親方も「こいつはものになる」というんで、遊んでいるとビシビシ叱られるように。それからは幕内に上がるまで負け越しは一場所だけだった。
とりわけ相撲をとっていて思い出に残るのは、五ツ洋(元前頭)を寄り倒しで破った。幕下からこれで勝てば十両、つまりは関取になれるという一番だった。まぁ、もっともこれは後に横綱や大関になった人でも同じだと思うけどね。
|
|
水戸泉入門秘話
7、8年前のこと、フジテレビの番組「ひらけボンキッキ」の子ども相撲の検査役をやっていた時、サイン会で高見山(現東関親方)と水戸へ行った。
サイン会の途中、ふと会場に目を遣ると、見るからに大きな男の子がいた。1メートル90くらいなんだ。そこで「いい体しているね。相撲取りにならないか」って声をかけて、ラーメンを一杯食わせた。あとの交渉は高砂親方に任せたけれど、それが今の水戸泉だよ。今まで何人か口ききで入れたけど、一番大物になったね。

初の外国人力士、大関・高見山
|
|

館内を湧かせる水戸泉の塩まき
|
|
私は東横沿線に縁があるんだ
戦争中、高砂部屋が空襲で焼けてしまった。ちょうど終戦直前、神宮で奉納相撲があった。代官山の同潤会アパートの裏あたりにいたことがあったね。そう代官山と言えば、高見山も両国に移るつい最近まで、旧山手通りをちょっと入った所にいたんだ。
また、終戦後最初の場所の際、1か月くらい、九品仏の幼稚園のところにいたときもあった。稽古は、あの広い境内でやっていたと思う。そのころのエピソードは、今思うと随分と悪いことだと思うが、火をたく薪がないので、お墓の塔婆をくべたりしたよ。あと尾山台、等々力の方へ野菜をもらいにリヤカーを引いて行ったこともあった。行く道すがらは、一面畑だった。
だからこっちに引越してきてから先輩に「自由が丘も大きくなりました」と言っても「なんだお前、あんななぁんにも無い所」なんて言われたよ。
|
|
大島広史さん(58歳)
高砂部屋 陣幕親方
元前頭筆頭・島錦 |
|
昭和3年、大阪生まれ。昭和18年5月初土俵。27年8月、初入幕。現役中はぶちかまし、寄りを得意とし、横綱吉葉山を破り、金星を挙げたことも。幕内在位31場所で35年3月引退。のち、15年間の長きにわたり審判委員を務める。
昭和33年から世田谷区奥沢5丁目に在住。
|
|