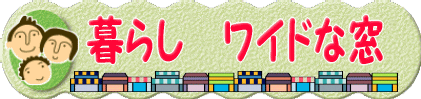山口さんも「江分利満氏」の中で、この会社に入社の当初、自分が(異邦人の如き感があった)と述懐しているが、そこで初めて関西人とその文化のアクの強い異質さをじかに体験することになった一種のカルチャーショックが、山口さんに『江分利満氏』の筆をとらせた一つの契機であったと思う。ちなみに江分利氏の勤め先は“東西電気”という名の会社であった。
新幹線で僅か3時間の距離を隔てて東と西にかなり異質の文化が併存して相互交流が行なわれていることは貴重なことだという趣旨の桐島洋子さんのエッセイをどこかで読んだことがあるが、僅か3時間の隔たりにもかかわらず、異質の文化や人間同士の相互理解ということになると、じつはそんなに容易なことではない。
作曲家三善 晃さんはそのフランス留学の体験から、根源的なところでの東西の理解などまず望めないと悲観的だし、俳人安住 敦さん(都立大在住)は久保田万太郎について(東京人にしか分らないものを持っていた人)と評している。
山口さんは私にとってそういう東京人らしい東京人であって、短い交友の間、私が山口さんに敬服したことは決して少なくない。
山口さんはつねに自分にもひとにも一生懸命な、折目正しい人で、どんなことであれすぐにその |

国立市の自宅で作家・山口瞳
撮影:岩田忠利 |
|
本質が見えてしまうし、何よりまずこの国の言葉の美しさを一人になっても守りぬくぞという侍のような文人である。山口さんはまたこよなくウイスキーを愛したが、そばで眺めながら私はよく思った。古風に言えばこの人は“酒道”の宗匠ではないかと。
20年の歳月が過ぎ、『江分利満氏』の舞台となった川崎・木月大町の界隈もかなりの変貌をとげた。
町のたたずまいは相変らず雑然としたままだが、雨が降ると長靴を穿かなければ歩けなかった泥んこ道、トラックが拳大の砂利石をはねて社宅の窓ガラスを割った道路もいまはすっかり舗装されて、つい先ごろ下水管が埋め込まれたし、6月がくるとカエルの声が夜空をつんざくばかりであった田圃も大方は家が建った。
山口さんがさまざまな思いをこめて住んだテラスハウスの社宅も、老朽化と手狭のためか、昨年溝酒なマンション風に建てかえられてしまった。
久しぶりに『江分利満氏の優雅な生活』を読みなおし、人生とは、かくも短きものかと愕然とするこの頃である。 (完)
|
|
筆者・今井茂雄さん(64歳)
サントリー音楽財団
理事
|
|
大正9年大阪生まれ。昭和22年毎日新聞社(大阪)に入社後、昭和36年サントリー入社。宣伝部の制作室長、宣伝部長を経て、昭和55年定年退職。現サントリー音楽財団理事。
川崎市中原区伊勢町在住。
|
|