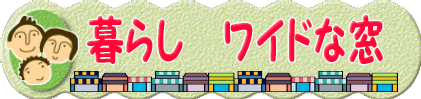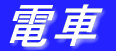|
今回は目蒲線に乗っていただきたい。3000系と呼ばれる古いタイプの電車がやって来たら、屋根にパンタグラフのある車両を選んで、車端部の戸口付近に立ってみてほしい。
発車すると、床下から轟音とともにプルプルとものすごい振動が伝わってくる。足の裏がむずかゆくなるような振動、というよりも音そのものである。これこそ、古い電車独特の「つりかけ式」と呼ばれる駆動装置から出てくる音なのである。
東横線をはじめ、現在の日本の電車の多くは、動力源であるモーターをバネの上にふんわりと支えた「カルダン式」と呼ばれる駆動装置を備えている。一方、目蒲線や池上線の「つりかけ式」は、モーターが車輪をガッチリと抱きしめており、回転を伝える歯車のかみ合わせもやや粗っぽい。
|

イラスト:中岡 奈津美(妙蓮寺) |
|
|
|
|
昔はみなそのような仕掛であったから、電車は乗心地が悪いものと相場が決まっていた。東横線に「カルダン式」の5000系が登場したのは昭和29年で、その4年後、東海道線に特急「こだま」が走るに至って、ようやく電車の乗心地が一般に評価されるようになったのである。
昨今では「つりかけ式」は珍しく、その音色を足の裏で聴くために、わざわざ目蒲線、池上線を訪れる熱心なファンも少なくない。
次は大井町線に乗換えていただきたい。本数が少ないので乗れるチャンスは少ないが、6000系というステンレスカーが独特の音色を奏でるので有名である。
6000系の駆動装置は、「中空ピニオン平行カルダン1電動機2軸駆動方式」という複雑なもので、モーターの回転がいくつもの歯車を介して前後2軸の車輪に伝わる仕掛けである。音色もそれなりに複雑で、捨て難い魅力がある。
このように、電車の駆動装置が奏でる音色は、形式によって微妙な違いがあって、耳(場合によっては足の裏)をすまして聴いていると実におもしろい。特に7000系などは、音色によってモーターを作ったメーカーを識別することさえできる。
電車の音の聴き分けも、テレビドラマの効果音に文句をつけたくなれば一人前である。
|