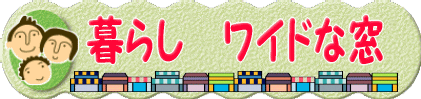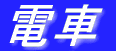|
『どですかでん』という映画があった。主人公の知恵遅れの少年は、「ドデスカデン、ドデスカデン、……」と口ずさみながら、都電の運転士のまねをして街を走り回る。筆者も幼少のみぎりは東横線の音まねをして、「タタントトットトン、タタントトットトン、……」とやっていた。そして多摩川の鉄橋を渡るときは、「サザンゾゾッゾゾン、……」となり、芸の細かい所を見せていた。
これらの音は、車輪がレールの継目を通過するときのものである。レール一本の標準の長さは25メートルであるから、車内で時計を見ながら音を数えれば、電車のスピードがわかる。10秒間に聞こえる「タタントトントトン」の数を9倍すればよい。7回ならば時速63キロである。興味のある方は計算式を導いてほしい。(中学1年程度)
|

イラスト:中岡 奈津美(妙蓮寺)
|
|
|
|
|
最近はレールを何本も溶接して長くした「ロングレール」が増え、あまり音がしなくなってしまった。騒音・振動防止の見地からは結構なことだが、おもしろさは半減してしまう。所々に短いレールや複雑なポイントが挿まることによって、単調なリズムが変化し、通い慣れた区間なら目を閉じていても場所がわかるものである。
もっとも本誌スタッフの中には、そのリズムを子守歌代わりに、夢の中で日吉を通り過ぎるお姉さんもいるが……。
音は線路だけではなく、電車の種類や乗車位置によっても違ってくる。東横線は決して「ドデスカデン」とは聞こえないし、7000系と8000系を比べても音色が違う。線路を楽譜にたとえれば、電車は楽器ということになる。また編成の先頭部、連結部、最後部で、それぞれ聞こえるリズムが異なる。
筆者が大好きな音は、7000系の下り急行(今は無い)が元住吉を通過するときのもので、連続4か所のポイントを一気に渡る音を連結部で聴いていると、思わずうっとりしてしまう。
ここまでくると“ほとんどビョーキ”であるが、鋼(はがね)がぶつかり合って奏でるこの軽快なリズムを、美しいと感じたからこそ、筆者は機械技術者への道を選んだような気がする。
● ●
次回は楽器について続編をお届けしよう。
|