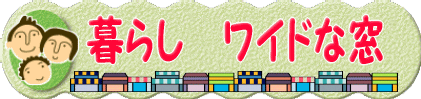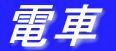|
大倉山の梅林に花が咲き始めると、東横沿線にも春がやってくる。昔は梅の季節になると、急行が大倉山に臨時停車するという粋なダイヤを組んでいたが、いつのまにかやめてしまった。
3月から5月にかけて、東横沿線のあちこちに薄紫色の小さな花が咲き乱れるのをご存じだろうか。車窓から見える場所で最も群生しているのは、都立大学と自由が丘の中間地点で、線路際の斜面を薄紫に染めあげている。
|

イラスト:中岡 奈津美(妙蓮寺)
|
|
|
この花の名前を調べてみると、ムラサキハナナ、ショカツサイ、オオアラセイトウ、ハナダイコンといろいろある。中国原産のアブラナ科の多年草で、江戸時代に渡来したといわれている。このように、外国から渡来して繁殖し、野性化した植物のことを、帰化植物という。
|
|
帰化植物の多くは、その種子が船の積荷などに付着して海を渡り、上陸してからは鉄道によって各地に運ばれ、強い繁殖力で野生していった。ヒメジョオン、ハルジオン、セイタカアワダチソウなどがそれである。北米原産でキク科のヒメムカシヨモギぐさは、その名もズバリ 「鉄道草」という別名を持っている。
鉄道は人や物を運ぶのが本業であるが、はからずも運んでしまう場合がある。上野駅に到着する長距離列車が屋根にいっぱい雪を積んでくるのがよい例である。東横沿線に群生するムラサキハナナも、その種子が電車の車体や乗客の衣服に付着して運ばれ、こぼれ落ちて根づき、さらに子孫を殖やしてあちこちに美しい花を咲かせているのだ。
移動・定着・世代交代という点では、人間もまた同じである。東横線が開通した頃、沿線の人口はわずかだった。現在の住民の多くは、全国各地から移り住んだ人か、その2代目、3代目である。そして人々は、電車という不特定多数が利用する乗物を媒介にして、さまざまな出会いを生み出してゆく。
『とうよこ沿線』今年のテーマは、「出会いの予感…『ゾクゾク』」である。
みなさんもすばらしい人にめぐり合い、ムラサキハナナのような可憐な花を咲かせてほしい。
|