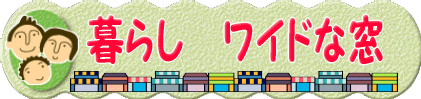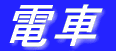|
「電車まんだら」連載第5回にして早くも脱線! 今回はバスのはなしをしよう。
東京オリンピックの前の年、私は東京学芸大学付属世田谷小学校に入学した。日吉の自宅から深沢の学校へは、電車とバスを乗り継いで通学した。ランドセルを武器に朝の満員電車に乗ること、そして学校のフルネームを覚えることにはひと苦労したものである。
毎朝田園調布駅から乗ったバスは世田谷区民会館行き(現在とほぼ同じコース)で、等々力小学校の停留所で降りて歩いた。当時のバスは、ボンネット形とリヤエンジン形(箱形)が半々で、私はボンネット形が大いに気に入っていた。
|

イラスト:中岡 奈津美(妙蓮寺)
|
|
|
|
|
正面は“剣道の面”のような恰好をしていて、両脇に砲弾形のヘッドライトがにらみをきかしている。曲がり角に近づくと方向指示器がシャキッと飛び出し、オーバーハングが長いのでお尻を振るようにして曲がってゆく。そしてミンセイ(現在の日産ディーゼル)の2サイクルエンジンが独特のうなりをあげていた。
当時のバスには女性の車掌さんが乗っていた。今思えば20歳前後の娘さんだったのであろうが、小学生の私にはおばさんに見えた。九品仏の踏切を渡るときは、雨の日も風の日もバスを降り、笛を吹きながら小走りに誘導していたその姿は、とてもたのもしく映ったものである。また帰りのバスの中では、下校途中の解放感から大声ではしゃいだり、道草をくって泥靴のまま乗ったりして、車掌さんに叱られたこともよくあった。
バスが終点に近づくと車掌さんが前後の行先幕をクルクルと変えるわけだが、リヤエンジン形の場合は後部座席のうしろにかなりのスペースがあって、背の低い車掌さんは座席に膝をついてクルクルやっていたのを思い出す。そういえば一度、そのスペースにランドセルを置いたまま家まで帰ってしまったことがある。
通学のバスの車内は遊び場であり、社会勉強の場であった。最近の小学生が放課後、塾へ直行する姿を見ると、何やらかわいそうな気がしてくる。
|