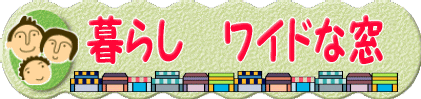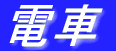|
「次は元住吉でございます。元住吉では車両点検のため、車両の交換をさせていただきます。どなたさまも……」
この放送で、立っている人はいっせいに戸口へ移動するので、坐っている人は遅れをとってしまう。乗換が終わって車内を見回すと、両者の顔ぶれが逆転している。そんな“小さな革命”が、毎日くり返されているのだ。
元住吉が近づくと車窓が気になるのは小生だけではあるまい。工場が長津田に移転する前は、玉電を除く東急全線の電車が元住吉へやってきたから、きょうはどんな電車が見えるかと楽しみだった。
|

イラスト:川名亜佐子(妙蓮寺)
|
|
|
|
|
やがて飲酒の習慣が定着してからは、元住吉行終電のお世話になる機会が増えた。泥酔者の寝息と脂粉の香りが充満する車内で、ひとり最後部の架線電圧計とにらめっこしているお兄さんがいたら、それは筆者である。
電車は文字通り電気で動くわけであるが、たいていは電気を使い捨てにしてしまう。
ところが東横線の電車は、走るときに一度使ってしまった電気を、止まるときに再び電気として架線に送り返す機能を持っている。これを回生ブレーキという。架線に戻された電気は他の電車が再利用するから、省エネルギーの決定版といえる。
さて、終電車と回生ブレーキとがどう結びつくのか? そもそも回生ブレーキは、近くに電気を食べてくれる電車がいないとお手上げなのである。深夜になると、電車は次々と車庫に入ってパンタグラフを降ろしてしまう。元住吉行終電ともなると、架線に戻された電気は行き場を失い、回生ブレーキが効かなくなる現象が生じる。(すぐに空気ブレーキに切換わるので安全性に問題はない)
そのようすは運転台の架線電圧計を見ていると手に取るようにわかる。針がピクンと振れ、「あっ、またやった」などと言っているうちに、だんだん酔いがさめてきた。
「あれ、今晩は横浜で呑んだはずなのに、何で下りの終電に乗っているんだろう?」
元住吉に着いた終電車は、千鳥足の乗客をホームに降ろし、赤いランプの尾を引いて車庫の闇に吸い込まれていった。
|