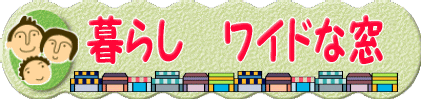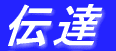|
忙しい最中に他人からダラダラと長電話がかかったりすると、ついイライラしてしまいます。思わず「要するに何が言いたいんだ」と口走りたくなります。
話が簡潔にならない原因はいろいろありますが、次の2つがポイントです。
1つは伝える態度として「結論をなかなか言わない」こと、もう1つは音声化段階で「話体文が長い」ことです。
昔から日本人は「起承転結を名文の基本として大切にしてきました。「結」は縷々述べてきて意を尽くした後、最後の極め付きにそっと出してくるのが長いというのでしょうか、スピーチでもよくこうした話し方に出会います。しかしこれは「書き言葉」の場合のこと。話し言葉ではこの方法は分かり難いのです。話し言葉ではまず「結」から言うことです。
「結−起−承−転−結」の組み合わせではじめて聞き易い話が成立するのです。「結」という言葉を使いましたが、場合によりいろいろです。
言い換えれば一言で話の内容が見通せる言い方とでもいうものです。「全体のイメージ」、「話そうとする主題」など言い方はいろいろですが、要は「何のことだ」を早く提示することです。
|
|
話し言葉は声の言葉です。生理的に聞き手がいちばん直截に聞こえる言い方を工夫しましょう。
もう1つ、文の長さの問題も起承転結と関係します。「何が、どうして、こうだから、こうなって、こうなのだ」。話し言葉は息づかいの関係から一文の長さが短ければ短いほどいいのです。で話体文は「何が‥…・どうした」の主述をできるだけ接近させること、その短い文の積み重ねで論理を展開していくことです。書き言葉のように一文で論理を尽くそうとせず、短い一文一文を起承転結に割り振って話体を組み立てることが秘訣です。
|
また、接続詞類は文中につけないこと。「〜ですが」「〜けれども」などの言い方は文を長くしてしまいます。
|

絵:阿部紀子(市ヶ谷)
|
|
|