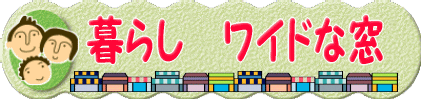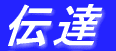|
「最近の新人サラリーマンは、声が小さいですね」。企業研修の場で研修担当者からよく聞く言葉です。企業によってはその対策として、大声で「おはようございます」と、先ず発声練習から研修を始めるところも多くみられます。
たしかに「声が小さい」という傾向は近年増加傾向にあるようです。これはなにもサラリーマンに限ったことではなく、NHK日本語センターの先生へのアンケートの結果では、いまの子どもたちの声が弱く小さいという傾向もみられます。
ところで私たちの声は、まず声帯を振動させるお腹からの呼気の強さに左右されます。第二にその振動で起こる声の響きを拡大させる共鳴が関係します。共鳴は主に声帯から口までの声の通路(声道)が影響します。呼気がしっかりしていれば声も力強くなります。声には個人差があり、明るさ、暖かさ、暗さ、冷たさなどは声の質に関係する部分が多く、大小には余り関係ないように思われがちです。
しかし声が弱かったり、小さかったりすると、一般に声調が低くなりやすく、それだけ相手に伝えようとする積極的な意欲が欠けているように受け取られがちです。相手にしっかりと伝えたいのであればそれなりの声の力が必要になってきます。
|
|
その声の力を鍛えるポイントとしては、「自分の声を少なくとも4〜5メートル程度先の人にしっかり届ける気持ちで話すこと」「屋外で騒音に負けない声を作ること」「自分が日頃普通と感じている声のトーンより少し高めの声で話す習慣をつけること」などに心がけてみることです。
|
身体全身で言葉を発することの習慣づけをするということです。単なる喉声でその場しのぎの会話や応対をしていたのでは声の力もつきません。相手との応答で「話を聞く意欲、話す意欲を持つこと」が声の力を作ります。
|

絵:阿部紀子(市ヶ谷)
|
|
|