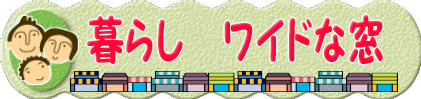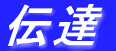|
アナウンサーへのお世辞は、大抵「話し方の歯切れがいいですね」と相場が決まっている。こう言っておけば無難だろうが、何十年もこの仕事をやっていると、少しこだわってしまう。
日本語の音は、一音一音の切れ目が母音で終わる「子音+母音」という組み合わせになることが多い。五十音をローマ字で綴ってみると分かるように、カメラ(KAMERA)、コトバ(KOTOBA)など、それぞれ「A」や「0」の後に切れ目ができる。そして 「KA」や「ME」のそれぞれの音を調べてみると、K、Mの子音はわずかなきっかけを作る程度。寿司だねが子音で、ご飯が母音という関係だ。
つまり母音の口構えが音の骨格をはっきりさせていると言ってよい。では一音一音をはっきり発音しさえすれば歯切れがよいかというとそうではない。それではコンピュータの合成音声のように間の抜けた不自然なものになって、日常の言葉の発音には聞こえない。
言いかえれば、歯切れの良さを支える要素にはもう一つ、言葉を作るそれぞれの音のつながりに合わせて、いかに滑らかに音から音へ渡り歩く発音ができるかが決め手になる。
|
|
「新横浜」という地名を丁寧に発音しすぎると、「シン・ヨコハマ」となることがある。これは「ン」をはっきり言い過ぎるためで、かえって不自然に聞こえる。
日本語の言葉としての馴染んだ発音があるわけで、それを苦もなく声に出している時が一番歯切れがいい発音と言えるのではあるまいか。聞き手に「このアナウンサーは口が良く回るなあ」と感じさせている間は、本当の歯切れの良さとは言い切れない。
|
ところで日本語センターのスタッフが発案した発声練習に「パラピリプルポロぺレ」というのがある。
昔から「呂律が回らない」とよく言ってきたが、ラ行のこの発声練習を重ねれば、歯切れも人一倍良くなること請け合いと自賛している。
|

絵:阿部紀子(市ヶ谷)
|
|
|