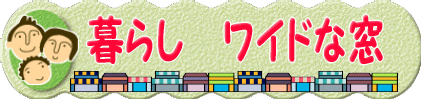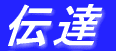|
最近、「ニュースのキャスターやアナウンサーのしゃべり方が早口になって分かりにくい」と、よく注意される。
たしかに戦前から戦後、そして最近年々その傾向は続いている。終戦後、旧満州から復員する軍人が、船中で久しぶりに当時のNHKの冗談音楽番組を聴いて、日本語が変わったのかと心配した話は有名だが、その後も早口の度は増している。
NHKアナウンス室が調査した資料によると、30年前に1分当たり400拍(句作をする時の要領で、かな1文字を1拍と数える)だったものが、現在では平均500拍近くにまで増加している。
最近テレビによく登場する早口組をあげると、定評のある久米宏氏が700拍近いし、桜井洋子アナが540拍、川端アナが530拍、黒柳徹子さんは490拍を数える。平均して500拍にはなっているといってよいようだ。拍数は文字数の約1・3倍だから、文字数にすると1分に380字ぐらいしゃべっていることになる。
そもそもこうした早口傾向はどうして出現したのだろうか。理由の第一は、日本人がテレビやAVメディアに馴染んで情報を聞き取る力が戦前に比べて格段に向上したことが上げられる。
|
|
第二は情報の提示方法の多様化によって、音声だけでなく文字やイメージを有効に駆使して内容理解を助けていることも大きな要素である。
またそれに伴って、急速に増える情報量を限られた時間内により多く詰め込みたいという欲求も一方で作用している。
しかし早口なら情報が多く理解できるかというとそれはまた別で、早口でも理解できる話し方、読み方が必要なのだ。
|
その鍵は、間の問題だ。他にも発音や口調などいくつかの要素はあるが、間をいかにうまく作るかが、分かる、分からないの決め手になる。いわばプロの技の発揮のしどころ。キャスターもアナウンサーも「間」抜けでは務まらないのである。
|

絵:阿部紀子(市ヶ谷)
|
|
|