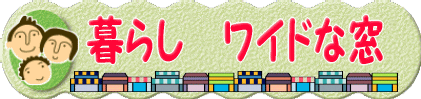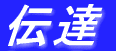|
仕事柄「演説やスピーチのコツは何か」とよく聞かれる。そんな時は必ず「調子をつけるな」と言うことにしている。これまでに昭和の名演説をいくつか聞いているが、それらは名調子ではあっても必ずしも名演説とは言えないものが殆どだ。
ここで言う「調子」とは、話の口調、つまり文全体の抑揚(イントネーション)のことである。名調子といわれるものを分析すると、その人の個性というよりも、同じサイクルの音の高低を繰り返す調子が圧倒的に多い。
こういう節は、人を心地良い気分にさせるが、反対に伝える意味内容を分かりにくくする場合が殆どである。
この原因はいろいろあろうが大抵は、その演説が前もって用意した原稿を読み上げていることが多いからだ。書き言葉は、目で見た関係だけで文体を書き連ねていくため、声に出す生理的限界を無視しがちだ。普段の会話につかう息の長さは、ほんの1秒か2秒。それが演説の時だけ5秒も10秒もの長さの
|
|
文に合わせて声を出そうとして、変な句切り方や声の上げ下げになりがちだ。聞き手にとっては名調子どころか“迷調子”とならざるをえない。
では本当の意味での名調子とはどういうものか。一言でいえば、「原稿に頼らず、要点をメモして話す」ことだろう。そうすれば日頃の自分の息づかいそのままで、その人の個性が発揮される。もちろんそうなるには少々の訓練がいる。話の組み立てや音声化の基本も身につける必要がある。今までの我々日本人は、こういうことに無関心で声の言葉を無視してきた。
口下手が人柄の良さのようにも言われたりした。
|
しかし、さすがに近頃は国際化時代、「調子良く」ではなく、「しっかりと論理的に話す力」が求められている。経営のトップがスピーチの研修を受けに来る時代である。
ひょっとすると近い将来、本当の意味での日本人の名演説集が出来上がる時代が来るのでは……。
|

絵:阿部紀子(市ヶ谷)
|
|
|