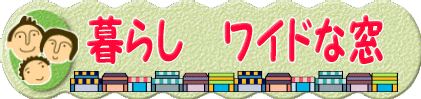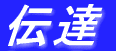|
アクセントは、その土地の表情をあらわすとよく言われる。
特に、地名となるとその特色がよくあらわれる。例えば、長野は、地元ではナガノと発音するが、東京人はナガノと音の高低が逆になる。(赤字部分は高音)山口県の萩も、地元がハギで東京人はハギ。家康の地元、岡崎は、かつてNHK大河ドラマで有名になったが、ナレーションでオカザキと発音したら、地元からオカザキだと抗議を受けた。
地名のアクセントはその地域社会全体の共有財産のようなもので、それを普段と違う形で発音されると、町の形を変えられたような気になるものだ。
そう考えると、東横沿線の日吉や綱島は、ヒヨシとヒヨシ、ツナシマとツナシマの、それぞれどちらがこの町の顔にぴったりなのだろうか。
しかしこのことは、仕事で使うアナウンサーにとっては大変難しい課題を抱えることになる。
地元に馴染む言い方は、一方で全国、他の地域の人には必ずしも耳慣れたアクセントとは限らないからだ。この両者の狭間で、仕事人アナウンサーは、しばし悩むことになる。
|
|
近ごろは、ローカルニュースは地元型、全国ニュースは東京型と使い分けを考えたりしている。
ところで、東京方言の場合、ある種の言葉は口に馴染むにつれて平板化していくとよく言われる。地元の地名が平板化するのはその例かもしれない。外国語のアクセントや専門語などもそういう傾向のあることが報告されている。
それならばと、人名もそれにならって発音してはと思うのだが、これはなかなか難しい。宮田という名のミヤタとミヤタ、平田のヒラタとヒラタ、当誌編集長、岩田氏のイワタとイワタなど、にわかに判断しかねるものもあり、相
|
手の顔色ならぬ声音を確かめてからでないと口を出すのがはばかられる。人名アクセントは、その人と馴染みだからといって平板化していいというものではないらしい。
|

絵:曽我二郎 |
|
|