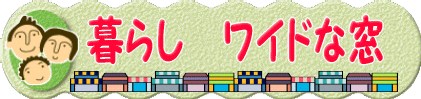|
同じように、慶応3年(1867年)に創刊された英字一『ジャパン・ガゼット』が開港50年を記念して発刊した『ジャパン・ガゼット横浜五十年史』にも第1号らしきホテルが紹介されている。アーサー・ブレンドという居留民が1860年代の横浜を回想している中に、本町通り85番辺りにある「コマーシャルホテル」という3流ホテル以外にホテルはなかった、というくだりがあるのだ。
どちらにしても、初期のホテルはかなりお粗末だったようである。先ほどのアーサー・ブレンドは、「三流ホテルしかないので、横浜を訪れた人を居留民が自分の家でもてなした」といっている。「田舎に泊りがけで出かける時には、陶器類、炊事道具にコックまで連れて行った」とも。
また「横浜ユナイテッドクラブ」には毎晩、雑談と一杯のシェリー酒やビターズ(苦味酒)を楽しむため、朗らかな居留民たちが集まってきて、夕食前のひとときを過ごしたという。
|
華麗なグランドホテル(写真右上)
明治6年には、ホテル・ニューグランドの前身、グランドホテルが海岸通20番にできた。今のちょうどマリンタワーの隣あたりである。1階に食堂、料理室、読書室があり、2階には室がおよそ30つくられた。
当時としては、かなりモダンなホテルで明治初年に発刊された写真入り英字新聞『ザ・ファー・イースト』にも「居留地内ではもっとも美しい建物のひとつ。毎夜、楽隊が楽しい音楽を奏でた」と紹介されている。
明治22年に経営者が変わると、新館が増築され、自家発電の設備まで整った。
他にも、「オリエンタルパレスホテル」「ホテル・フェニックス」など、この時代になると、今の山下町と同じように、ホテルが建ち並んでいたようである。
|

関東大震災で崩壊した旧居留地の山下町。後方がグランドホテルの外壁 |
|
新しいグランドホテル
大正12年の関東大震災は、この地区にも決定的なダメージを与えた。「グランドホテル」も「クラブホテル」も崩れ去り、どこもかしこもガレキの山と化した。ちなみに山下公園は、このガレキで作った公園である。
震災後、被災した多くの外国人を救済するため、また衰退しだした横浜貿易に歯止めをかけるために、横浜市は復興計画の中に外人ホテル建設を盛りこんだ。こうして作られた新しいホテルが「ホテルニューグランド」である。
大正15年12月1日、山下町10番に開業。だから、グランドホテルとは、直接関係があるわけではない。喜劇王チャップリン、野球のベーブルース、そして連合軍司令官マッカーサーと数多くの有名人が泊ったこのホテルも、今や老舗中の老舗となった。
|
|
|