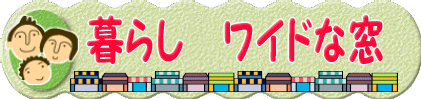|
中区末広町に「太田なわのれん」という牛鍋屋の老舗がある。このお店、老舗も老舗。なんと、横浜の歴史を綴った『横浜市史稿』の文明開化編に牛鍋屋(シキ焼き屋)の草分けとして紹介されているのだ。
明治元年の創業時と同じ場所で、今は5代目故高橋富美男さんの妻ハナエさんが店をとりしきっている。まずそのお話を聞こう。
――初代の音吉は石川県の能登から一旗あげようと横浜へやってきて、まず吉田橋(関内駅前)あたりで牛串焼きの屋台を始めました。開港当時ですから「牛肉を食べると四つ足になる」なんて時代です。
なにしろ昨日までの貧しい漁村横浜は、一夜明けると、野心に燃えた外国人、武士、商人のごった返す街となっていた。だから居留地の入り口にあり、そういう人々を相手にした彼の店も結構、繁盛したようである。
――それでここに店を構えました。今度はふつうの日本人相手だから、最初は売れなかったとか。それでも馬車引きや大工さん、遊郭帰りの人々が食べだしてね。気味が悪いけど試しに一回食べてみようみようなんて。その頃、小港町の方に外人のための、牛馬を殺して皮をはいで肉にする“と殺場”があって、まあ、カス肉を安く仕入れてきたそうです。
こんな時代に〝牛肉が売れる〟と見込んだ音吉氏。先見の明があったようである。
――この初代は大酒飲みで頑固者の変わった人だったとか。客には体にさわるといって3合以上は飲ませないのに、自分は朝からほろ酔い気分で仕事。肉を薄く切るなんて面倒だとブツブツ大切りにして牡丹鍋(猪鍋)のように味噌で煮込んだら、これが評判になったそうです。
明治17年(1884年)発行の「横濱一等流行店濁案内」という本に早くも名を連ねている。日本人の新し物好きは今も昔も変わらないようだ。
|
――店の前の道路を昔のことだから馬車が通るわけですよ。ハエもたくさん飛んでくる。それを防ぐために入り口に長い縄でできた“のれん”を垂らしていました。一時、道路の整備のため太田(現西区赤門)に店を移していたこともあって、《太田なわのれん》と呼ばれるようになったと聞いています。
創業時は牛鍋5銭、お酒2銭5厘、ご飯2銭でした。
今ライスは250円くらい。とするとその2.5倍、つまり625円で牛鍋(スキ焼き)が食べられる計算になる。現代の〇〇屋の牛井並の安さだ。ちなみに今のお品書きでは、牛鍋3千6百円。コースは6千5百円から。といっても、最上のヒレとロースだから当然のお値段。
|
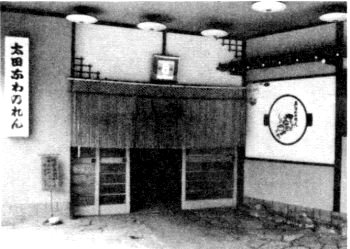
現在も縄のれんがかかっている「太田なわのれん」 |
|
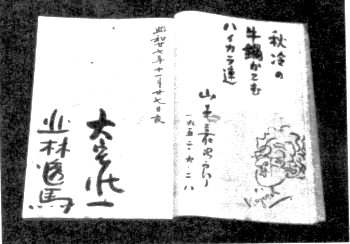
芸術品のような“左院帳” |
|
――故獅子文六さん、故大宅壮一さん、高木東六さん……今もいろいろな方が見えます。横浜にゆかりのある方が多いかしらねえ。
ここのサイン帳は「左院帳」という和綴じの帳面である。映画監督の山本嘉次郎、作曲家の古賀政男、評論家・大宅壮一ら著名人の毛筆サインと素晴らしい手描きイラスト入り。なかなかの芸術品である。こんなところにも何となく〝明治〟を感じてしまう。
さあ、文明開化を舌で感じてみたいあなた、一度「太田なわのれん」へお出かけになってみては?
|
|
|