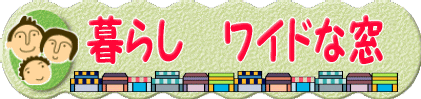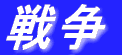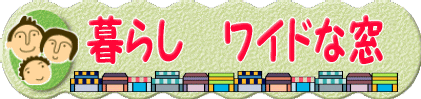父と弟は家を守り、家族の女5人で避難
今から50年前の昭和20年当時、神奈川郵便局電信課勤務の主人は〝中支〟(現在の中国・中部地方)に応召中。家族は、学齢期の長女・次女・3女、両親と青年学校生の弟でした。
その年、昭和20年5月29日朝8時半頃、連続してけたたましく鳴る警報のサイレンに非常事態を知りました。
|
自宅の防空壕に入る間もなく、わが家の2階の屋根が直撃弾を受け、燃えていました。危険を感じ、近くの神明神社へ避難。頭上の敵機の音を聞いては、じっとしていられず、今度は神奈川小学校へと移りましたが校舎には入らず、また第一国道へ出て神奈川公園へと逃げました。父と弟は防火のために家に残ったので母が次女を、私が3女を背負い、6歳の長女は健気にも長い長い国道を歩き続けました。
ヒューッと不気味な音とともにパラパラッと油のようなものが空から撒かれる。と、焼夷弾が星のように降り、周囲の建物を次々と焼いていきます。防空頭巾の上から軽い布団をかぶり、防火用水を見かけるたびに水を掛け合い、あちこちに狐火のようにチョロチョロと炎が立ちこめるのを避けては走りました。公園は避難者でいっぱい。お互いに、はぐれないように名前を呼び合いながら横浜中央市場へ。
|

昭和18年、隣組で防空演習のバケツリレー
現東神奈川2丁目で 撮影:著者・山室まさ
|
|
非常時の兵士・大学生・船員、その人間模様
その途中、4~5人の兵隊を連れた将校さんが私たちに「“10メートル岸壁”はどこか?」と尋ねたので、勝手知った土地のこと、指差して教えたところ、「それっ!」とサーベルの音とともに走り去ってしまいました。正直言って、恐怖と不安におののく私たち住民を助けてくれると思っていましたのに……。
横浜中央市場の広場は空き箱や包装紙やらが渦高く積んであり、もし火がついたら危険と察知し、船ならばと思い、岸壁に逃げました。幸い修理船が一隻あり、避難者50人ほどを乗せて岸を離れてくれました。油じみた海面には木片や浮いた油に火が付いているので、船員さんたちがそれを竿で払いのけ沖に出ました。
神奈川の町を振り返ると、炎や真っ黒い煙で何も見えず。ただ、ドドーン! ガターン! と不気味な音が響いてくるばかり。「あ~、助かった」と思ったのは、やっと腰を下ろせた貨物船の中でした。
この船の中に大学生3人がいて、超満員の船内でお弁当を食べ始めました。それを母が見かねて、
「学生さん、小さい子供もいますから、後ろを向いてください」
と頼みました。10人ほどの子供たちが携帯非常用の何十粒かの煎り大豆を食べ始めると、船員の方が、
「これは船員の食事ですので子供さんたちの分しかありません」
と分けてくださいました。思いがけないご親切と子供たちが無心に食べる姿に親たちの目には涙がどっと溢れたのでした。
初老の紳士の叫び
夕方近くに轟音もおさまり、船は着岸、避難者は渡し板を渡って陸に上がりました。今日、折角命拾いしたのに海に落ちないようにと子供たちの手を取り板を渡り、最後の私が土を踏んだ途端のことでした。
突然後方から、
「皆さ~ん!」
と大声。一斉に振り向くと船の甲板から背筋のピンとした初老の紳士が呼びかけていました。
「私は東京で2回、きょう横浜で1回、計3回も空襲に遭いました。皆さんはたった一度のことで挫けてはいけません! この船は芙蓉丸、浅野ドックで修繕中です。命永らえたらこの船のことを忘れないように。さあ、万歳で別れましょう!」
カーキ色の戦闘帽にゲートル姿の紳士と船員たちを一同が見上げると、その人は帽子を高々とあげて、
「天皇陛下バンザ~イ!」
陸に上がった避難者も大声でそれに応えて何度も唱和し、別れを惜しみました。
|

イラスト:石野英夫(元住吉) |
|
町に入ると、その風景は朝とは打って変わり、丘の上の幸ヶ谷小学校だけを残し見渡す限りの焼野が原。道路脇の溝には少しの水でも求めてか、真っ黒になった骸の群れが重なり合っていました。初めて〝生〟を実感し、しつかりと大地を踏みしめた気持ちで、その異常な光景が気味悪くはありませんでした。
船でのあの会話、一挙手一投足、目に焼き付いている恐ろしかった光景などは、忘れようもありません。あの勇気、あの親切心を学びとって生き抜くことが感謝と報恩と思い、今までそれを忘れずに助け合って生きてきました。
空襲体験記 おしまい
|