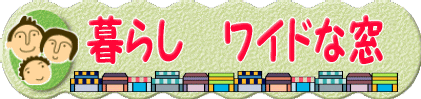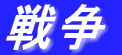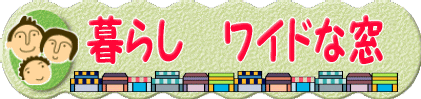中原区を襲った爆撃
|
昭和20年4月15日、9時30分ごろ、突然、警戒警報発令……。私は急遽、火の見やぐらに登って鐘を打つ。10時3分、空襲警報発令、退避信号の鐘を打つ。
今度は危ないと思っているうちに、上丸子天神町探照灯陣地から発する光の中、1機が光ったと思ったら、ザーッと落下の音が聞こえ、新丸子駅前のダンスホールに落下し、見る見るうちに火の海となった。
そのうち第2波、平間ガス橋付近、焼夷弾が落下し火災が起こる。直後、下丸子の北辰電機被爆、これより蒲田・大森・川崎方面が火の海となった。
|

多摩川の六郷橋から見た、被爆から8カ月後の第一国道を挟む
川崎市内
昭和20年12月撮影:石渡久吉さん |
|
第3波により、井田・元住吉・法政大学予科(現法政二高)付近が被爆。富士通信機製造を狙った爆撃により、神地通りに焼夷弾落下。下小田中の沖電線爆破、火災発生。
本部員は25名であったが、空襲時は市川団長、尾上副団長、加藤一男部長以下、井田の青山泰さん、下小田中の小島実さん、市ノ坪の横山賢二さん、そして小倉の佐伯さんと私であった。
この空襲で南武線北側の日本石油が焼け、その煙が中原警察署にまで広がる。同警察署前の大野青果市場庭中に焼夷弾落下、この火は中原郵便局の爆風よけに燃え移り、警防団員の横山賢二さんが大声で叫び、火を消し止めた。その働きには目を見張るものがあった。
被爆後、中原署前の半分焼け落ちた民家に子供2人を抱えたまま母親が死んでいた。畳が横に立てかけてあったが、爆風よけにしていたのだろう。
朝になり、今井神社表の小宮武雄さん邸内に50キロ不発弾があるのを発見し、中原国民学校(現中原小)に駐屯していた軍隊に連絡し、処理する。
|
小杉陣屋町の原正巳邸内と現中原中学校前の畑の中にも不発弾あり。上小田中神地1444番地で大型爆弾が爆破する。その爆破の穴は直径5メートルに及んでいた。私の友人、原喜八氏は消火作業中に直撃を受け爆死され、隣家の方々も2〜3人の犠牲者を出した。
上小田中の砂糖問屋・島甚の焼跡に、焼けて黒くなった砂糖が道路のアスファルトのようにドロドロと流れ出ていた。警備員に追い払われながらも、うろうろする子供たちが泥だらけの砂糖をしゃにむに口にほおばっていた。その姿は、現代の子供たちにはおそらく想像もつかないことだろう。
|

イラスト:石野英夫(元住吉) |
|
非常時に身を挺して活動した人たち
警防団本部から中原第5分団本部に伝令に行くと、分団長の西村義正氏や小野三郎氏らがいた。小野さんは丸子境の自宅が焼けてしまっても平然と事務を執っておられた。その姿を私は尊いと思った。西村分団長から「避難者は200名ぐらい」と聞き、本部からその分の炊き出しのむすびを国民学校まで届けた。
ガソリンポンプ(当時の消火ポンプ)が小杉1丁目の医大グラウンド北側に、燃料が無く、放り出されていた。消防署に行けばあると以前聞いた覚えがあるので直行し、平野署長から1缶を受け取り、消火作業ができた。
大空襲の中、小林連太郎さん、荻野長太郎さん、西村市蔵さんたちの協力で小杉1丁目の全焼を免れ、平素は大きなことを言ってもみんな逃げてしまった人の多い中で、この人たちの郷土愛には頭が下がった。
新丸子ダンスホールから出た火は新丸子二業地から丸子通りに焼け移っていき、人々はことごとく退避して全焼してしまった。逃げた人の中には、多摩川河原に布団をかぶったまま死んでいる人もあった。おそらく敵機による機銃掃射の際の犠牲であると思う。
住吉分団の本部は、住吉国民学校(現住吉小)の講堂にあった。第2波の焼夷弾が落下したとき、分団員は身を捨てて消火にあたっていた。その瞬時、不幸にして嵯峨野団員が至近弾により殉死された。今も私は元住吉の講堂を見るとき、身を挺して消火にあたっていた人々の冥福を祈らずにはいられない。
|
上記の原平八さんと私との関係を、私事で恐縮ですが、ここに追記させていただきます。
私は同氏の生前、大変お世話になりました。30代のとき武蔵小杉駅前の東横病院に入院しました。主治医が家族に「今晩が峠。葬儀の準備を…」とまで宣告された大病を、原さんは心配され、私の病室に連日奥様や代理の方が見舞ってくださったり、同病院の明石院長(次ページ登場)に何やかやと無理なお願いしてくださったりとご配慮賜り、おかげで完治いたしました。
また、社会復帰後、とび職であった原さんに旧編集室だった建物の基礎工事をお願いしたり、本誌『とうよこ沿線』創刊に当たっても発起人としてご協力いただくなど公私にわたる掛け替えのない私の“恩人”でした。
原平八さんは当サイトのNO.181「名門旧家を訪ねて-1」にも登場。
|
|
|