■
|
創刊2号の「秋」以来お付合いの編集長に、圧倒されて満7年経ちました。そこで、不屈の精神力と豊富な思考力の編集長に敬意を表しまして、
「大男 総身の知恵をもてあまし」とは、如何でしょうか?
(大倉山のもの好き・山室まさ)
|
■
|
入会して初めて仕事をしました。普及協力店への配本です。私は頭より体です。次号の配本も頑張ります。ヨロシク! 追伸:「アルバム拝借」を1冊の本にしましょう。
(白楽・橋本 寛)
|
■
|
戦後間もない頃の、二子玉川園は遊園地が多摩川園の弟分であり、花火大会も丸子の花火に次ぐ規模だった。砧撮影所に近く、眺望絶佳の丘陵には五島慶太のお屋敷があり、第一勧銀のコートでテニスをやったのが懐かしい。
(反町・会社員・山下二三雄)
|
■
|
小さい頃、会社は人間を一つの歯車にすると思っていて、入社する時その歯車になろうと思い、今は全くその歯車になりきっている。感性も自由も忘れて自分は一体何をしているのだろうか。
(菊名・ちょっと疲れ気味・光吉 修)
|
■
|
近所のお友達の家に行ったら3冊の『とうよこ沿線』が棚の上に。第2の故郷、綱島の昔の古い写真の数々を見て、懐かしさのあまり胸がジーンと……。近くのスーパーで新刊を求め、編集室へお電話したのがご縁でした。
(綱島・主婦・長谷川栄子)
|
■
|
タウンガイドページ「どういうの〇〇」シリーズを私が担当するのも、代官山・菊名に続いて3回目。毎回新たな発見に知的好奇心は大満足。一方、誌面や取材時間の制約上、十分に書ききれないのが残念。
(日吉・紅玉りんごが好き・鈴木ゆうこ)
|
■
|
「人の世の流転を思うお彼岸に 荒れしままなる墓あまたあり」津田山霊園へ墓参の折の一首。
誰も来てくれない墓の主も、行けない人もさぞや辛かろう。
(武蔵小杉・自由人・天笠伝次郎)
|
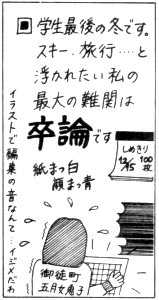
■(御徒町・五月女恵子) |
|
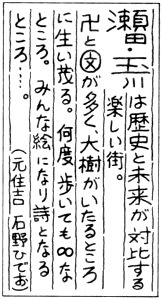
■(元住吉・石野ひでお) |
|
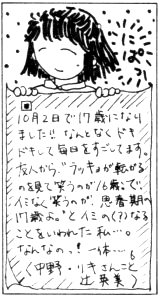
■(中野・辻英美) |
|
|
■
|
高校2年生の晩秋、はっきり言ってあせってます。女の子だしー、うちはお金もないので浪人・下宿はぜったいダメ。それになるべく国公立にしろって?ウチって実は4年制(?)なの、ご存知?
(野方・都立高校2年・高橋園子)
|
■
|
電車が上野毛駅を過ぎ、しばらくすると急に辺りがひらける。二子玉川園だ。多摩川の川面がキラキラ光り、街は緑がいっぱい。以前住んでた頃より一層洗練されて素敵な街になっていた。
(奥沢・旧二子玉ボーイ・小田房秀)
|
■
|
ふと思い出して、京都の中学卒業アルバムを開いてみた。木造老朽校舎、初老の恩師、お世話になった級友等々。懐かしさと想い出の多い学校。そこは転校して半年後、卒業式を迎えた学舎だった。
(日吉・プータロー・森 邦夫)
|
■
|
本誌を手にされた方は、ぜひ一度編集室に遊びに行くべきです。なぜなら東横線は、日本一料金の安い電車です? そして、すばらしいスタッフに会えるから。それに、この不思議な縁を大切にしてほしいから。
(等々力・野島幸雄)
|
■
|
4年制の専門学校に入学して2年目。他の専門学校生は早や来年卒業。で、私も就職活動の結果をよく聞かれる。私はまだまだ学生です。
追伸:皆さん、大晦日のウォークラリーにこぞって参加しましょう。
(溝の口・学生・橋口稔秀)
|
■
|
第39号9頁の五島慶太社長をうまく引き出した男、松村某は河野一三氏の誤り。広島県出身、夏も冬も和服を着流し朴歯(ほうば)の下駄でカランコロンと歩く男。
多摩川園の浅間神社に、昭和5年建設の愛桜之碑があり、裏面に多摩川両岸の当時の市町村長・助役が列挙されている。その中に東調布町長・天明啓三郎と並んで彼の名がある。忘れ得ぬ人である。中原町助役であった僕の名もある。
(武蔵小杉・小杉御殿町・小林英男)
|
■
|
現在の日本、とかく住みにくいといわれている。自分に関係ないことには全く無関心の人が多い。たとえ儲からなくても、いろいろのことにもっと関心をもつようにしたら、住みやすくなるのではないだろうか。
(菊名・本田芳治)
|
■
|
今年もまた落葉と共に秋が去り、冬将軍がやってきました。北風、木枯し、霜。そんな寒さの中で見る冬の夜空は、とても綺麗です。どうせオリオン座しか知らないんだろだって? 余計なお世話だ!!
(奥沢・トラ猫ミー君の主人・数野慶久)
|
■
|
女なんて嫌いだ! とフォークダンスの輪を抜けて、ひとり、「バラ園」の中のパーゴラの下で受験勉強をするイヤ味な生徒。赤い夕陽が校舎を染めて、畑田青年、高校3年生(都立玉川高校)晩秋のことでした。ホントは好きだったのにゴメンネ! ひばなちゃ~ん。
(緑が丘・漫画家・畑田国男)
|
■
|
遅れること20年、S58年の玉川高校卒業生。ロマンチックな話はないけれど、陽が暮れてボールが見えなくなるまで野球をしたり、授業をサボって煙草を吸ってた多摩川の土手が懐かしい。悪友と共に残した校舎の落書は今や壁画になっているらしい。
(祐天寺・その後はなぜか銀行員・一色隆徳)
|
■
|
あの俵 万智ちゃん風に私も短歌を作ってみました。(ご主人の海外勤務にともない旅立つピアノの先生を詠める歌)「アメリカに4年行ってくる」なんて電話一本で言ってしまっていいの。
(日吉・主婦・新井静江)
|
■
|
悠々と流れる多摩川、そびえ立つ巨木に囲まれた家並。二子玉川・上野毛特集で歩いたこの街の、お逢いした人たちがなんと素晴らしかったことか! 恵まれた風土が人の心を優しく育てるというのは、本当ですね。
(編集室・鈴木善子)
|
■
|
平日昼間の編集室に30代の奥さんが訪ねてきた。「25号綱島特集の本、まだありますか。あったら2冊譲ってください」。発行後1年も経ってからのことである。
「先日亡くなった父が、この本に載っているのです。父は病院のベッドの上で死の直前まで毎日毎日自分の載っているそのページをながめていました。ご近所からお借りした『とうよこ沿線』なのに、もうボロボロ……。1冊はそのお返しに、1冊は父の形見に保存して置きたいのです」。
その主婦は理由を一気に話し、25号36ページをめくってみせた。昭和33年8月早渕川決壊のときの写真である。これに長靴を履いた男性が心配そうに堤防の上を歩いている。これが亡き父上だというのだ。
私としては何気なく掲載した写真、これが個人にとってこれほど貴重なものであったとは……。恐らく撮影者も何気なく撮った1枚のスナップであったろう。それが歳月がたつと、貴重な記録や思い出となっている。
この事実を体験し、私は改めて〝記録としての写真″の重要性を知った。「アルバム拝借」のページも創刊以来40号の連載、7年半も経った。どの家庭にもアルバムの数冊はあるものだが、このページを飾るにふさわしい社会性のある写真、例えば風景や地域の行事、仕事中の情景などというのは、意外と少ない。旧家でも5軒訪ねて1枚の写真があればいいところだ。あるのは個人的な旅行・家族・友人知人のスナップばかり。
見慣れた光景でも年月が経つと思い出せないもの。写真があれば、すぐわかる。自宅前や通勤通学路をぜひ1枚カメラに収めておいて欲しい。
(本会代表・編集長・岩田忠利)
|