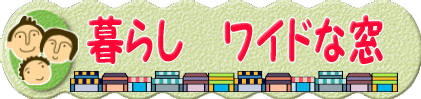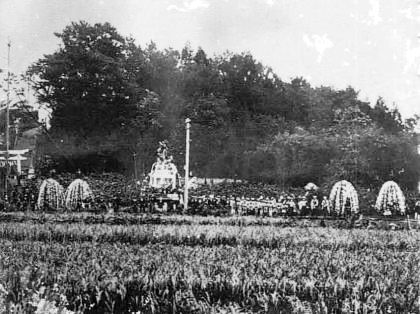|
|
都会生活に疲れ神経衰弱におかされていた佐藤春夫は、病をいやすため都会から離れ自然豊かな田舎暮らしを始めました。その田園生活を送る作者自身の心境、憂鬱で倦怠な日々の繰り返しの体験を赤裸々に綴った作品です。
舞台の「田園」は武蔵野台地の南端、現在の青葉区鉄町。その大正時代の情景がつぶさに描かれています。
|
作者の心情をつづったその抒情的文体と田園を写実的に描いた文体が日本人が共通に持っている古き良き時代へのノスタルジアと感情に対する共感を呼び、読者の心をとらえた作品と言われています。
|

佐藤春夫が大正5年から同9年まで住んでいた家
提供:坂田成一さん(鉄町)
|
|
|
鉄(くろがね)に来てからの春夫
春夫が鉄に来たときの持ち物といえば「ひとりの女と2匹の犬と1匹の猫と絵具と10冊の書物と2枚の着物」だけ。
その印象を春夫は主人公の目を通して『田園の憂鬱』の中でこう表現しています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
一筋の平坦な街道が東から西へ、また別の街道が北から南へ通じているあたりに、その道に沿うて一つの草深い農村があり、幾つかの卑下った草屋根があった。それはTとYとHとの大きな都市をすぐ6、7里の隣にして、3つの激しい旋風の境目にできた真空のように、世紀からは置きっ放しにされ、世界からは忘れられ、文明からは押し流されて、しょんぼりと置かれているのであった。
(中略)この丘つづき、空と、雑木原と、田と、畑と、雲雀との村は、実に小さな散文詩であった。
|
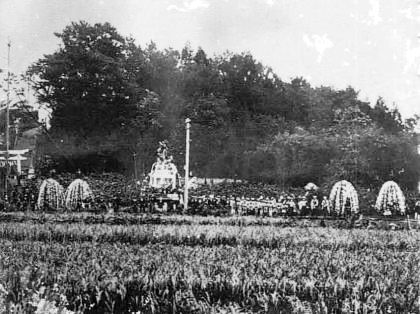
昭和3年、鉄神社祭礼の行列が神社の前に
提供:村田武さん(鉄町) |
|
|
|
|
小説の冒頭に彼が移り住む家(写真左)についても以下のように主人公に語らせています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「いい家のような予感がある」
「ええ、私もそう思うの」
その草屋根を見つめながら歩いた。この家ならば、いつか遠い以前にでも、夢にであるか、幻にであるか、それとも疾走する汽車の窓からででもあったか、何かで一度見たことがあるようにも彼は思った。その草屋根を焦点としての視野は、実際、どこででも見出されそうな、平凡な田舎の横顔であった。しかも、それが却って今の彼の心をひきつけた。
|
当時の佐藤春夫
|
|
|
|
|
佐藤春夫は明治25年、和歌山県新宮市、旧家の長男として生まれました。
県立の旧制新宮中学校に入学したとき、将来の志望を先生に聞かれ「文学者たらん」と即答したという。
文学書に没頭するあまり、3年生のとき落第を宣告されたことも。同校卒業の3月に上京し詩人・生田長江に師事し、9月には作家・永井荷風を慕って慶応大学文学部に入学しました。だが、学問のほうは怠り、在学5年間でたった1回進級しただけで大正3年に退学しています。小説の舞台、鉄を初めて訪れたのはその翌々年、大正5年4月のことでした。
|
|
|
その後の佐藤春夫
小説『田園の憂鬱』を大正8年に発表してからの春夫は、極度の神経衰弱になり大正9年鉄から帰京。
中国と台湾を旅した後、大正10年(1910)『殉情詩集』を発表、詩人としても認められます。そして小説のほかに戯曲も書き、さらに知的洞察力と鋭い分析力を持つ批評家として文芸評論、文学史論に多くの業績を残しました。
晩年は門弟3000人ともいわれ、昭和35年に文化勲章受章。ラジオ録音中に「私の幸福は……」と言い残して急逝したのでした。
春夫が鉄を初めて訪れてから100年が経ちました。その間、鉄町はすっかり様変わり。いま彼がこの地を再訪したらどんな視点でどのような筆致で鉄の今を描くでしょうか。
|