�@�@�n���̏㏸���傫�ȎЉ���ƂȂ��Ă���B�V���ɐ܂荞��ł���s���Y�̍L��������ƁA�����P���̑����z���Ă���̂��S�R�������Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@���̗����u�[���ȏ�Ƃ������Ă���ŋ߂̒n���㏸�́A�ȑO����n���̍������������ɂƂ��āA���̒n��ɂ��܂��ėR�X�������ɂȂ��Ă���Ƃ����悤�B
�@�����ō���́u�z�b�g���C���v�ł́A�{���́u�e���E���@�����W�v�ɂ��ȂP�[�X�Ƃ��ċe���w���ӂ����グ�A�n���㏸�̖��̍����ɐG��Ă݂����Ǝv���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�n���Ƃ͉����H
�@�Ƃ���ŁA�n���Ƃ����Ă��A���ʂ̏��i�Ƃ͈قȂ�A����������܂��͏㕨�����邩�ǂ����őS���قȂ邽�߁A���z���߂邱�Ƃ͓���B�܂��V�����ŕ�����̂ɂ��Ă��A�������i�A�H������������A�����Ƃ��Ăǂ��������Â炢��������B
�@�ł́A�����@�ւŒ�߂�������i�A�H�����Ƃ͈�̉��Ȃ̂��A������ƒ��ׂĂ݂邱�Ƃɂ����B
�@���������i�c�c�n������������Ӗ��ŁA���Ђ�����I�@�ւ���ʂ̓y�n����̎w�W�ƂȂ�悤�Ȑ���Ȓn�������I�ɒ����E�������ׂ����Ƃ����ӌ��f���āA���a45�N����͂��߂�ꂽ�B���ۂ̓y�n����̎w�W�Ƃ����������i�ł͂��邪�A���ۂɔ�������鉿�i�i�������i�j�̂W�����x�Ƃ����Ă���B���y�����S���B
�@���H�����c�c������ƂȂ��݂̔������������邪�A�ꎞ���A�V�h�^�J�m�t���[�c�p�[���[�O�̓y�n����ԍ����Ƃ����Ă����̂́A���͂��̘H�����̂��Ƃł���B
�@�@��v���H�ɖʂ����y�n�P�������[�g��������̕]���z�̂��ƂŁA�����ł②�^�ł̐Ŋz�̎Z���ɂȂ��Ă���B�i�ʐ}�Q�Ɓj�������i�̂ق�6���ɂ�����Ƃ���A������͍̂��Œ��ł���B
�@�@���ԂƂ��ċe���̏ꍇ
�@�@���I�@�ւ����\�����̉��i�ɂ��Ē��ׂĂ݂����A���̒����i�K�ł���傫�Ȏw�W�ƂȂ�̂��A��͂���ۂ̎���ł̉��i�ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@�ł́A���ۂǂ̂悤�Ȏ�����s��ꂽ�̂��A�e�����P�[�X�ɂƂ��Ă݂悤�B
|
|
�@�@
�@�����̕\�����Ă��������Ă�������Ƃ���A��͂肱���ɂ��Ă̎��Ⴊ�Ƃ�킯�������Ƃ�������B�����������E����В��ɂ��A�Ƃɂ����ŋ߂͕������o�Ȃ����������A
�@�u���o�Ƃ��āA�`�k��т��u�̂�����ō�N�̉č��܂Œ�100�����x�̂��̂��A10�����炢����125���~�A150���~�ƁA�㏸���͂��߁A���݂ł�200���~�Ƃ�250���~�Ƃ��Ȃ�����v
�@�Ƃ̂��Ƃł���B
|
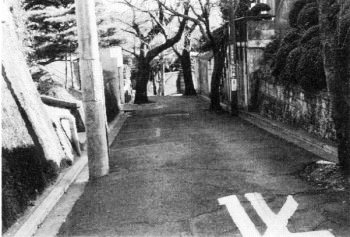
�e���w���ӂŐ���̏Z��X�A�т��u |
|
|
�@�т��u�Ƃ����A���̒n�悫���Ă̏Z��X�ł͂��邪�A����ɂ��Ă����N���炸�Ŕ{�ȏ�̒l�オ��Ƃ����̂́A������Ə펯�ł͍l���ɂ����B
�@��̂ǂ����Ĉُ�Ȃ܂ł̋}�����N���Ă���̂ł��낤���B
�@�@�T���V���C��250�����̎��v
���̌��������ǂ�ƁA�s�S�̃r�����v�̍��܂�ɍs�����B�O���n��Ƃ̓��{�i�o��{�Ђ̑����ړ]�Ȃǂɂ��s�S�̎������s���͐[���ł���B���y���̗\���ɂ��A����23����̐���2000�N�܂ł̃r�����v��5000�u�A�r�܂̃T���V���C��60�K���Ă̂��悻250�����ƂȂ��Ă���B
�@���ɊJ���̐i��ł���23����ň��K�͂̃r�������Ă邱�Ƃ́A���R����ȃr���̌��ݗp�n�̒�n�T���������N�����B�n�グ�����X��p�j���A�܂������x�O�������悤�Ȉړ]�⏞���������҂Ɏx������B
�@���̍��z�̕⏞����ɂ����l�������A���̑�֒n�Ƃ��ēs�����邢�͍ŋ߂ł͓c���s�s���ɂ܂ŏZ�܂������߂�悤�ɂȂ����B���ꂪ�n���㏸�̍��{�I�Ȍ����ƂȂ����B
�@�@�����A�c���s�s���̂��܃v���[�U�A�����ݖ�ł́A��300���~�Ƃ�500���~�Ƃ������A���ꂪ�������ƂȂ��ċe���w���ӂ̒n�����オ�����ƁA�O�q�̔��肳��͐������ꂽ�B
�@���v�Ƌ����Ƃ̃A���o�����X�����i�ɂ����Ē��������̂́A�ߑ�o�ϊw�̋��ȏ��̒ʂ�ł��낤�B
�@�������A�����ɐ������Ă����A����̌o�ς͐��藧���Ă���͂��ł���B���{���A���@�I�y�n�����}�����邽�߂̓y�n�Ő��̌��������l���Ă���悤�ł��邪�A���̖�����u���Ă����ƁA�P�ɐŋ��ʂ����łȂ��A�L���s�s�`���̊�b����邩���Ƃ��v����B
�@�����A�ŋߓc�����z�ł͒��ԏꂪ�����Ă���Ƃ����B�c�Ɨp���Y�Ƃ��ēy�n���^�p���邱�Ƃɂ���āA�ߐő�Ƃ��Ă��邩�炾�B
�@�@��������ǍD�ȏZ����������A�Ȃ��Ȃ����Ƃɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�܂��ɁA���A�n���̋}�㏸��s�s���Ƃ��Đ^���Ɏ~�߁A�l���Ă䂭�K�v������Ǝv����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ށE���F����T�v
�@�@ |