高校生に欠けているもの
先日、私は「現在の高校生に欠けているものは何か」というテーマで、高校の教員を志望している人たちの討論を傍聴する機会に恵まれた。
参加者のほとんどが、今の高校生に欠けている点として、「自主性に欠けている、根気がない、シラけていて何かに熱中することがない、我慢することができない」等々をあげていた。
彼らの発言に半ば首肯しながらも、私は次のような感慨を抱いたのである。
経済社会と精神的豊かさ
確かに彼らの言うとおりだろう。しかし、現在の高校生にそうした望ましくない傾向が見られるようになったのは、私自身を含めて、大人たちに責任があるのではなかろうか。
戦後、私たちは誰もが、飢えと貧しさとに喘いでいた。そこからの解放を求めて、世界一豊かな国、アメリカ合衆国を目標に、馬車馬のようにあくせくと働いた。その結果、見事に高度経済成長を成し遂げた。それによって、生活が豊かになるということは、大いに結構なことであるが、問題はそれ自体が一つの価値基準になってしまったということである。
本当は、人間らしく生きるための価値基準として、便利さや豊かさよりももっと大事なものがあるはずなのに……。それが全く忘れ去られてしまった。換言すれば、私たちの生活は物質的には大変豊かになったが、精神的には極めて貧しくなってしまったといえよう。
また、高度経済成長によって出現した高度工業社会では、「最大の効率と生産の原理」が指導原理となっている。それゆえに、効率を最大限にするために、社会全体があらゆる分野にわたって、組織化され、制度化され、管理されている。
|
|
したがって、もしも他律的に管理された生き方を選ぶならば、それは至極、楽にできる。が、そうでなく、自律的に生きようとするならば、すなわち、常に自分自身の判断に基づいて行動し、そのことに対して、すべて自分で責任をもつという生き方を選ぶならば、それは大変難しいことであり、かつ勇気を必要とするといえる。
このような社会の体質が、多分に依存的で無気力、かつ自制心と進歩性に欠ける高校生を大量に育てあげているのではなかろうか。
|
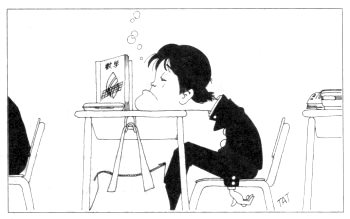
イラスト:石原辰也(横浜翠嵐高校2年 反町) |
|
|
大人として責任感を持たせよ
だからこそ、私たち大人は発想を大幅に切り換え、「贅沢は子どもの敵だ」を認識し、子どもたちを精神的に、強化するよう努力しなければならない。そのためにも、多少至らない面があろうとも、高校生たちを大人として扱う必要がある。
1年刻みのゼネレーション
もう一つ感じたのは、討論参加者はその多くが20代前半で、高校生とほぼ同世代と言えるのに、「今の高校生と接していると、我々とかなり違っていることを痛感する」などという発言がかなりあったことである。
私の考えでは、ゼネレーションというのは、ほぼ30年と思っていたのだが、いまの日本では、極論すれば、1年刻みになっているのではないかと空恐しさを感じたのである。
|