他人に無関心
隣は何をする人ぞ! 地元の人より地方から上京して住みついている住民の方が多くなった東京では、隣近所の連帯もなく、他人に無関心は普通のことになっている。過干渉の煩わしさを考えると、この方がずっと気楽で住みよいということも、ある一面では事実であろうし、そう思っている人も多いであろう。しかし、隣の人が死のうが、近所の子供が非行に走ろうが、情も何もない東京砂漠となっても本当にいいものだろうか?
住民による住民のための住区
15年前、目黒区では、東京23区で初めて「明るい住みよい人間の街目黒」をスローガンに街づくりの長期計画が立てられた。通学区毎に住区住民会議をつくり、住んでいる人は誰でも参加でき、いわゆる住民の手による住民のための住区づくりを目指している。住みよい環境施設づくり、交通防犯対策、青少年の健全なる育成、住民のよりよい人間関係等を目標に、住民だけではなく、区内の企業、学校等も参加している。
その一環として、住区関係者が一体となり、秋には大運動会を開催している。老若男女合わせて1400~1500人の参加があり、町会対抗リレー・綱引きなどの白熱ぶりは、子供以上であった。また、私の担当している文教青少年部会では、毎年夏休みに小学生を対象とした和田村キャンプ、秋に手づくり子供会、親子料理教室を行なっている。
どれも学校教育では体験できない貴重なことばかりだ。これらはすべて、地域のおじさん、おばさんたちの協力でできている。
|
|
|
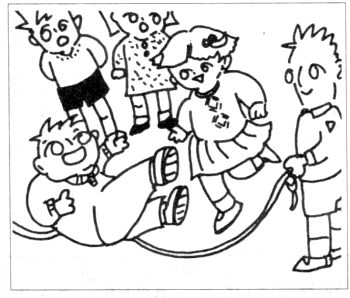
イラスト:倉田和枝(戸越公園) |
|
|
核家族化で、異世代との交流が減少し、文明社会の反映で、手先が不器用になっているパソコン世代に、こうした住区活動を続けることが少しでも子供達に人とのかかわりの大切さ、思いやり、責任感を教えることになるのではと思う。青少年が健やかに育つには地域社会の役割が大きく、家庭や学校だけではなく、住区の連携プレーが力を発揮するのである。
奉仕する心のゆとり
確かに、住区活動の意義、必要性は認められているが、区内約1万世帯にどれだけ浸透し、関心を持たれているかは心もとない。町会・商店街組織と併設された形での住区住民会議の共存運営の難しさ、地域の奉仕活動に対する認識の低さ、事実上の運営者は年配者のごく一握りと問題は多い。設立3年目にして、軌道に乗りかけている住区活動の、今後の課題である。
自分勝手な生活をし、地域の人とのかかわりを持たなくても暮らしてゆけるけれど、いい意味での干渉のしあい、助けあいや人情が、自分の住む街への愛着、連帯感へ、とつながってゆくのてはないだろうか。
物が豊かになり、生活水準が上昇してきた現在、これからは、他人のために奉仕する心のゆとりが問われるのではないか。
|