پ@پ@پ@پ@گ¢ٹE‚ج’[پA‰“‚¢‚؟‚ء‚؟‚ل‚¢چ‘پA“ْ–{
پ@ژ„‚ھ51”N‘OپA“ْ–{‚ض—ˆ‚½ژپAƒˆپ[ƒچƒbƒpگl‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA“ْ–{‚جچ‘‚ح‚ـ‚ء‚½‚کb‚جƒ^ƒl‚ة‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBˆê”ت‚جگl‚حپA“ْ–{‚ھ‚ا‚±‚©‰“‚¢پuگ¢ٹE‚ج’[پAگ¢ٹE‚جڈI‚ي‚èپA‚؟‚ء‚؟‚ل‚¢چ‘‚ةˆل‚¢‚ب‚¢پv‚ئژv‚ء‚½پB’†چ‘‚ح‘ه‚«‚بچ‘‚إپA‚ف‚ٌ‚ب‚ھ‚ي‚©‚ء‚½پB
پ@‚¾‚©‚çپA“¹‚إ“ْ–{گl‚ھ•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‚¤‚µ‚ë‚إƒ„ƒ“ƒ`ƒƒ‚ب’j‚جژq‚½‚؟‚حپA‚©‚ç‚©‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚·پBپu‚ظ‚çپAŒ©‚ؤ‚²——پAƒ`ƒƒƒCƒjپ[ƒY‚وپv‚ئ‹©‚ر‚ب‚ھ‚ç‚ح‚₵‚½‚ؤپA‚¢‚½‚¸‚ç‚ةگخ‚ً“ٹ‚°‚邱‚ئ‚àپA‚½‚ر‚½‚ر‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
پ@‘وˆêژںگ¢ٹEگي‘ˆ‚ج‚ ‚ئ‚àپA‚©‚ê‚ç‚ح‡€ˆنŒث‚ج’†‚جƒJƒGƒ‹‡پ‚ف‚½‚¢‚ةپAگ¢‚ج’†‚ج‚±‚ئ‚ً’m‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB—·‹q‹@‚ج‚ب‚¢ژ‘مپA“ْ–{‚ًگ¢ٹE’nگ}‚إ‚ب‚ھ‚ك‚é‚ئپA’†چ‘‚ج‚à‚ء‚ئ“ŒپA‚¢‚؟‚خ‚ٌ‘¬‚¢‘D‚إ‚à‚TڈTٹش‚à‚©‚©‚ء‚ؤپA‚و‚¤‚â‚’…‚چ‘‚إ‚µ‚½پB
|
|
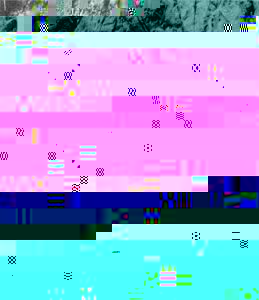
22چخ‚ج‰ؤپA—ˆ“ْ“–ژ‚جƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[
|
|
پ@‚ ‚جچ ‚جƒˆˆêƒچƒbƒpگl‚ح‚ف‚بپA“ْ–{گl‚ج‚±‚ئ‚ًپu”畆‚ح‰©گFپBٹل‚ح•ï’ڑ‚إگط‚ç‚ꂽ‚و‚¤‚ةچׂپAŒ¾—t‚ح’¼گع‚ة‚حکb‚³‚ب‚¢چ‘–¯پv‚ئ‰\‚µ‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB
پ@‚»‚ج‚و‚¤‚ب“ْ–{گlٹد‚إ‚µ‚½‚©‚çپAƒڈƒ^ƒV‚à‚à‚؟‚ë‚ٌپA“ْ–{گl‚ً‚½‚¢‚ض‚ٌ•|‚¢گlٹش‚إ‚ ‚é‚ئ‹°‚ê‚ـ‚µ‚½پBƒڈƒ^ƒV‚ج—F‚¾‚؟‚ئ‚حˆل‚ء‚ؤپAƒڈƒ^ƒV‚حƒ‰ƒtƒJƒfƒBƒIƒnپ[ƒ“پiڈ¬گٍ”ھ‰_پj‚ج–{‚ًˆêچû‚à“ا‚ٌ‚¾‚±‚ئ‚ھ‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚©‚çپA‚ب‚¨‚³‚ç‚ج‚±‚ئپcپB
پ@‚»‚µ‚ؤ“ْ–{‚ة—ˆ‚½‚ئ‚«پAژq‹ں‚½‚؟‚ھ‚¤‚µ‚ë‚ة‘–‚ء‚ؤ—ˆ‚ؤپAپu‚ظپ[پAٹOگl‚¾پAٹOگl‚¾پIپv‚ئ‹©‚ٌ‚إپAڈخ‚ء‚½پB‹ك‚‚ةٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚½“ْ–{‚جژq‹ں‚½‚؟‚حپAƒhƒCƒc‚ج’j‚جژq‚½‚؟‚ف‚½‚¢‚ةگخ‚ً“ٹ‚°‚é‚و‚¤‚بگ^ژ—‚¾‚¯‚حپAˆê“x‚à‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB
پ@‚µ‚©‚µچ،‚ح•\‘è‚ج‚و‚¤‚بƒ|ƒXƒ^پ[‚ًƒچƒ“ƒhƒ“پAƒpƒٹپAƒچپ[ƒ}‚ب‚ا‚ا‚±‚إ‚àŒ©‚ç‚ê‚ـ‚·پB‚ف‚ٌ‚بپA“ْ–{‚ج‚±‚ئ‚ً‚و‚’m‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·ƒlپB
|
|
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چDٹï‚ج“I‚جƒڈƒ^ƒV‚½‚؟
پ@ƒڈƒ^ƒV‚ھ“ْ–{‚ة‚«‚½”NپA1929”NپA‚»‚µ‚ؤ—‚”N‚àپAٹOچ‘گl‚ح‚ـ‚¾“ْ–{‚ة‚ح–w‚ا‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚¾‚©‚çپAƒڈƒ^ƒV‚ھگ_Œث‚ج“¹‚ً•à‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ئپA‘هگl‚ج“ْ–{گl‚ھ—§‚؟ژ~‚ـ‚ء‚ؤپAƒڈƒ^ƒV‚ة‚±‚¤•·‚‚ج‚إ‚·پB
پ@پu‚ ‚ب‚½‚جگآ‚¢ٹل‚إ‚àژ„‚ج’ƒگF‚جٹل‚ئ“¯‚¶‚ه‚¤‚ةپA‚ب‚ٌ‚إ‚àŒ©‚¦‚é‚ج‚إ‚·‚©پHپvپA‚ـ‚½‚حپA
پ@پu‚ ‚ب‚½‚جچ‘‚ة‚حپAژ„‚جچ‘‚ئ“¯‚¶‡€‹Dژش‡پ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚©پHپv
پ@’¬‚ح‚¸‚êپA‹™ژt’¬‚ب‚ا‚ًƒڈƒ^ƒV‚ھ’ت‚é‚ئ‚«پA‘هگl‚àژq‚ا‚à‚à‹ء‚¢‚ؤٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚éپB‚â‚ھ‚ؤپA‘؛‚ج‘S•”‚جگl‚½‚؟‚ھ‘–‚ء‚ؤٹٌ‚ء‚ؤ—ˆ‚éپB‚ـ‚·‚ـ‚·‹ك‚‚ةٹٌ‚ء‚ؤ‚‚éپB‘هگl‚إ‚³‚¦‚àژè‚ً‚ج‚خ‚µ‚ؤپAƒڈƒ^ƒV‚ئ—F‚¾‚؟‚جکr‚ً‹‚ژw‚إ‚ب‚إ‚é‚ج‚إ‚·پB
پ@”畆‚ج”’‚³‚ھ•sژv‹c‚ب‚ج‚©پA‰½‚©“h‚ء‚ؤ‚ ‚é‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پBژ©•ھ‚جژwگو‚إƒڈƒ^ƒV‚½‚؟‚ج”§‚ًگG‚ء‚ؤ‚ف‚ؤ‚حپA
پ@پu”’‚¢‚à‚ٌپA•t‚¢‚ؤ‚¢‚éپHپ@•t‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚¢پHپv
پ@‚ئ‘ه‘›‚¬‚µ‚ب‚ھ‚ç’²‚ׂé‚ج‚إ‚·ƒlپB
پ@ƒڈƒ^ƒV‚ئƒڈƒ^ƒV‚ج—F‚¾‚؟‚à‚ـ‚¾“ٌڈ\‚»‚±‚»‚±‚إ‚µ‚½‚©‚çپA‘ه•د‚«‚ê‚¢‚ب‹à”¯‚¾‚ء‚½پB
|
|
پ@‚ـ‚½“¯‚¶‚و‚¤‚ة”¯‚ج–ر‚ً‰“—¶‚ب‚‚ب‚ٌ‚ׂٌ‚àژw‚إ‚³‚ي‚ء‚½‚èپA‹‚‚ب‚إ‚½‚èپAˆّ‚ء’£‚ء‚½‚èپcپcپB‚»‚µ‚ؤژ©•ھ‚½‚؟‚جژwگو‚ً‚¶ˆê‚ء‚ئ’²‚ׂé‚ج‚إ‚·ƒlپB‚»‚µ‚ؤ‚ف‚ٌ‚ب‚ھ‘هگ؛‚إپA
پ@پu‚ـپ[پA‚ـپ[پA“ٌگl‚ا‚ء‚؟‚àگF‚ھ—ژ‚؟‚ب‚¢‚وƒbپvپB
پ@ƒڈƒ^ƒV‚½‚؟‚جٹç‚حگش‚‚ب‚èپAگg‘ج‘S‘ج‚ھ”M‚‚ب‚èپA‚»‚µ‚ؤ‚±‚ٌ‚ب‚ةگس‚ك‚ç‚ê‚é‚ئپA“¦‚°ڈo‚µ‚½‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚¨• ‚ھ‹َ‚¢‚½‚ج‚إپA‰½‚©”ƒ‚¢‚ةچs‚±‚¤‚ئژv‚ء‚ؤ‚àپAگl‚ر‚ئ‚ح‚ا‚±‚ـ‚إ‚à•t‚¢‚ؤ—ˆ‚é‚ج‚إ‚·پB
پ@‚±‚جژ‚ج“ْ–{گl‚جژ·X‚بچDٹïگS‚ئŒQڈWگS—‚ة‚حپA‚ظ‚ئ‚ظ‚ئچ¢‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚µ‚½پB
|
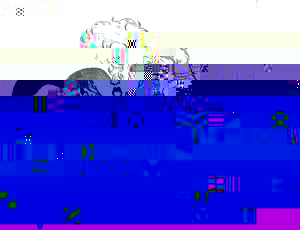
”§‚ًگG‚ء‚½‚èپA”¯‚ًˆّ‚ء’£‚ء‚½‚èپc
ƒCƒ‰ƒXƒgپE”آژR”üژ}ژq |
|
|
|
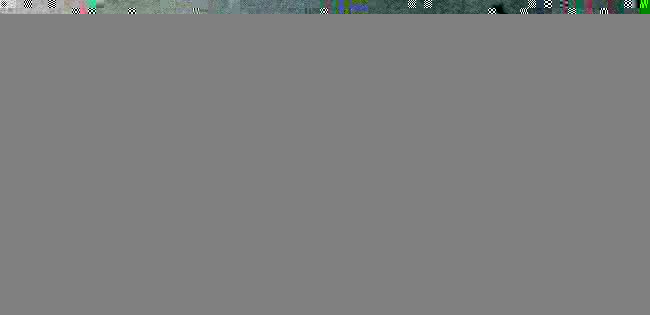
‚ا‚±‚ـ‚إ‚à•t‚¢‚ؤ—ˆ‚éژq‹ں‚½‚؟‚ةƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌ‚ھƒJƒپƒ‰‚ًŒü‚¯‚é‚ئپA–I‚ج‘ƒ‚ً–_‚إ“ث‚ء‚آ‚¢‚½‚و‚¤‚ة‚ ‚ي‚ؤ‚ؤ“¦‚°‚éژq‹ں‚½‚؟پcپcپBچ°‚ً’D‚¢ژو‚ç‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤–ہگM‚ھ‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·ƒl
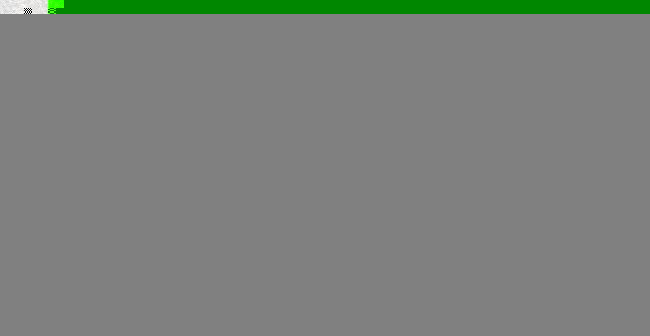
پu‚±‚ê‚حپAŒiگF‚ً—ا‚Œ©‚é“ء•ت‚بƒ‰ƒ“ƒv‚إ‚·پv‚ئƒڈƒ^ƒV‚ھگà–¾‚·‚é‚ئپA“¦‚°ڈo‚µ‚½ژq‹ں‚½‚؟‚ھˆہگS‚µ‚ؤپA‚ـ‚½ڈW‚ـ‚ء‚ؤ—ˆ‚ـ‚µ‚½
|
|
|
|
|
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ْ–{گl‚ئƒAƒCƒkگl‚جˆل‚¢
پ@پ@1932”N(ڈ؛کa7”N)پA–kٹC“¹‚جƒAƒCƒkگl‚ج‘؛‚ةچs‚ء‚½‚ئ‚«پA‚»‚ج‚و‚¤‚ب‘جŒ±‚حˆê“x‚à‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پBƒAƒCƒkگl‚حپA‘ه—¤‚جگl‚½‚؟‚ةژ—‚ؤ‚¢‚é‚ئٹ´‚¶‚ـ‚µ‚½پB
پ@کb‚·‚ئ‚«‚àپA‚©‚ê‚ç‚حƒڈƒ^ƒV‚ة’¼گعکb‚µ‚©‚¯‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚ـ‚½ژ©•ھ‚جٹ´ڈî‚ً‰B‚³‚ب‚¢گl‚½‚؟‚¾‚ء‚½پB‚QپA‚R‰ٌƒAƒCƒkگl‚ة‰ï‚ء‚½‚¾‚¯‚إ‚µ‚½‚ھپAچإŒم‚ج•ت‚ê‚ج‚ئ‚«‚ة‚حپAƒڈƒ^ƒV‚جŒ¨‚جڈم‚إ‘ه—±‚ج—ـ‚ً‚±‚ع‚µ‰“—¶‚ب‚‹ƒ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚½پB
پ@ƒAƒCƒkگl‚ھ“ْ–{گl‚ئˆل‚¤‚ج‚حپA‚»‚ج“_‚إ‚·پBƒAƒCƒk•”—ژ‚©‚ç•”—ژ‚ض”n‚ةڈو‚ء‚½ˆêگl—·‚إ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µگش–ت‚·‚邱‚ئ‚حˆê“x‚à‚ب‚پA”ٌڈي‚ة‹Cٹy‚ب—·‚إ‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ƒCƒU‚ئ‚¢‚¤ژپA—ٹ‚è‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢“ْ–{گl
پ@ژهگlƒ^ƒJƒnƒVƒPƒ“ƒW‚حپA‚ئ‚ؤ‚àگس”Cٹ´‚ج‚ ‚éگl‚إ‚µ‚½پB‚إ‚àپAگي‘ˆ‚ج‚·‚®‚ ‚ئ•a‹C‚إ–S‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBƒڈƒ^ƒVپA‰½”N‚à‰½”N‚àٹإ•a‚µ‚½‚¯‚ê‚ا‚àپcپcپB
پ@‚»‚جچ پA–؛‚àƒڈƒ^ƒV‚àگ¶‚«‚邱‚ئ‚ھ‚ئ‚ء‚ؤ‚à‚ق‚¸‚©‚µ‚©‚ء‚½پBگH‚ו¨‚ح‚ب‚¢‚µپA–ٍ‚ح‚ب‚¢‚µپAˆمژز‚حŒؤ‚ٌ‚إ‚à—ˆ‚ب‚¢‚µپcپdپEپBڈ•‚¯‚ؤ‚‚ê‚éگlپA‚¾‚êپ[‚à‚¢‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پB“ْ–{گl‚حپAˆ«‚¢•a‹C‚إ‚à‚·‚é‚ئپA’‡—ا‚‚µ‚ؤ‚¢‚½‘هٹw‚جگوگ¶‚½‚؟‚ـ‚إ‚à‚ھپdپcپEپBŒ‹‹اپAژهگl‚ح‹¹‚ًˆ«‚‚µ‚ؤ44چخ‚إژ€‚ة‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جژپAژ„‚½‚؟‚Rگl‚حپA‚àڈ‚µ‚إˆêڈڈ‚ةژ€‚ت‚ئ‚±‚낾‚ء‚½‚إ‚·ƒˆپB
پ@‚¯‚ê‚ا‚àچK‚¢‚ة‚Rگl‚ج‹³‚¦ژq‚جٹwگ¶‚³‚ٌپAٹطچ‘گlپA’†چ‘گlپA“ْ–{گl‚ھ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پB‚»‚ج‚¤‚؟“ْ–{گl‚جٹwگ¶‚حڈ•‚¯‚éˆسژu‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àپA‘وˆê‚جƒXƒeƒbƒv‚ًچs“®‚·‚é—E‹C‚ب‚©‚ء‚½‚جƒlپB
پ@ٹطچ‘گl‚ئ’†چ‘گl‚جٹwگ¶‚³‚ٌ‚ھ–؛‚ئƒڈƒ^ƒV‚ً‹~‚ء‚ؤ‚‚ꂽ‚جƒˆپB‚Qگl‚جژل‚¢ٹwگ¶‚³‚ٌ‚ھٹOچ‘گl‚إ‚ ‚éƒڈƒ^ƒV‚ئ–؛‚ًٹإ•a‚µ‚½‚肵‚ؤ–ت“|‚ف‚ؤ‚‚ꂽ‚جپB‚»‚ج“ٌگl‚جٹwگ¶‚³‚ٌپAگeگت‚جگl‚½‚؟‚©‚炳‚ٌ‚´‚ٌˆ«ŒûŒ¾‚ي‚ꂽ‚ج‚ةپA‚»‚ê‚ًچ\‚ي‚¸پA‚P”Nٹش‚à–ت“|‚ف‚ؤ‚‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج“ٌگl‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚çپAƒڈƒ^ƒV‚ئ–؛‚حپA‚¢‚ـ‚±‚جگ¢‚ة‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚إ‚·ƒˆپB
پ@‚±‚ج‚ئ‚«ƒڈƒ^ƒVپA“ٌ‚آ‚ج‚±‚ئ‚ً•×‹‚µ‚ـ‚µ‚½ƒlپBˆê‚آ‚حپAپuگlٹش‚ء‚ؤپA‘¼گl‚ج”ü‚µ‚¢‘Pˆس‚ًپA‰ک‚ˆ«‚‰ًژك‚·‚é‚à‚ج‚¾پv‚ء‚ؤپcپdپB‚à‚¤ˆê‚آ‚حپAپu“ْ–{گl‚ء‚ؤپA‚س‚¾‚ٌ‚ح‚ئ‚ؤ‚àگS‚ًچ‡‚ي‚¹‚ؤڈ•‚¯چ‡‚¢‚ـ‚·پB‚¾‚¯‚اپAƒCƒUچذ‚¢‚ج‚ئ‚«‚ة‚ب‚é‚ئپAژ©•ھ‚ھ–{“–‚ة‹êکJ‚µ‚ؤ‘¼گl‚ًڈ•‚¯‚ب‚¢‚±‚ئپvپA‚»‚ê’m‚è‚ـ‚µ‚½ƒlپB
پ@پ@’†چ‘گl‚ب‚ا‘ه—¤‚جگl‚½‚؟پA‚»‚ج“_پAˆل‚¢‚ـ‚·ƒlپBپuژ©•ھ‚حژ€‚ٌ‚إ‚àچ\‚ي‚ب‚¢پv‚ئچإŒم‚ـ‚إڈ•‚¯‚ـ‚·ƒlپB
پ@“ْ–{گl‚حپAژ©•ھ‚ج‰ئ‚إ‚àٹë‚‚ب‚ê‚خپA‚½‚¾ژ©•ھ‚ج‚±‚ئ‚¾‚¯‚ًچl‚¦‚ـ‚·ƒlپB‚±‚ꂶ‚لپA‘ه‚«‚ب’nگk‚إ‚à—ˆ‚½‚ئ‚«پA‚ا‚¤‚ب‚é‚ج‚©ƒlپ[پB
|
پ@ پ@پ@پ@پ@چف“ْ51”NپAƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌ‚ج‘«گص
پ@ƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌ‚ج‰ïکb‚جˆü‚ة‰B‚ꂽگlٹشگ«‚ئژv‘zپA‚»‚µ‚ؤƒPƒ^‚ح‚¸‚ê‚جچs“®—حپA‚»‚جˆê’[‚ًژ¦‚·چف“ْ51”N‚ج‘«گص‚ً‚¢‚‚آ‚©ڈE‚ء‚ؤڈذ‰î‚µ‚ؤ‚ف‚و‚¤پB
پ@“ْ–{‚جƒXƒLپ[‚جƒپƒbƒJپE‘ ‰¤پB‰”N‚ج‘هƒXƒ^پ[Œ´گكژqپBگVٹƒŒ§•ZŒخپi‚ذ‚ه‚¤‚±پj‚ج”’’¹پB‚¢‚¸‚ê‚à“ْ–{‘S“y‚ةپA‚»‚µ‚ؤگ¢ٹEٹe’n‚ة‚»‚ج‘¶چف‚ح’m‚ê“n‚ء‚ؤ‚¢‚éپB”ü‚ج‹ة’v‚ئ‚¢‚ي‚ê‚é‚ظ‚ا”ü‚µ‚¢پB‚»‚ج”wŒم‚ة‚ح‚·‚ׂؤ‚±‚جƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌ‚جˆ¤‚ئ‚»‚جٹˆ“®‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
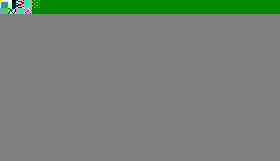
ژ÷•X‚ج‘ ‰¤
|
|

گâگ¢‚ج”üڈ—‚ئŒ¾‚ي‚ꂽŒ´گكژq |
|
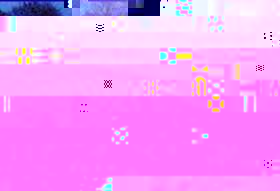
”’’¹‚جŒخپA•ZŒخ
|
|
پ@”قڈ—‚حڈ؛کa‚T”N21چخ‚ج‚ئ‚«—ˆ“ْپB–؛گ·‚è‚ج23چخ‚إƒAƒCƒk‚ج“`گà‚ً’²چ¸‚·‚邽‚ك–¢ٹJ‚ج’nپA–kٹC“¹‚ة“n‚éپB‚»‚ج‹AکHپA‚ج‚؟‚ة•v‚ئ‚ب‚é‹“s‘هٹw‹³ژِپEچ‚“ڈŒ’ژ،‹³ژِ‚ةگآ”ںکA—چ‘Dڈم‚إڈo‰ï‚¢پA—ِˆ¤پA‚ـ‚¾ٹOچ‘گl‚جژp‚ھ’؟‚µ‚¢ژ‘مپA“ٌگl‚حچ‘چغŒ‹چ¥پB
پ@‚¢‚ـ‚ح–S‚«“¯‹³ژِ‚ح“ْ–{ژRٹxٹE‚جŒ ˆذژز‚إ“–ژ‚©‚çƒXƒLپ[‚âژRٹx‚ةٹض‚·‚鑽‚‚ج’کڈ‘‚ھ‚ ‚éپB‚ـ‚½ژRٹxƒXƒLپ[‚ج–¼گl‚إپAچ‚ڈ¼‹{“a‰؛‚ئژOٹ}‹{“a‰؛‚ةƒXƒLپ[‚ً‹³‚¦‚½گl‚إ‚à‚ ‚éپB
پ@ڈ؛کa11”NپAگ¢ٹE“IژRٹx‰f‰و‚جگ»چىژزƒAپ[ƒmƒ‹ƒhپEƒtƒ@ƒ“ƒN”ژژm‚ھ—ˆ“ْپB‚ـ‚¾“Œ–k‚جٹ¦‘؛‚¾‚ء‚½‘ ‰¤‚ً•‘‘ن‚ةڈ——DŒ´گكژqژه‰‰‚جƒ‰ƒuƒچƒ}ƒ“ƒX‰f‰و‚ًژB‰eپA‚±‚ê‚ھگ¢ٹE‚ةچL‚ڈذ‰î‚³‚ꂽپB‚±‚ê‚ً‚«‚ء‚©‚¯‚ة‡€ژ÷•X‚ج‘ ‰¤‡پ‚ئ‡€”ü–e‚جƒZƒcƒRپEƒnƒ‰‡پ‚حگ¢ٹE‚ة’m‚ê“n‚ء‚½پB‚»‚جژ‚جƒچپ[ƒ[‚³‚ٌ‚حژR’‡ٹش‚¾‚ء‚½ƒtƒ@ƒ“ƒN”ژژm‚ج”éڈ‘‚ئ‚µ‚ؤپA“ْ–{ژ–ڈî‚ًگ¢ٹE‚ةڈذ‰î‚·‚é‚ج‚ةˆêگl‚إ‰½–ً‚à‰‰‚¶‚½پB
پ@‚¢‚ـ‚â•ZŒخ‚ح‡€”’’¹‚جŒخ‡پ‚ئ‚µ‚ؤ—L–¼‚¾‚ھپA‚±‚ê‚àژہ‚حپAƒچپ[ƒ[‚³‚ٌ‚ھڈ؛کa45”N‚XŒژگVٹƒŒ§’mژ–ˆ¶‚ؤ‚ئ’nŒ³ژتژہ‰ئˆ¶‚ؤ‚ةژèژ†‚ًڈo‚µپA”’’¹‚â–ى’¹‚ج•غŒىپA•ZŒخ‚جژ©‘Rٹآ‹«•غŒى‚ً‹‚‘i‚¦‚½‚ج‚ھ‚«‚ء‚©‚¯پB‚ف‚¸‚©‚çپu”’’¹”ة’jپv‚ئ‚¢‚¤گU‘ضŒûچہ‚ً—X•ض‹ا‚ةگف‚¯•ه‹à‰^“®‚ة–z‘–پA‘Sچ‘‹K–ح‚جپu•ZŒخ‚ج”’’¹‚ًژç‚é‰ïپv‚ً‘gگD‚µ‚½پBˆê•ûپA”قڈ—‚حٹCٹO‚ة‚à•ZŒخ‚ج”’’¹‚ًڈذ‰îپA‚»‚ê‚ھ”½‹؟‚ًŒؤ‚رپAƒCƒMƒٹƒX‚جپuچ‘چغ”’’¹‰ï‹cپv‚ةڈµ‘ز‚³‚ꂽ‚±‚ئ‚àپB‚»‚ج‚و‚¤‚ةپA‚ـ‚³‚ة“ْ–{‚ج•ZŒخ‚ًگ¢ٹE‚ة‚ح‚خ‚½‚©‚¹‚½‚ج‚àپAƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌ‚¾‚ء‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@گيŒم‚ج‹ê“ï‚جژ‘م‚ة‹~‚ء‚ؤ‚‚ꂽٹwگ¶‚ج‰¶‚ً‹¹‚ة
پ@ڈIگيŒم‚جڈ؛کa21”N•é‚êپA‚²ژهگlچ‚‹´‹³ژِ‚ح–S‚‚ب‚ء‚½پBگيŒمٹش‚à‚ب‚¢“®—گ‚ج‚ب‚©پA‹Q‚¦‚ئ•خŒ©پAˆظچ‘‚إڈ—‚جچ×کr‚إگ¶‚«‚éƒLƒr‚µ‚³‚ئ‚ي‚ر‚µ‚³پA‚»‚ٌ‚بڈ‚آ‚¢‚½گS‚ً–ü‚µ‹~‚ء‚ؤ‚‚ꂽ‚ج‚حپA’†چ‘‚ئٹطچ‘‚ج‘ه—¤‚جٹwگ¶‚¾‚ء‚½پB
پ@‚»‚ج‰¶‚ھ–Y‚ê‚ç‚ꂸڈ؛کa35”N‚TŒژپAƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌ‚ھ‘nژnژز‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚ح‚¶‚ك‚½‰^“®‚ةپuƒ‚ƒAپEƒWƒ‡ƒCپEƒZƒ“ƒ^پ[پvپiگS‚جگشڈ\ژڑ‰ïپj‚ھ‚ ‚éپB‚±‚ج‰^“®‚حپuگ¶‚«‚邱‚ئ‚حپA•ھ‚©‚؟چ‡‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپ\پ\پv‚ئ‚¢‚¤گ¸گ_‚ًچL‚گ¢ٹE‚ة’m‚点پAگlپX‚ھ—‰ً‚ًگ[‚كچ‡‚¤’†‚إ’²کa‚ج‚ئ‚ꂽ•½کa‚بگ¢ٹE‚ًŒڑگف‚µ‚و‚¤‚ئ‚¢‚¤‚à‚جپB
پ@پ@ƒCƒ“ƒh‚ةگe‘P—¯ٹwگ¶‚ً‘—‚èچ‚ٌ‚¾‚èپA“ْ–{ٹe’n‚ج•—Œi‚╶‰»چà‚ب‚ا‚جƒXƒ‰ƒCƒh‚ًژ‚ء‚ؤ359“ْٹش‚جگ¢ٹEˆêژüگe‘P—·چs‚ً‚â‚ء‚½‚è‚à‚µ‚½پB—·چs’†پA“ْ–{‚جگـ‚èژ†‚â“`گà‚ًگ¢ٹE‚جگlپX‚ة‹³‚¦‚ؤ‰ٌ‚èپAگ¢ٹE‚جŒ©’m‚ç‚ت—Fگl‚½‚؟‚©‚瑽‚‚جٹ´ژس‚جŒ¾—t‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½پB”قڈ—‚حپA‚ ‚جگيŒم‚ج‹ê“ï‚جژ‘م‚ً‹¹‚ةپA‡€گي‘ˆ‚ج‚ب‚¢گ¢ٹEپA’²کa‚ج‚ئ‚ꂽگ¢ٹE‚ج‘n‘¢پچ‚ً‚ك‚´‚µ‚ؤ‚±‚ج‰^“®‚ة”Mˆس‚ً”R‚₵‚ؤ‚¢‚éپB
|
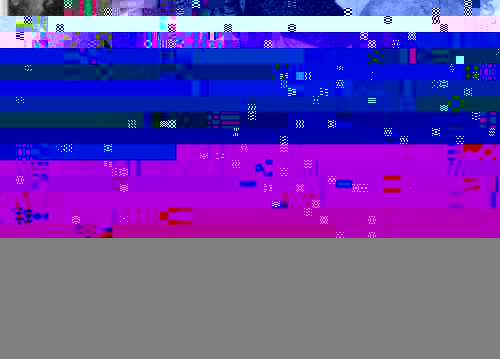
1960”Nپiڈ؛کa36”Nپj3Œژ26“ْپA“ْ–{‚جژq‹ں‘م•\‚ًکA‚ê‚ؤƒCƒ“ƒhپEƒlپ[ƒ‹ژٌ‘ٹ(‰Eپj‚ً–K–₵‚½ƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌپiچ¶پj
پ@پ@ژتگ^پFƒCƒ“ƒhگ•{’ٌ‹ں
|
|
|
پ@51”N‘OپA“ْ–{‚ج“y‚ً“¥‚ٌ‚¾ƒچپ[ƒ[پEƒŒƒbƒTپ[‚³‚ٌپBˆب—ˆ“ْ–{گlˆبڈم‚ة“ْ–{‚ًˆ¤‚µپAچ‘‹«‚ئ–¯‘°‚ً‰z‚¦‚½گ¢ٹE‚جگl‚½‚؟‚جگS‚جŒً—¬‚ًگ[‚ك‚邱‚ئ‚ًگ¶ٹU‚جٹى‚ر‚ئ‚µ‚ؤپA72چخ‚ج‚«‚ه‚¤(پڑ‚±‚ج‹Lژ–ŒfچعژپA1980”N)‚à“ْ–{ڈذ‰î‚جƒ^ƒCƒvƒ‰ƒCƒ^پ[‚ج‰¹‚ح–آ‚è‹؟‚پB
|