پ@پ@‘‚“´ڈ@‚جŒڑŒ÷ژ›‚حپA–{ژR‚ج‘چژژ›‚ئ“¯—l‚ة—Rڈڈ‚ج‚ ‚邨ژ›‚³‚ٌ‚إ‚·پBژ؛’¬ژ‘م‚©‚ç‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB”nڈê’¬‚ح‚»‚جگجپAگz–Kژپ‚ئ‚¢‚¤چ‹‘°‚ھ‚¨‚èژ›”ِڈéڑ¬‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ڈZگE‚ح‘¢‰€‰ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚à’m‚ç‚ê‚é
پ@ڈZگEپAe–ىڈr–¾‚³‚ٌ‚ح‘¢‰€‰ئ‚ئ‚µ‚ؤ‚à—L–¼‚إپANHK‚ب‚ا‚جƒپƒfƒBƒA‚ةژو‚èڈم‚°‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢پB‚»‚جژ‚حڈ@‹³‰ئ‚إ‚ح‚ب‚پAƒAپ[ƒeƒBƒXƒg‚ئ‚µ‚ؤڈo‚ؤ‚¨‚ç‚êپAƒ†ƒjپ[ƒN‚بگl‚¾‚ب‚ ‚ئژv‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پ@’كŒ©‚ج‰wƒrƒ‹پuCIAL’كŒ©پvپi‰،•lژs’كŒ©‹و’كŒ©’†‰›پj‚ج‰®ڈم‚ة‚àپAƒ_ƒCƒiƒ~ƒbƒN‚ب“ْ–{’뉀‚ً‘¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژ›‰@‚âگ_ژذ‚©‚ç‚جˆث—ٹ‚à‘½‚¢‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAƒzƒeƒ‹‚âŒِ‹¤‚ج‰ïٹظپAٹCٹO‚ج‘¢‰€‚àژèٹ|‚¯‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB
پ@‚³‚ؤپA‘هٹA“ْ‚ج–é‚إ‚·پB‚²‰ئ‘°کA‚ê‚ج•ûپX‚ھŒڑŒ÷ژ›‚ض‚ج“¹‚ً•à‚¢‚ؤچs‚«‚ـ‚·پBژگـپAŒڑŒ÷ژ›‚جگڈà‚ج‰¹‚ھ•·‚±‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚·پB
پ@‚و‚¤‚â‚پAژR–ه‚ة‚½‚ا‚è’…‚‚ئپAˆأ‚¢ˆإ‚ج’†‚ةک؛–¾‚é‚¢–³گ”‚ج–¾‚©‚è‚ھ‘«Œ³‚ًڈئ‚炵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژخ‚ك‚ة‚»‚¬—ژ‚ئ‚µ‚½20ƒZƒ“ƒ`‚ظ‚ا‚ج‘¾‚¢’|“›‚ةپA‚¨“•–¾‚ھ“”‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚êˆبٹO‚جڈئ–¾‚حژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@Œ¶‘z“I‚بŒُ‚ة“±‚©‚ê‚ؤپAٹK’i‚ً“o‚é‚ئژR–ه‚ھ•‚‚©‚رڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚‚éژïŒü‚إ‚·پB‚ئ‚±‚ë‚ا‚±‚ë‚ةپA‚¨“•–¾‚ًژ‚ء‚½ژل‚¢گl‚ھپu‚±‚ٌ‚ة‚؟‚حپv‚ئ‚©پAپu‚و‚‚¢‚ç‚ء‚µ‚ل‚¢‚ـ‚µ‚½پv‚ئ‚©گ؛‚ًٹ|‚¯‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پB‘½–€”üڈp‘هٹw‚جٹwگ¶‚³‚ٌ‚¾‚»‚¤‚إپA—ل”N‚جچsژ–‚ئ‚µ‚ؤژQ‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پBڈZگE‚جe–ى–¾ڈr‚³‚ٌ‚حپA‘½–€”üڈp‘هٹw‚إپu‘¢‰€پv‚ً‹³‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA‹³‚¦ژq‚½‚؟‚ھژè“`‚¢‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚½‚ٌ‚إ‚·‚ثپB
پ@‚ ‚ـ‚è‚جˆأ‚³‚ةƒJƒپƒ‰‚جگ«”\‚ھ’اگڈ‚¹‚¸پAŒ©‚½–ع‚ج”ü‚µ‚³‚ح“`‚ي‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚±‚جچsژ–‚حپuنف“•ڈœ–éپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ژR–ه‚ـ‚إ‚جٹK’i‚ھ35“x‚‚ç‚¢‚جŒXژخ‚إپA“o‚è‚«‚é‚ج‚ھ‚ئ‚ؤ‚àگh‚¢پB‚³‚ç‚ةگi‚ق‚ئپAژQ“¹‚ةƒAپ[ƒ`ڈَ‚ة•¢‚ء‚ؤ‚¢‚é–طپX‚جژ}‚ةپA‚¨“•–¾‚ً’ف‚邵Œُ‚ج“¹‚ھڈo—ˆ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBچ،‚ـ‚إ‘«Œ³‚¾‚¯‚ج–¾‚©‚è‚ھ‹}‚ة“ھڈم‚ةچL‚ھ‚é‚ج‚إˆس•\‚ً“ث‚¢‚½ژïŒü‚إ‚·پB
پ@پu‚¨‚ءپAمY—ي‚¾پIپv‚ئ‚¢‚¤گ؛‚ھژQŒw‹q‚ج’†‚©‚ç•·‚±‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚¨ژQ‚è‚جگl‚ھ‘½‚¢‚ج‚ئپA‚±‚ج•—ڈî‚ًٹy‚µ‚قگl‚ھ‚¢‚é‚ج‚إپA•à‚ف‚ح’xپX‚ئ‚µ‚ؤگi‚ف‚ـ‚¹‚ٌپB
پ@‚µ‚خ‚炤‚±‚¯‚آ¤‚ـ‚½پA‚±‚ë‚ر‚آ•à‚¢‚ؤ‚¢‚‚ئپA•ھٹٍ‚ج“¹‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB•ذ‚âڈàکO‚ةŒü‚©‚¤“o‚蓹‚إ‚·پBڈàکO‚ح’|—ر‚ج’†‚ة‚ ‚èپA‘ه‚«‚بٹâ‚ھŒح‚êژRگ…‚ج‚و‚¤‚ة”z’u‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBڈàکO‚ةŒü‚©‚¤ٹK’i‚ج“r’†‚ة‚¨ژذ‚ھ‚ ‚èپAپuگz–Kگ_ژذپv‚إ‚ح‚ب‚پAپu”’ژRگ_ژذپv‚ئ“ا‚ك‚ـ‚·پB
پ@‚و‚¤‚â‚ٹJ‚¯‚½ڈêڈٹ‚ة‚½‚ا‚è’…‚«پA–{“a‚ھگ³–ت‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·پB‚¨وخ‘K‚ً“ٹ‚°‚ؤپAˆê”N‚ج–³ژ–‚ً‹F‚è‚ـ‚·پB
پ@‚±‚ج‚¨ژ›‚³‚ٌ‚حگz–Kژپ‚ة‚؟‚ب‚ٌ‚¾‚ج‚©پAگz–Kگ_ژذ‚إ—p‚¢‚ؤ‚¢‚éپuٹپپv–ن‚إ‚µ‚½‚ھپAڈ‚µŒ`‚ھˆل‚¤‚و‚¤‚بپB”’کg‚ج’†‚جچ¶‚ھˆê”ت“I‚بٹپ–ن‚إپA‰E‚ھگz–Kگ_ژذ‚جٹپ–ن‚إ‚·پBگz–Kگ_ژذ‚ج‚à‚ج‚ةŒ`‚ھژ—‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA—t‚جŒ`پAچھ‚جŒ`‚ھˆل‚¢‚ـ‚·پBگz–Kژپ‚حگV“cژپ‚ب‚ج‚إ–{—ˆ‚ب‚çپAٹغ‚ةˆê‚آˆّ—¼‚إ‚·‚ھپA‰½Œج‚©ٹپ–ن‚إ‚µ‚½پB
پ@‚³‚ؤپA“ü‚èŒû‚إ’¸‚¢‚½‚¨“•–¾‚حپA‚±‚±‚إگ…”ص‚ج’†‚ة“ü‚ê‚ؤ‹A‚è‚ـ‚·پB‚ب‚ٌ‚¾‚©ƒˆپ[ƒˆپ[’ق‚è‚ج‰ڈ“ْ‚ج‚و‚¤‚إ‚µ‚½پB
پ@‹A‚è‚ج“¹‚ح‚ـ‚½ˆل‚¤“¹‚ً’ت‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚±‚ةگخ•§پA“¹‘cگ_‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ة‚àƒ‰ƒCƒeƒBƒ“ƒO‚ھژ{‚µ‚ؤ‚ ‚褂¢‚©‚ة‚àˆê”N‚جŒv‚ھژn‚ـ‚éٹ´‚¶‚إ‚·پB
ژ؛’¬ژ‘م‚©‚猻‘م‚ـ‚إپAژ›‰@‚â’뉀‚ًژc‚µ‚ؤ‚¢‚‚ج‚حپA‘½‚‚جگlپX‚ج“w—ح‚جژ’•¨‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚»‚±‚ةگV‚½‚بˆسڈ ‚ً‹أ‚炵پAلS‚点‚é‚ج‚àگl‚ج‹ئ‚إ‚·‚ثپB
پ@ŒڑŒ÷ژ›‚ح“Œ‰،گü–ک@ژ›‰w‚©‚çپgگ…“¹“¹پh‰ˆ‚¢‚ة•à‚¢‚ؤ15•ھ‚ظ‚ا‚إ‚·پBچ،”N‚ج‘هٹA“ْپA‚¨ژQ‚肵‚ؤ—ا‚¢‚¨”N‚ًŒ}‚¦‚½‚ç‚¢‚©‚ھ‚إ‚·‚©پB
|

ŒڑŒ÷ژ›‹«“à
2012”N‚PŒژ‚P“ْژB‰eپF“üŒû‚إ‚¨“•–¾‚ً”ƒ‚¢‚ـ‚·
|

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@نف“•ڈœ–é
2012”N‚PŒژ‚P“ْژB‰eپFٹK’i‚ج‘«Œ³‚ة“•–¾‚ھ‚ ‚è,’|‚ب‚ج‚إگ´پX‚µ‚¢ٹ´‚¶‚إ‚·
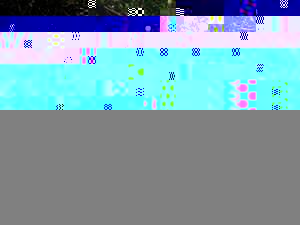
نف“•ڈœ–é
2012”N‚PŒژ‚P“ْژB‰eپF“ھڈم‚ة‚ ‚邨“•–¾

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈàکO
2012”N‚PŒژ‚R“ْژB‰eپF’|—ر‚ج’†‚ة‚ ‚è•—ڈî‚ذ‚ئ‚µ‚¨

ٹپ–ن
2012”N‚PŒژ‚P“ْژB‰eپF›ي–‹‚جٹپ–ن‚ھ“–ژ›‚ج‚à‚ج

گ…”ص
2012”N‚PŒژ‚P“ْژB‰eپF‚²‰ڈ“ْ‚ج‚و‚¤‚ةٹy‚µ‚¢‚إ‚· |
|
|
|
|
|
|