|
東横線大倉山駅下車、徒歩10分で港北区師岡(もろおか)の熊野神社につく。神社は、神亀元年(724年)金寿仙人がいまの社殿裏の「の」の池のところにあった椰樹(なぎ)の大木のほこらに住んでいたとき、ここに社(やしろ)をつくれというお告げによって小さな祠をつくったことに始まるという。千二百余年の歴史がある。
熊野神社の前には、ひらがなの「い」の字の形をした『い』の池があり片目の鯉の伝説が語られている。
|
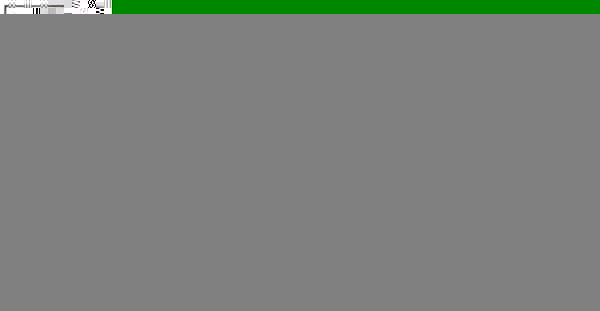
熊野神社の「い・の・ち池」所在地を示すマップ
|
|
|
むかし、熊野神社の神、権現は、この地方の悪者と戦って片目になってしまった。
ある日、権現が池の畔に立つと、池のぬしの鯉があらわれて、ジーッと権現さまを見つめていた。光った大きな目で見つめていた。
権現は、目が欲しゅうなった。
「のお、わしにその片方の目をゆずってくださらんか」
権現の心がつうじたのか鯉は、片方の目をさしだした。
この話は、師岡村はもとより神奈川宿にまで知れわたった。そんなある夜、池に忍びこんだ男が鯉をしゃくって逃げていった。
つぎの日、男は、神奈川宿へその鯉を売りにいったが宿場のかみさんが鯉を見て、
「片目の鯉だ。ことによったら熊野神社の鯉かもしれん。食べたらたたりがある」
と、いうて誰も買おうとせんかった。
男は、たたりときいて、まっ青になりその夜、池に鯉をかえした。それから『い』の池のさかなは、みんな片目になったそうな。
『い』の池は、水たまりのようだが、水は神の水(禅定水)とされている。むかし、熊野神社が落雷をうけて火事になったとき、『の』の池の水でご神体を守ったという。また、どんな日照りがつづいても水の涸れるときがなかったという。
また、『い』の池でも雨乞いの行事がおこなわれた。承安4年(1184年)日照りのつづいたとき、延郎上人が、12の竜頭をつくり、八大竜王を招くと、三日三晩、大雨が降り田畑の作物を生き返らせたという。
|