横浜市港北区岸根町の盆踊りでうたわれる『岸根音頭』に
♪ハァヨイホ 岸根の琵琶橋 武蔵の名所
むかし 琵琶法師 むかし 琵琶法師
流れも歌う ハァヨイホ ハァヨイホ
という一節がある。
その琵琶橋は、いまはないが、あったところは、東横線白楽駅下車、県道横浜上麻生線の岸根バス停から小机の方に向かって少し行った小川の右手(下の写真)で、昔、このあたりを鎌倉街道がとおっていたという。
その琵琶橋には、伝説が語られていた。
むかし、ある秋だったと。
とりいれを待つ岸根の村にひとりの琵琶法師がどこからともなくやってきた。長い旅をつづけてきたのだろう。わらじは、すりきれ、衣はほころびていた。
法師は、風呂敷包をしょい、手には大事そうに古い琵琶をかかえていた。
法師は、目が見えなかった。田んぼの畔にしゃがんで休んでいた。
秋風は、さわさわと稲穂をゆすっていた。
「おお、豊年のようじゃ。お百姓しゅうも秋祭りを待っておられるじゃろ」
法師は、重そうにたれている稲穂をさわって豊年万作をわがことのように喜んでいた。一服した法師は、稲穂とわかれてしばらく行くと立ち止まった。前には小川がコボコボ、コボコボと流れている。
「おお、ここは静かなところ。ごめいわくかけることもあるまい」
法師は、草ぼこに腰をおろすと琵琶をかきならした。
ピョンピョン ピョンピョン ピョン……
草ぼこて鳴いていた虫も法師の琵琶のひびきにききほれたようにぴたりと鳴きやんだ。 ピョンピョン ピョンピョン ピョン……
|
秋の日はつるべ落とし。あたりは暗くなった。法師が立ち上がったとき、胸ぐらをつかまえた者がいる。
「金を出せっ! その包もおいていけ」
「ど、どなたか存じませぬが、おらは旅の法師。武蔵の寺をまわろうと思ってこの地にさしかかった者です。どうかお見逃しくださいませ」
法師が頭をさげたとき、盗賊は、風呂敷包とわずかな銭のはいった袋をひったくった。
怒った法師は、「返せ、返せ」と叫んでむかっていった。
「うぬ、なまいきな。目も見えんというのに。え−いっ!」
法師は、琵琶をかかえたまま川に突き落とされてしまった。すると、川の中から琵琶をひく音がひびいてきた。
ピョンピョン・ピョンピョン…………
呪うようなひびきに盗賊は、おそれをなし逃げていった。
それから夜にここを通ると、どこからともなく悲しげな琵琶の響きがきこえてきたという。年月が流れてここに丸木橋がかけられた。
村の人は、悲しい法師の死をいたんで琵琶橋と名づけたと。
|
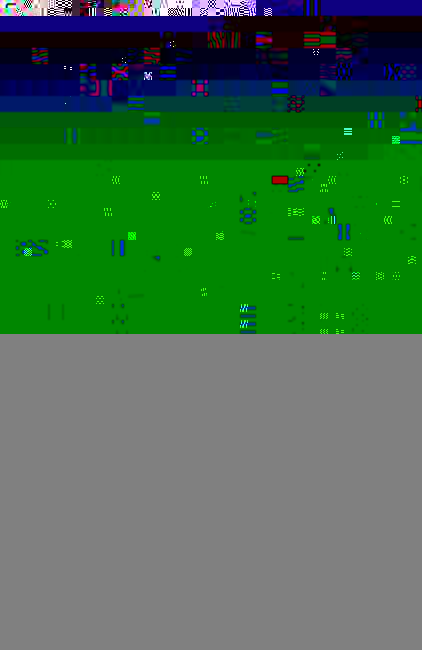
絵:石野英夫(元住吉)
|
|
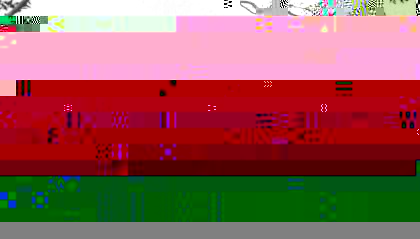
昭和39年新河川開通当時、枇杷橋があった「八軒谷戸」
右手山裾の茅葺きの家は枇杷橋の脇にあり、屋号「枇杷橋」の岩田鉄夫さんの家
提供:高橋 稔さん(岸根町)
|
|

写真左と同じ場所から見た平成16年
撮影:岩田忠利
|
|
|