|
菅堀を矢野口駅方面に辿っていくと、大きな柳の木が見えてきます。これは大丸親水公園の中にある遊び場です。子供が用水に近づかないように、いちおう柵がしてあります。先ほどとは異なり、今度は反対側の岸に、円形の淀みが造られています。
|
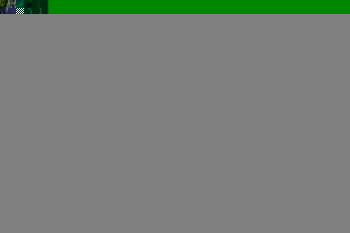
大丸親水公園
2014年10月17日撮影:水田の近くに住宅が並んでいます |
|
|
稲城市の観光案内、「-江戸時代の歴史を中心として-」では、
「大丸用水を使った地域は、江戸時代には稲城地域の4村(大丸村・長沼村・押立村・矢野口村)と川崎地域の5村(菅村・中野島村・菅生村・五反田村・登戸村)でした。これらの村々は、橘樹郡と多摩郡という二郡にまたがり、支配領主も異なっていましたが、大丸用水を利用するという点では一致しており、「大丸用水九ヶ村組合」を組織していました。」
と記されています。「大丸(おおまる)」という地名は、この仕事に携わる前には、聞いたことがありませんでしたが、それ以外は、殆どの村が聞いたことがある名前です。
現在大丸地区は、梨や、葡萄の果樹園が盛んなところで、今でもこの用水を利用しています。しかし、このあたりも市街化が進んできており、住宅が多くなってきました。いきおい、生活排水や雨水のための排水溝が必要になります。排水溝が用水を跨ぐときは、このような懸け樋で対応しています。ちょっと珍しい風景です。
|
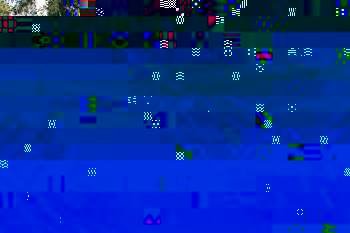
横断する懸け樋
2014年10月17日撮影:増水したときが心配です |
|
大丸用水の水位と道路との高低差はほとんど無く、夜などうっかりすると踏み外して、堀に落ちてしまいそうです。そして至る所に分水樋が存在し、無数の支流が出来ています。家の脇を通る溝のようなものから、大きな川のようなものなど、大小さまざまです。
|

分水樋
2012年11月9日撮影:当新田の近く |
|
|
そうこうする間に、雁追橋跡に着きました。脇の碑文にはこんな昔話が……。
「江戸時代の頃に、この近くに、大変美しくて、気立てのいい女の人が住んでいました。この人は御殿女中と言って、江戸幕府の中で働いていた人でしたが、どんなことがあったのかわかりませんが、この地に移り住んでいるのでした。近所でも評判の美しい人でしたので、村中の男たちは、キュウリができたり、ナスができたりすると、こぞって持って行きました。なんと仲良くなろうと思ったのでしょうが、大変貞淑な人だったので、男たちはすぐに帰されてしまいました。このころの稲城には、多摩川のほとりにたくさんの雁が来ていました。村人たちはこの雁にたとえて「雁と同じように男たちが集まってくるが、すぐに追い返されてしまう」と言って、うわさをたてました。女の人は長くこの地に住みましたが、そのうちに「雁追婆さん」と呼ばれるようになり、橋の名前にもつけられたのです。今では雁の姿もほとんど見られなくなってしまいました。」
と「稲城の昔ばなし」の逸話が記されています。晩年の姿まで書かれてしまうと、なんだか寂しい話に感じますね。
|
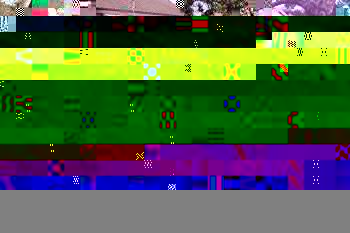
雁追橋跡
2012年11月9日撮影:橋が架かるほど大きな川は無いようですが |
|
|
ここまで稲城市文化財地図(平成20年(2008)1月)を頼りに歩いてきました。その地図を見ると、近くに但馬稲荷神社がありました。そこで、少し引き返しました。但馬新田のあたりに分水樋があり、長閑なことに,鴨の夫婦が羽を休めていました。
用水の土手の丸石は、江戸時代からあるものなのでしょうか。多摩川から運んだとしても、大丸用水はおよそ200本の支流があるそうで、大量な丸石が使われていることになります。
但馬稲荷神社は大変立派な参道を持っています。お社はさほど大きくはありません。伏見稲荷大社が総本社で、宇迦之御魂神・倉稲魂命を祭ると、置石の脇の木板に書いてありました。
この割れた置石には句が彫ってあります。芭蕉の句碑だそうで、
「此あたり 目に見ゆるものは 皆涼し」
とありますが、割れていますので判別するのが難しいです。この辺りまで、芭蕉が来たのでしょうか。
(続く)
|

分水樋
2012年11月9日撮影:但馬新田のあたり、石の上に鴨の夫婦がいます |
|

但馬稲荷神社
2012年11月9日撮影:お社の場所は何か霊的な感じがします |
|