|
گ›–x‚ح200‹ك‚‘¶چف‚·‚é‘هٹغ—pگ…‚ج‚¤‚؟‚جپA”نٹr“I’·‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB
پ@چ‘“yŒً’تڈبٹض“Œ’n•ûگ®”ُ‹ا‚جژ‘—؟‚إ‚حپA
پu‘هٹغ—pگ…‚حپAˆîڈéژs‘هٹغ‚جژوگ…Œû‚©‚瑽–€گى‚جگ…‚ًژو‚è“ü‚ê‚ؤپAگىچèژs“oŒث‚ـ‚إ—¬‚ê‚鑽–€گى‰Eٹف‘¤‚ةˆت’u‚·‚é—pگ…‚إپA‚X–{‚ج–{—¬‚ئ–ٌ200–{‚جژx—¬‚ًچ‡‚ي‚¹‚½‘چ’ى’·‚ح70ƒLƒچ‡b‚ة‹y‚ر‚ـ‚·،پv
پ@‚ئ‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إپAگ›–x‚ح–{—¬‚جˆê‚آ‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پ@پ@ژوگ…–x‚حچ،‚ج“ى•گگü‚ج“ى‘½–€‰w‚ج–k‘¤‚ةˆت’u‚µ‚ؤ‚¨‚èپA—pگ…‚ئ’JŒثگى‚ھŒًچ·‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚ةپAچ]Œثژ‘م‚ج“y–ط‚ج’mŒb‚إ‚ ‚é•ڑ‰z‚ة‚و‚ء‚ؤپAگ…کH‚ھ•غ‚½‚ê‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½،
پ@
پ@‚µ‚©‚µپAچإ‹ك‚ج“ى‘½–€‰wژü•س‚جژsٹX‰»گ®”ُچHژ–‚ة‚و‚èپA’JŒثگى‚ئ‚ئ‚à‚ة•ڑ‰z‚حڈء–إ‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
|

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•ڑ‰zگص
2012”N11Œژ13“ْژB‰eپFژè‘O‚ھ—pگ…پAƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒgˆâچ\‚ھ’JŒثگى•ڑ‰zگص |
|
|
“ى‘½–€‰w‚ج“Œ‘¤‚ةپA‘هٹغ—pگ…‚ج•ھ—ت”َ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
پ@‚PپF‚Q‚جٹ„چ‡‚إ–x‚ھ•ھٹ„‚³‚êپA‘هٹغ‘؛‚ئ‘¼‚ج‘؛پA•”—ژ‚ة—pگ…‚ھ•ھ”z‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBچ،‚à‚±‚جˆâچ\‚حژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@ˆîڈéژs‚جپu‘هٹغ—pگ…پ|چ]Œثژ‘م‚ج—ًژj‚ً’†گS‚ئ‚µ‚ؤپ|پv‚إ‚حپA
پ@پuژو“üŒû‚حپA‘هٹغ‚جپuˆê‚جژR‰؛پv(Œ»چف‚ج“ى•گگü‘½–€گى“S‹´‚ج‚â‚âڈم—¬)‚ة‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‘½–€گى‚ة’·‚³–ٌ100ٹش(–ٌ182‡b)‚جژوگ…‰پ‚ً’z‚«پA‚±‚±‚إ‚¹‚«ژ~‚ك‚ç‚ꂽ‘½–€گى‚جگ…‚ح‰،•‚Qٹش(–ٌ3.6‡b)‚ج—pگ…ڑ§”َپi‚¢‚è‚ذپj(—pگ…‚ًˆّ‚«“ü‚ê‚邽‚ك‚جگ…–ه‚ج”َ)‚©‚çژوƒٹ“ü‚ê‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پBژوگ…‚³‚ꂽگ…‚حپA‚ـ‚¸‚¤‚؟–x‚ً’ت‚ء‚ؤ•ھ—ت”َ‚ض‚ئŒü‚©‚¢‚ـ‚·پB•ھ—ت”َ‚حپA‘هٹغ‘؛—p‚ج—pگ…‚ئ‘¼‘؛—p‚ج—pگ…‚ً•ھ‚¯‚邽‚ك‚ة•tگف‚³‚ꂽ”َ‚إپA–x•‚ح‘هٹغ‘؛—p1‚ة‘خ‚µ‚ؤ‘¼‘؛—p2‚جٹ„چ‡‚ة•ھ‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚±‚إ•ھگ…‚³‚ꂽ‘هٹغ‘؛—p‚ج—pگ…‚ح‘ه–x‚ئŒؤ‚خ‚êپA‘هٹغ‘؛‚ج“ى•”‚ًڈپ‚µ‚½‚ج‚؟’·ڈہ‘؛پE–î–ىŒû‘؛‚ً—¬‚êپA‚³‚ç‚ةگىچè•û–ت‚ةŒü‚©‚¢‚ـ‚·پBپv
پ@‚ئ‹Lڈq‚³‚êپA“–ژ‚ج‘؛–¯‚ة‚حپA‚±‚جگ…—ت‚جٹm•غ‚ھژ€ٹˆ–â‘肾‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB
|

•ھ—ت”َگص
2012”N11Œژ‚X“ْژB‰eپF—pگ…•‚ھ1پF2‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚· |
|
پ@‚±‚±‚©‚瓹کHˆê–{‚ي‚½‚é‚ئپA—pگ…‚جڈم‚ةڈ¬‚³‚بŒِ‰€‚ھ‚ ‚èپA“،’I‚ھ”ü‚µ‚’nˆو‚جڈZ–¯‚ج•û‚ھپAژè“ü‚ꂳ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ•·‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·،
پ@چX‚ةگi‚ق‚ئپA‘هٹغگeگ…Œِ‰€‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پB‚»‚±‚ة‚ح‰~Œ`‚ج—„‚ف‚ھ‘¢‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژü‚è‚حگ…“c’n‘ر‚إپAگـ‚µ‚àˆîٹ ‚è‚جگ^چإ’†‚إ‚µ‚½پBپi‘±‚پj
|
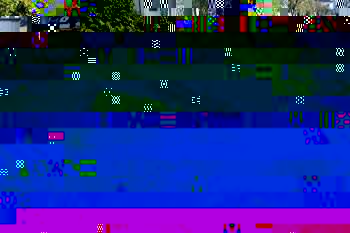
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هٹغگeگ…Œِ‰€
2014”N10Œژ17“ْژB‰eپFƒTپ[ƒNƒ‹“à‚ةŒï‚ھڈW‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚· |
|