|
�@�@�֓���k�Б̌��k�����щp�j����
�@�@�@�g�����̑�n�k�h���o�����Ă���c���̋@�]
�i���@���o�Ȃ̊F����̒��ɂ́A���̊֓���k�Ђ̖͗l���悭�o���Ă������������������Ǝv���܂��B�����ŁA���a���܂�̓ǎ҂̊F���܂ɑ吳12�N9��1���̑�n�k�̑̌��k���c�c�B
�@73�N�Ԃ����L�����������Ă���ꂽ���т���A���̓��̖͗l�����R�L����Ă���̂ł��傤�˂��H
�����@�ˑR�O���O���b�Ƃ��āA���ꂪ�u�V�n�̏I��肩�v�Ǝv�����Ƃ����悤�Ȉ�ۂ����L�ɂ͏����Ă���܂���B
�@�����Éi�S�N�i1851�N�j���܂�̑c�����������Ɂg�����̑�n�k�h���o�����Ă����ł��ˁB�����͕����Ŋ��̂Ђ������o�Ă���̂ł��B
�@���̑c�����܂���ɍ~��āu�O�ɏo�Ă����Ȃ��B�Ƃ̒��ɋ�����I�v���đ吺�Ő��~�����̂ł��B�ЂƂ菗�������܂��ĂˁA�ޏ����O���b�Ƃ����u�ԁA���̋r�ɂ����݂���������B�Q�ĂĒ����ȂƊԈႦ�Ă˂��B
�@�ЂƂ�����Â܂�̂�҂��āA�O�̋n�ɉᒠ�i����j��݂��ĉ�����o���A���̒��łQ�ӂ��炢��𖾂����܂����˂��B
�@�֓���k�Б̌��k�����c��������
�@�@�@�@�X���R�}�̏�ɏ���ĉ���Ă���悤�c
�i���@���c����A�a�J�̕��͂������ł������B
���c�@���͓���12�B9��1���͎n�Ǝ��̓��Ŋw�Z����A���Ē��A��Ă��F�B�Ǝ����̐搶�̉Ƃ֍s���r���ł����B
�@�ŏ��u�S�I�[�b�v�Ƃ����������Ă���A���͗F�B�Ɂu����A�����o�Ă����̂ˁv�ƌ������r�[�ɁA�h�ꂪ�n�܂����̂ł��B�ƁA���̓������ɂ������p���̐����s�`���s�`���ƍ���������A�O������Ă����w�����u����A����`�I�v�Ƌ��ԁB
�@���Œn�ʂɍ����Ėڍ��̊X�̕���������ƁA�X���Ɗy�i���܁j�̏�ɏ���ĉ���Ă���悤�Ɍ����܂����ˁB
�@�Â܂��Ă���T�̒�����Ԃ��č��̓�����̃C���L�̊ዾ���̏��܂ŋA���Ă���ƁA�������������œ��͖��܂��Ă���B�߂��̂������̎p���݂���ƁA�u�悭�A���Ă����A�悭�A���Ă����v�Ɨ܂��{���{�����ڂ��āc�B
�@���ꂩ��Q��ڂ̒n�k�c�c�B�~�̖ɂ��܂��Ă��܂������A�Ƃ̉������n�ʂɓ͂���Ȃ����A�����Ă��̐��̏I��肩�ȂƂ����悤�ȋC�����܂����B�@
�@�@�@�@�s����������f�}�Ɨ������
�@���̔ӂ͂������Ƃɂ�����܂���A��h�ł����B�����ĂQ���ڂ̔ӂɂ��́u���N�l���P���Ă��邩�瓦����v���Č����A���̕S���X�i�Ђ�����ȁj���܂��ԓy�̎R�ł�������A�݂�Ȃ����ɓ�������ł��B
�@���ꂪ����Ȕ�펞�Ƀf�}�𗬂���ł����˂��B
�@�u������A���N�l���������`�v�Ȃ�ċ��Ԑl�����邩��A�ꕔ�̐l�������|���ɂȂ�܂��Ă˂��B�ŁA�ꂪ�u����ȑ吨����ꏊ�Ŏ��˂A�N�̎��̂����킩��Ȃ��Ȃ����Ⴄ�B�����̉ƂA���Ď��̂��I�v�ƌ����Đ^���Èł̓�������������܂������A�����̋�͂܂��Ԃł����B���̓����ɂ͌��⏊�������ł��ˁB�u�ǂ��̒N�X���v�ƁA�����������ׂ�̂ł��B
�i���@���ɂ���ד����̔�Q�͑傫�������悤�ł��ˁB�Â܂��Ă���̐����͂������ł������B
���c�@���ǂ��̉Ƃ͑݉Ƃł������肵���Ƃ���Ȃ��ł�����A20���ԂقǑ�Ƃ���̉Ƃɔ��߂Ă��炢�A�X�����Ƃ��܂����B�H�ו��́A�~��T�o�̊ʋl�E�������̃J���s���E�Ȃǂ̋~�������̔z�����w�Z�̒�ōs���A�Ȃ�Ƃ������ł����킯�ł��B
|
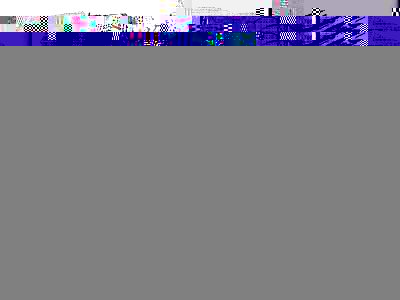
���c�������w�吳�E�a�J������x�́u�֓���k�ЂƓ�����v����
|
|
|
�@�֓���k�Б̌��k���R���܂�����
�@�@�@�@�@�@���� �Ƃ����̋@�]�ƍs���́c
�i���@�R������͋��R�ɂ����c����Ɠ����N�������ł����A�������l�ł����₩�ȊX���������_�ސ�ɂ��Z�܂��ɂȂ��Ă��āA������̔�Q�����������ł��傤�H
�R���@���̎����͏��w�Z�T�N���ł������A���傤�ǎq���̈�V�{�_�Ђ̂��ՂŁA�n����̉Y�����w�Z�͂��x�݁A�Ƃɂ��܂����B����i�������j�͂�������̏����тł����̐H���̂Ƃ��A�����Ă����q���R���s�[�s�[����ł��B���������Ƃ��A�������͕q���ł��ˁB�s�R�Ɏv���ėl�q�����ɍs������A�K�^�K�^�ƒn�k�c�c�B
�@���̏u�ԁA�����A�Ԕт̓�������C�i���Ђj���u���V�̉��ɉB���I�v���Č�����ł��B�߂��̐_���_�Ђɓ����܂����́B
�@���ꂩ��́A�����悤�ɒ��N�l�����łˁA�Ƃɂ͋A��Ȃ����A�Ƃ̏�����_�Ђ̋����Ɏ������݁A�����Ŗ�h���܂����̂�B���̂Ƃ��A�H�c������C�̒��̐Ԕт�H�ׁA���������������ƁI
�@���̌�A�Ђ������B�ߌ��̐�������_�ސ�̎q���܂ŔR�������A���l����͓��_�ސ�̌����l������܂ŏĂ��s�������̂ł��B�킪�Ƃ͏Ă��܂���ł������A�����v��11��58���ŁA�~�܂��Ă��܂����́B
�@���̂Ƃ��A�q���̎������������͕̂��̋C�]�̗ǂ��ł����B
�@�����̎�������ؖȎ��A����������؎���Ȃǂ��W�߂Ă��āA���Ȃʼn��{���������臁���������̂ł��ˁB������̓d�M���ɕt���ĕ����܂����́B
�@�����Ő^���Èł̐_�������ɁA�������Ȃ��疾���肪�������̂ł��B���������s���̂Ƃ��A�u����͓d�C�����܂��v�ƁA�ɔ��f���镃�̋C�]�̑����Ƃ��̍s���͂Ɋ��S�������̂ł����B |
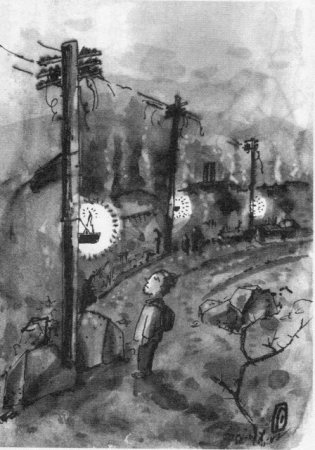
�R���܂����w���̂��h�x����
�G�F�Ζ�p�v |
|
�@�@�@�@�C����̐l�Ԗ͗l
���c�@���炢�����l�ł��ˁB
�@���ǂ����Z�ޏa�J�ł͔��鉺���̐l�����̍s��A�ߎS�ɂ܂�Ȃ������ł��ˁB
�@�Ă������ꂽ���A�������ɂȂ������̖сA���q�ǂ���w��������e�A�ǂ̐l���ア���ǂ�ő�������ʂ֓����邽�߂Ƀ]���]���Ɠ������o���Ă����B�g�Ɋy��y�̒ҁh�Ƃ����̂́A�������������Ǝq���S�ɑz�����Ă݂����̂ł��B
�R���@���ǂ������C���̐_�����ł��傤�B�����ʂ��瓌���̐e�ʂ����ɍs���l�A��Q�҂̐l�A�������������ǂ�ǂ�ʂ�܂�����B
�@���ł��ڂɏĂ����Ďc���Ă���̂́A�葫���_�����Ƃ��Ď��F�ɂȂ������q���e���̂Ă�킯�ɂ��������A�����Ĕ�����i�B
�@�Ƃɂ͈�˂�����܂��āA��ː����ǂ�ǂ�ł͈�l�M�i�ЂƂ���j�ɓ���A�\�̑�ʂ�ɏo���܂����B�ƁA�ꏡ�r��҂��Ă����ʍs�l�������Ɓu�����ɍs������A���������v�Ɣq�ނ悤�ɁB
�@�@����Ȏ�����A�悻�̑q�ɂ���ޗ��𓐂ݏo���āg�c���\���h������Ĕ����Ă���l��������ł�����˂��c�c�B
���c�@�������͎q�����납��u���قǑ�Ȃ��̂͂Ȃ��v�ƕ����Ă����ł��ˁB��q�T�l��������Ƃ����A������ꂽ�P���r�Q�{�Ɛ�c�̂��ʔv�i���͂��j�������A�ꂪ�����̍��Ɏ�ʂ������܂��āA�S�l�̎q��������ɂ��܂��ă]���]�����Ƃɑ����̂ł��ˁB
�@��������������F�B�̘b�ł��ƁA�u�A�������āA�A�������āv�ƁB���������قǂ��A����ɍ��R���Ȃ��A���̂����������Ă����ɐ��ꉺ����B�����āA����������グ�či���Ĉ��Ƃ�����ł����́c�c�B
|

�����ɕ�܂�A�卬�G�̂Q��ډ��l�w�i�������j
�f�}����ь����A���ɉݎԂɔ�я��A�����}���l�X
�@�F���J��O�a����(����ɐ����j
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|