ひとの人生に、それぞれ過ぎ去った過去があるように、私たちの町にも過去がある。
たとえ、小さな空間であれ、そこは汗と涙で築いた先人たち、その多くの足跡がある。
いま、同じ地に生きる私たちは、それを知り、現在と未来に活かさなければならない。わが町こそ……と次世代の人たちが誇れるように。
そこで、東横沿線の行政区分を越えて7区8名の代表が、新丸子・山王日枝神社に集い、晩夏のかすかなセミの声、扇風機の風を背に、『沿線の昔と今』を大いに語る……。
|
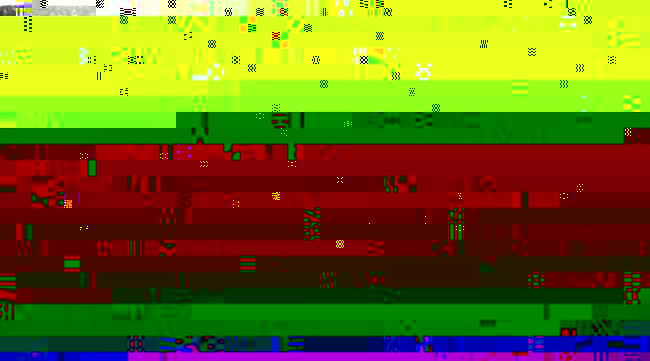
沿線の土地っ子の昔を語る座談会 丸子山王日枝神社社務所で |
|
|
| 出席者の顔ぶれ(各区代表) |
| 安藤金三郎さん |
目黒区代表。徳川時代初期から先祖は自由が丘に。自由が丘商店街の前副理事長。いまは同街史編さん委員長。画家。63歳 |
| 板垣大助さん |
港北区代表。日吉に16代つづく旧家の当主。民生委員。農協役員等で地域に貢献。造園業。58歳 |
| 小林英男さん |
中原区代表。中原区小杉御殿町在住の7代目。小学校教諭、旧中原町助役、元川崎市議、川崎市文化協会長など歴任。78歳 |
| 斉藤秀夫さん |
神奈川区代表。神奈川区旭ヶ丘在住。祖父の代、明治20年代後半から横浜に住む3代目。横浜市立大講師(地域政治論)。51歳 |
竹若勇二郎さん
芸名・杵屋勘次 |
大田区代表。昭和元年から30年まで田園調布に住み、今も仕事場は同地、自宅は中目黒。長唄家元。邦楽東明流家元の64歳 |
| 豊田眞佐男さん |
世田谷区代表。江戸時代の家業は酒造業で、いまの屋号が“酒屋”。世田谷区歴史研究会理事、民生委員。俳人。56歳 |
| 和田由美さん |
渋谷の資料を持参、オブザーバーで出席。両人はいとこ同士。先祖は元禄12年創業の酒問屋、宮益坂にあった「橋和屋」 |
| 渡辺昌枝さん |
| 司会 岩田忠利 |
「東横沿線を語る会」代表。本誌編集長 |
|
東急電車は目蒲線から
司会 お集まりの皆さんは、この沿線の〝生き字引〟みたいな人ばかり。そこできょうは、「子どもの頃の沿線の姿は、こんなだった」。そんな昔話を皆さんからたっぷり聞かせていただきましょう。
さっそく始めますが、最初に中原区の長老小林さんから口火を切っていただきますか。
|
小林 そうですね、私が一番古く記憶している東急の電車では、なんといっても目蒲線の開通。あれは確か大正12年。ちょうどあの時、築地にあった立教中学へ弟が入った時でした。やつが〝丸子の渡し″を渡って目蒲線の武蔵丸子(今の沼部駅)から目黒駅まで行って、それから山の手線に乗り換え有楽町まで……。
司会 東横線が開通したのは、その後でしたねえ。
小林 ええ、東横線が初めて横浜の神奈川駅(いまは廃止)まで行ったのは、大正15年2月14日でした。
|
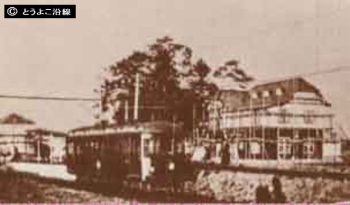
大正12年3月第1区間(目黒~現多摩川)が開通した時、洗足駅で |
|
南武線開通は昭和2年。あとからできたのに高架ではなく、いまの武蔵小杉駅は当時の駅名を「グラウンド前停車場」と言った。そもそもあの頃、南武線では駅よりも格下の“停車場”だった。それを住民が「停車場を造ってくれ!」と陳情して府中街道の端に「武蔵小杉停車場」ができた。
ずっと後になって、停車場が昇格して「駅」となり、武蔵小杉停車場が廃止され、「グラウンド前停車場」という名が「武蔵小杉駅」と改称され、今に至っているんだよ。
司会 なるほど……。グラウンド前駅とは、どこかにグラウンドでもあったんですか。
小林 あの辺には第一生命、山一証券、横浜正金銀行横浜支店のグラウンドがあって、そう呼ばれていたんですね。
司会 そういえば、今でも武蔵小杉駅のホームからグラウンドが見えますね。東横線が開通した当時、沿線の住民の反応はどんなものでしたか。
|
|

「グラウンド前停車場」と呼ばれた当時の南武線・現武蔵小杉駅
のち、「停車場」から「駅」に昇格、はじめて「武蔵小杉駅」と改称され、晴れて駅となった
|
|
|
小林 開通してからも、荷車は丸子の渡しに乗らなければ東京へ行けなかったけど、歩行者ならば丸子の渡しを渡らなくとも東京へ行けるって、みんな大喜びだったですね。
|
自由が丘辺りに群れをなす白サギ
司会 つぎに豊田さんの子どもの頃、一番印象強く残る沿線の風物は……。
豊田 私の子供の頃の話をしますと、驚かれると思いますが……。いまの自由が丘駅の近くがですねえ、小字名で「鷺野谷」という地名だったんです。
|
あの辺は水田。九品仏を囲む奥沢城の周りがほとんどいちめん水田でして、いま考えるとウソのように 〝白サギ〟が群れをなしていたんです。現在の踏切のあたりを「鷺の谷」という地名で呼んでいましたね。
大字名としては九品仏浄真寺の東門から自由が丘の駅までを「シロムカイ(城向かい)」というんです。「向い」というのは、戦国時代の住居表示としてお城とか武家屋敷の東側を必ず「ムカイ」と言ったんですねえ。
さらにこの機会に皆さんにご報告しておきたいのですが……。自由が丘駅の奥沢寄りの郊外、あの辺は盆地になっていて、町中に「沖の谷」という海に関係する地名が残っています。これは大昔、あそこまで東京湾の海水がきていたらしいのです。
|
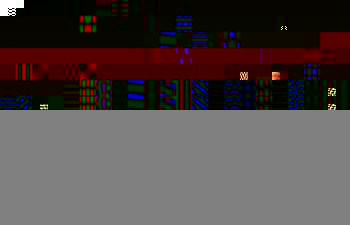
昭和2年、自由が丘3丁目10番の隣地、八幡中学校付近の耕地整理 提供:自由ヶ丘学園
|
|
司会 信じられませんねえ、いまの自由が丘や奥沢界わいからは……。安藤さんの子ども時代はどうでしたか。
安藤 私にとって印象深いのは、落語にもありますけど、〝目黒のタケノコ〟ですね。
|
生で食べていた目黒のタケノコ
安藤 目黒のタケノコの始まりは、薩摩藩の上屋敷か何かが目黒にありまして、鹿児島からいろんな竹を持って来て植えていたらしいんです。そのお屋敷に出入りしていた植木屋が、孟宗竹を貰い、その根を5、6本植えた。それが、目黒のタケノコの始まりだそうです。
そんなわけで、私の子供の頃は自由が丘のあの辺は畑、竹林、杉の森が主な風景でした。思い出しますねえ、学校へ行く前に、ちょっと地割れしているところを見つけては、木の枝を拾って指して置くんです。すると親が、3尺ほどの穴を掘って人糞などの肥料を入れ、タケノコをつくっていた。だから長いタケノコでしたよ。しかも太くて…。
土から顔を出さないやつでしたから、やわらかくって、そのまま生で食べるんですよ。私の子供の頃は、タケノコをゆでる、なんて知りませんでしたねえ。
それから、〝馬車〟を思い出しますね。いまの八雲のあたりから目黒駅まで、乗り物はこれ一つでした。「プッ、プッ、プー」ってラッパ鳴らして…。乗客はたしか10人くらいしか乗れなかったんじゃないかなあ。
|

安藤金三郎さん
(目黒区代表)
|
|
ラッパ鳴らして馬車が通る
|
司会 当時の馬車賃はどれくらいでしたかねえ?
安藤 子供の記憶ですから、覚えていませんね…。
小林 大正4年の私の日記によれば、多摩川の大坂を登った上沼部から五反田までの馬車が、当時9銭。ちなみに風呂が2銭、日比谷図書館も2銭、乗客は普通で8~9人、多い時で20人くらい。所要時間は40分ぐらいでしょう。
私は中学のころ、東京の寄宿舎にいて、月1回川崎の小杉の家に帰るんですよ。ときには、馬車より歩くほうが早い。なにしろ、2時間おきですから、五反田から歩いて2時間で家に着くなら、そっちのほうが早いし、15銭倹約にもなります(笑い)。
|

当時の乗合馬車 |
|
|
当時、すでに自転車もあったが、急な坂があるので登りは困難だし、下りは危険なんです。のちに馬車から中古車の〝乗合い自動車〟に……。それから目蒲線という電車が開通しました。それで、すっかり、馬車も乗合い自動車も姿を消しましたねえ。
司会 まさに、この沿線の交通変遷史ですね。目蒲線の開通は住民に大きな影響を与えたことになりますね。
|
|