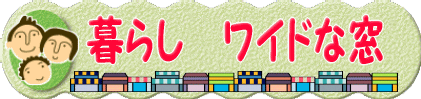 |
| 編集:岩田忠利 / 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |
| NO.312 2014.10.20 掲載 |
|
|
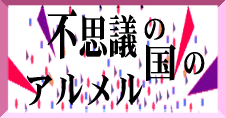 |
  |
筆者:アルメル・マンジュノさん
フランス人(女性)・港北区日吉在住
アテネフランセ&NHKラジオのフランス語講師
|
|
|
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載“復刻版”
掲載記事:平成2年1月20日発行本誌No.19 号名「梧(あおぎり)」
|
|
|
♪ もういくつ寝ると、お正月……。お正月を海外で迎える人が年々増えているそうですね。でも私の場合、ほんの数時間でも日本の外へ出るとなると、あらかじめ出入国管理事務所に出頭して再入国許可をもらっておかなければなりません。それについてはいくらかの手数料も払わなければならないし……。
こんな煩わしいことを避けるためにも私は、断然〝国内居残り派″、ディスカバージャパンに徹底するつもりです。
こういうとなんだか根っからの国内旅行好きみたいに聞こえますが、じつは、つい最近まで日本の地方には見るべきものはないと思っていたのです。
宗旨替えの理由は後回しにして、まず、なぜそんな偏見を持ったのかをお話します。
日本人の“温「楽」旅行”
来日当初は、ご多分にもれず私は北海道から南は沖縄まで電車や車や自動車であちこちを回ってみました。しかし、地方ごとに町並がガラリと変わるフランスに比べて、日本の街は何処も同じで、個性を捨てて東京の亜流になろうとしているように見えたのです。田園風景も、さほど変化に富んでいるという印象を受けませんでした。しばらくするうちに日本の地方に対する興味を失ってしまったのです。
また、日本人と日本文化を知るには「温泉へ行って、いわゆる“裸の付き合い”をするのが一番だ」とあちこちからすすめられたので、それも試してみました。
しかし、私は運が悪いのか、あまりいい思い出がありません。温泉が気持ちいいのは、外国人・日本人を問わずだれでもが認めるところです。ただ困るのは〝宿″です。ゆったりとした部屋で行き届いたサービスを期待するのなら、よほど奮発しなければなりませんし、並の所ではどんな目に遭わされるかわかりません。
早朝、鬼軍曹のような女中さんに布団から追いたてられたこともありました。フランスとは違って一泊二食付とは有難いと思っていたら大広間に全員集合で食べさせられ、それも時間厳守で、ちょっと遅れて行ったらおみおつけが冷たくなっていたなんてこともありました。
女性だから本国で免れた兵役を、遊びに行った日本の温泉で味あわされてはかないません。それに、薄い壁を通して隣近所のどんちゃん騒ぎが聞こえてきたのでは、日本人のように騒音のなかで眠る才能のない私は、まんじりともできませんでした。
むかし知人が温泉へ行ったというので「景色はいかがでしたか」と尋ねたところ、答えに詰まったので、びっくりしました。みんなそうだとは言いません。しかし、殆どの湯治客が湯舟と部屋の往復に終始するのをみて納得がいきました。こういう〝温「楽」旅行〟の行動パターンを海外旅行の時もするのでしょうか。
バリやフィリッピンに行ったのに豪華なホテルの内装しか思い出せないという人が若者を含めてたくさんいるらしいのですが……。
山間の温泉場で知る日本文化
それはさておき、今年の夏、これまでの国内旅行の失望を帳消しにするような経験をしました。
旅行先は、新潟と長野の県境にある街道からはずれた山間の小さな温泉場です。そこは銭湯のような形式になっていて、疲れを癒しにやってくるのは、殆どがその町の人と近隣の村々の人たちでした。その土地を一度も離れたことのないようなおばあちゃんたちが、孫を連れて陽の高いうちから湯につかり、土地の噂話をしている様子は、気取らない家庭的な雰囲気にあふれていました。
宿は、しゃれた母屋と独立した引き戸の棟からなっていて、私はその別棟の一つで、風にそよぐ木々の音を子守歌に快適な一夜を過ごしました。この宿は例の〝ふるさと創生″の一億円で建てたとか。都会の住民にはただの無駄使いに思えた「ふるさと創生」も案外いいものだな、と見直したしだいです。
運のいいことに、翌日はそこのお祭りでした。私は土地の人たちのお宅に招ばれ、ふき枝豆・ウリなどの取り立ての山菜や無農薬野菜をはじめ、フランスにはない岩魚(いわな)や鮎といった川魚をふんだんに使ったお祭り料理をごちそうになりました。そして、浴衣姿の老若男女に混じって、私も山の上の神社にお参りしてきました。
|
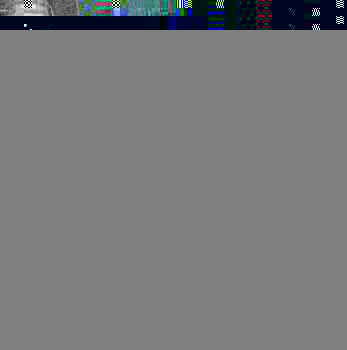
宿の近くの民家にお呼ばれご機嫌のアルメルさん |
|
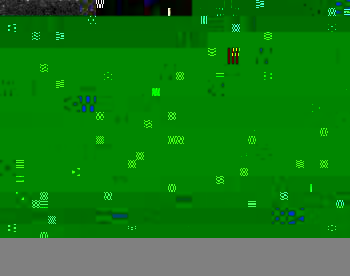
浴衣姿で子供たちと夏祭りを楽しむアルメルさん
|
|
日本人の行動のナゾは地方に
ここで私は、日本を再発見したのです。人々の顔にほのぼのとした穏やかさを見、森深い山と急流、そして抜けるような青空に天と地と水が調和した日本の自然の美しさを感じ、こんもりした森に囲まれた神社に創造主の存在を思い、祈る気持ちと、静けさや、木々の美しさ、景色の美しさ、生命の美しさに感謝する気持ちがわきあがるのを禁じ得なかったのです。
この夏の体験から、私は日本にはまだまだ発見しなければならないものがたくさんあることを悟りました。また、東京は近代的な日本の一面に過ぎないこともわかりました。
去年フランスへ帰ってパリと地方の違いを感じましたが、東京と地方の違いはそれと比較にならないほど大きなものであったのです。
都心から100キロ離れただけでもそこはもう別の日本なのです。
最先端をゆく東京人がしばしば見せる先進とかけ離れた行動のナゾは今でも私を悩ませていますが、もっと頻繁に田舎を訪ねてみることによって、そのナゾを解けるのではないかと思い始めています。
ずっと田舎に暮らすとなれば、それはそれでいろいろな問題もあるかもしれません。ただ私が確信を持って言えるのは、自分の背負っているフランス文化と自分を取り囲んでいる日本文化との軋轢(あつれき)に疲れたとき、田舎へ行ってみると、これからも日本を愛し続けていこうという気持ちを掻き立てられるということです。
|
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|