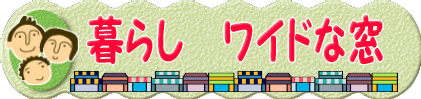 |
| 編集:岩田忠利 / 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |
| NO.306 2014.10.18 掲載 |
|
|
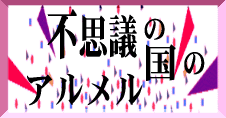 |
  |
筆者:アルメル・マンジュノ
フランス人(女性)・港北区日吉在住
アテネフランセ&NHKラジオのフランス語講師
6月12日付け、里帰りしたアルメルさんからのお便り。
「皆さんお元気ですか。里帰りしてからもう2カ月。私はいま北へ南へと飛びまわり、祖国を旅する喜びに浸っています。母の家では過ごす時には、近くを自転車で回ります」
|
|
|
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載“復刻版”
掲載記事:昭和63年8月15発行本誌No.43 号名「枇(びわ)」
|
|
|
里帰りしてみると、フランスは大統領選挙の真最中。テレビ・ラジオの話すことが全部わかるわ、などと当たり前のことに感激しながら選挙関連の報道を大いに楽しみました。で今回は、政治……じゃなくてマスコミを取り上げてみたいと思います。
この分野はつねに私の関心の的。私自身、その中に何年か身を置いたこともありますし、日本語を覚えられたのもひとつにはマスコミのおかげでした。
フランス人の私が言うのも変ですが、こちらのマスコミを見ていて、フランス人とはこんな国民だったのか、と教えられることが多くありました。
|
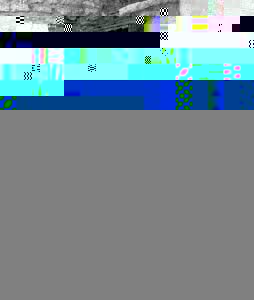
フランスへ里帰りして2カ月のアルメルさん、少しふくよかになったみたい… |
|
昼間はラジオ。ホンネで話す出演者
最近ようやくフランスでも朝からテレビを放送するようになりましたが、やはり朝、人々が目を覚まして付けるのはラジオです。シャワー・髭剃り・化粧と、とかく朝はすごす時間の多いバスルームには、どこの家庭でもラジオが置きっぱなしになっています。ニュースは新聞記事や前夜行なわれたテレビの政治討論に関する論評が大部分です。日本では考えられないことでしょう。
ニュースの後は、午前中ずっと男女数人の進行役が番組を進めていきますが、みんなが一時にしゃべろうとするので、その賑やかなこと! その間にはグルメの国フランスらしく料理の紹介や聴取者に電話で冗談をいうコーナーや政治風刺好きな国民性を反映した政治家の物真似などが入ります。
また、有名なジャーナリストや社会学者・心理学者などがマイクの前にやって来て、時事問題に対するそれぞれの見解を述べるコーナーもあります。あまりにもあけすけに本音を言うので、私はいつもびっくりします。
こちらでは玉虫色の発言は歓迎されず、必要とあらば挑発的になることもいといません。「この人は思っていることをハッキリ言うからいいわね」と母が言うのを聞いて、私もFM東京の『けさの提言』の出演者の中でひいきにしていたのは、塩田丸男さんや樋口恵子さんのようなズバリ本音を言う人だったのを思い出しました。やっぱり私もフランス人か!
夜はテレビ。人気ある討論番組と司会者
反対に夜、人々が世の中の動きを知ろうと付けるのはテレビです。事件報道やルポは短く、出来事に対するゲストたちの討論に多くの時間をさいています。大抵、活発な議論になるようです。話術に特権を与えている国があるとすれば、それはフランスでしょう。
夕食のあと、日本の皆さんがプロ野球番組で落合・桑田の対決に手に汗を握るのと同様、フランス人はゲストたちの丁々発止のやりとりに固唾をのんでいるのです。選挙期間中ということもあって、いやがうえにも熱が入ります。日本では見られないような激しさと鋭い切り返しで自説をぶつけあうゲスト。それを向こうに回して少しも慌てず番組を進める司会者には、私も舌を巻きました。
とくに女性司会者の見事な行司ぶりとジャーナリストとしての高い見識が印象に残っています。「はい」とか「そうですね」しか言わない日本の女性アナがフランス人の目に消極的と映るのも、むべなるかなという感じです。ただし、若さと美貌については日本のほうに軍配があがりそうです。ともかく、連日芝居を見ているような気分でした。
|
|
|
それに、ゴールデンタイムには、蛙のミッテランと禿げ頭のシラクという二人の大統領候補が登場して駄洒落をとばす人形劇まで放送していたので尚更です。おなかの皮がよじれるほど大笑いしました。
国営・民放を問わず、番組の基調に流れる底抜けの明るさ、留守中のフランスの変化を感じます。言葉遣いや服装にも堅苦しさがありません。天気予報でさえユーモアを忘れないようにしているのです。
討論が終わったところで次は何を見ようかなとテレビ番組雑誌に手をのばすのは、こちらも日本と同じ、ただし、面白そうなものがなければ消してしまいます。一般的に選択嗜好が強いので、日本のようにテレビを付けっ放しにしておくことはなく、見るか見ないか、はっきりしています。
ビデオはこちらでも大変普及していますが、レンタルのソフトを利用することよりも録画しておいたテレビ番組を見るのが主流です。仕事を早く終えて夫婦で友人を訪ねたり、あるいは友人夫婦を招いたりする機会が多く、そうした時にテレビを付けっ放しにしておくのは大変失札なこととされているのがその一因でしょう。日本では、みんなでテレビを見ることで親睦感が高まるようですが……。
子供番組は皆無。俳優・歌手らも出演せず
「変ねえ、夜はドラマをやってくれないの」と妹に訊いてみたところ、言下に「なくてけっこう。昼間はドラマだらけなんだから」と言われてしまいました。試しに4月19日の番組欄を見ると、第1チャンネルでは6本、そのうち5本がアメリカ制作ものでした。どうやらフランス人はドラマをあまり好まず、自分たちで作るよりも輸入物で間に合わせているようです。
そんなわけで、日本にいる時はよくドラマを見ていた、と言い出せなくなってしまいました。センチで憂愁に満ちたドラマというのは日本人の心を反映していたんですね。改めてそう感じました。
フランスでは映画俳優がテレビの仕事をすることは殆どありません。それに、CMにも全くと言うほど登場しません。歌手、スポーツ選手も同様です。
手軽に金儲けに手を染めた、と大衆から反発を買うのを恐れているのです。反対に、先ほど紹介した討論会に彼らを参加させるのは、ごく普通に行なわれています。彼らが自らの政治的立場を言明することに違和感はありません。ちなみに選挙期間中のアラン・ドロンは右翼支持、歌手のジュリエット・グレコ、作家のフランソワーズ・サガン、デザイナーのジャンボール・ゴルチィエらは左翼支持でした。
討論のあとには劇映画やクイズ番組が続きますが、いずれも大人向けのものばかり。
昼夜、週末の別を問わず、日本に比べてフランスのテレビでは子供たちが忘れられています。画面の隅に白い正方形が出る子供に見せないほうがいい番組などというのがある一方、漫画は殆どありません。
このようにフランスのマスメディアは、報道も娯楽も大人に照準を合わせているのです。
その代わり、飢餓に苦しむ第三世界に関する番組はたくさんあり、援助を願う現地の医師などに視聴者から多くの寄付が送られているようです。
テレビは世界の国々の懸け橋にもなる。フランス人は、そう考えているのです。
イラスト:高橋正幸(大倉山)
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|