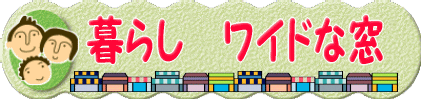 |
| 編集:岩田忠利 / 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |
|
NO.294 2014.10.14 掲載
|
|
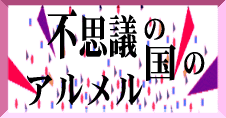 |
 |
筆者:アルメル・マンジュノ
フランス人(女性)・港北区日吉在住
アテネフランセ&NHKラジオのフランス語講師
|
|
|
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”
掲載記事:昭和61年2月20日発行本誌No.32 号名「樫」
|
|
|
私が初めて日本にやって来たのは、ちょうど今みたいに冬の終わりで、街は色彩に欠けていました。そのせいか、一番強い印象を受けたのは、公衆電話の鮮やかさでした。あの赤、青、黄、緑の電話機は、ほんとうにフランスのものより目を引きます。
そして、何の仕切りもなく、ただ台の上に置かれただけの電話機が人通りの多い駅頭にずらりと並び、その前で、人々が周囲のガヤガヤいう音も気にせず、ほほ笑んだり、見えない相手にお辞儀をしたりしている様子に、驚嘆したものでした。
次々と壊されるフランスの公衆電話
日本では、受話機を取り、硬貨を入れ、ダイヤルを回せばすぐ相手が出る、というのがごく当り前になっているようですね。外国では、こんなことさえスムーズにいかないことがあるなんて考えたことありますか。
先日、ちょうど器物破壊現象の被害を受けるフランスの公衆電話についてのレポートをテレビで見ました。これはかなり深刻で、特にパリ一帯では、まともに使える電話がまれにしかないというほどです。電話局の話によると、壊された電話機15台を修理したところ、翌日にはもう12台が壊されていた、なんていうこともあったそうです。もちちん、利用者に故障を知らせる貼り紙などなく、お金を損する人がたくさんいます。
その修理にかかる費用は、84年度を例にとると、なんと3億2千万フラン(約83億円)! すごい額です。社会学者たちは、今こうした現象を真剣に研究し始めましたが、具体的解決策はまだ示してくれません。
フランス郵政省が、過去10年間、公衆電話をより多く設置するように努力してきただけに本当に残念です。フランスの公衆電話は、国民の個人主義を反映して、たいていはボックスになっていてシャレているのに、あれを壊しちゃうなんて……。
日本の電話局の行き届いたサービス
聞くところによると、日本でも壊される電話機はあるけれども、すぐに修理されてしまうので、利用者が気づく間がないとか…。ともかく、日本の電話局の迅速で行き届いたサービスには、たいていの外国人がびっくりします。たとえば、引越しの時など、新居に移ってすぐ(時には引っ越しの最中)電話機を設置してもらえるとか……。
そのうえ、国内の電話システムが非常に発達していて、日常の利用に支障がでるなんてことがほとんどありませんね。フランスでよくみるみたいに、「ただいま回線が非常に混雑しておりますので、お客様の通話をおつなぎできません。しばらくしてからもう一度おかけください」なんて言われたことありますか。私は、日本に来てからまだ一度もありません。
日本人は電話が大好き
次に利用の仕方ですが、日本人は些細なことで、しじゅう電話をかけているのではありませんか。テレビドラマなどを見ていると、そう感じます。なにしろ、隣の家の人にまで電話するんですからね。ちょっとこんなことフランス人には考えられません。私自身、マンションの管理人さんから電話がきた時には、本当にびっくりしたのを今でも覚えています。なんでも、そのほうが着替えたり、わずかにせよ足を運んだりする手間が省けるからですって?!
それから、あと5分とか10分とかで帰る、なんてよく駅から電話していますね。これも、フランス人はめったにやりません。「これから帰るよ、ガチャン」だけのために電話機の前に列を作って待つなんて!
じつは、私もこの習慣が身についていて、フランスに里帰りしている時にやってしまいました。すると電話口に出た母は、ブスッとして「あんた、それだけで電話してきたの」ですって。ワタクシは、もう二度とすまいと心に誓ったのでアリマス!
そうかと思うと、反対にいつ終わるとも知れないほどの長電話。でも、友人とのコンタクトを保つためには、それもしかたがないと思います。パリなら、市内に住む友人を夜や週末に不意に訪ねてみることもできますが、巨大な東京では、その中を移動するだけで時間がかかるし、くたびれるし、おまけに人はみんな忙しくて時間がないので、そうもいきません。そこで、比較的割安ということもあって、電話を使うことになるのでしょう。
街じゅういたる所に公衆電話が設置され、赤貧学生のアパートを除けば、どこの家にも電話があるといった現状を見ると、つくづく日本はコミュニケーションの国だなと思わずにはいられません。
ちょっと意外だったのはフランスほどテレホンカードが普及していないのと、フランスとちがって日本の郵便局には公衆電話がたくさん置いてないことでしょうか。
|
|
|
電話セールスにうんざり
日本では小さな子供までが使い方を知っているほど電話が日常生活に入りこんでいながら、間違い電話やいたずら電話を別にすると、電話に私生活を邪魔され迷惑しているという人に全然出会わないのを、私は不思議に思っています。
これは、フランスでよく耳にする非難ですし、日本にいるフランス人で、静けさを守りたいから電話は引かないという人が何人もいます。
私の家には、仕事上必要なので電話はありますが、じつを言うと、夕方の6時頃までは鳴ってもめったに出ません。人の都合などお構いなしにかかってくる、マンションや車や墓所の電話セールスには、もうウンザリです。
日本の主婦のみなさんは、電話であれ買え、これ買えって言われるのを普通のことと思っているのかしら。私は子供じゃないんだから、買いたいものがあれば自分で行ってちゃんと選べます。
電話網は、人々の心をつなぐコミュニケーションの道具だけれど、あまり商業主義の道具として使い過ぎないようにしていただきたいと思います。
イラスト:石橋富士子(イラストレーター・横浜)
|
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|