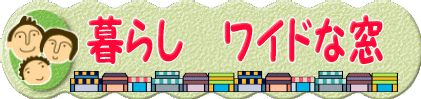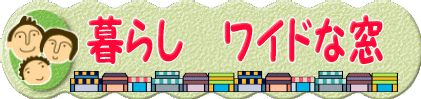 |
| �ҏW�F��c�����@/�@�ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |
| �m�n.289�@2014.10.13�@�@�f�ځ@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@
|
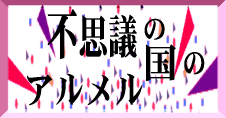 |
 |
�@�@�M�ҁF�A�������E�}���W���m�@����
�@�@�t�����X�l(�����j�E�`�k����g�ݏZ
�@�@�A�e�l�t�����Z��NHK���W�I�̃t�����X��u�t
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�T�����@�����̗U�f
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
|
|
�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a60�N�S���P�����s�{���m��.27�@�����u���i�������j�v
�@�@�@ |
|
|
�@�O��͓d�Ԃ̒��̍L������b���n�߂��̂ŁA����͑��̊O�Ɍ�����L������c�c�B�@ �a�J���o�č��ؒ��ɒ����܂ŁA�ǂ��̉w�ł����̎��ӂɂ́A�T�����Z�Z�Ƃ����[���~�~�Ƃ��������Ŕ��ї����Ă��܂��B���������A����Ȃɂ�������i�j������A�Ƃт����肵�Ă��܂������A���Ƃ���l�ɋ����Ă�����āA�����Ƃт����肵�܂����B
�@�@�@�@�@�@19���I�ɏ��ł���������
�@�@�t�����X�ł́A���{�l�͐T�d�ŗp�S�[���A�������A�����̂悤�ɁA�ꂵ�����ɔ����Ē����ɗ��ł���A�ƕ]���Ȃ̂ł��B�����g�A���{�̃T�����[�}���́A30�̐l�ŏ��Ȃ��Ƃ�20�J�����̋����Ɠ��z�̒����������Ă���A�ƃt�����X�̎G�����V���œǂL��������܂��B����Ŗ{���ɃT�����̂��q����Ȃ�Ă���̂�����c�c�B
�@�����݂̓t�����X�ɂ����܂����B18���I��19���I�Ɂc�c�B�u���f�����G�v�ƌĂ���m�炸�̔ނ�́A�����̕��w��i�A���Ƀo���U�b�N�̂��̂Ȃǂɂ����Γo�ꂵ�Ă��܂��B���q�̕��͂Ƃ����A�n����a�l����ŁA���X�̃p�����҂̕����̂��߂Ɏ؋������܂����B�܂�ɁA���łő�����������ljƂ̃h�����q�Ȃǂ��q�ɂȂ�܂����B
�@�ł�����̘͐̂b�B���܂ł͂���ȐE�Ƃ͂���܂���B1985�N�̃t�����X�l�̑����́A�������f�����G�Ƃ������t�����m��Ȃ��͂��ł��B����̃t�����X�l����������悤�Ǝv���A�܂��������s�֍s���܂��B
�@�t�����X�̋�s�́A���{�ƈ���Ă�����a���Ă����q��t���Ă͂���܂��i���q���t���͕̂ʂ̋��Z�@�ցj�A���Ȃ�ȒP�ɂ�����݂��Ă���܂��B������Ó��ȗ��q�ŁB
�@�����炭�A�t�����X�l�͋�s�������T�[�r�X�@�ւƌ��Ȃ��Ă���̂ł��傤�B���������킯�ł�����A�������f�����G�͑��݂����Ȃ��̂ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@���ʂ̐l���T�����n����
�@���̎���ɂ��Q��Ȃ̂��߂Ɏ؋��Ŏ��Ȃ��Ȃ�A��s����T�[�r�X�̒����ۂ����l�͂��܂��B����́A�Ƃ�킯�M�����u���[�̏ꍇ�ŁA���̍�ƃt�����\���[�Y�E�T�K���Ȃǂ��T�^�I�ȗ�ł��B�ł�����́A�ς��҂̃X�^�[����������̂悤�ɁA���Ƃ��ƘQ��邾���̂��̂������Ă���l�ɂ����N����Ȃ����́A�ƃt�����X�ł͑��ꂪ���܂��Ă��܂��B
�@�Ƃ��낪���{�ł́A�݂Ȃ���̂悤�ɕ��ʂ̐l������Ȏ؋�������A�o�ϓI�j�ŏ�ԂɊׂ��Ă���ꍇ�������̂ɂ́A�т����肳�����܂��B�������A�S���̂��炵�Ȃ����炻���Ȃ����ꕔ�̐l��ʂɂ���ƁA�����Ă��܂��߂ŁA�ߏ���E��̕]���������l�Ȃ̂ł��B�����ĐV�����J���ƁA���������l�������؋�����Ɉ�ƐS�����͂���Ƃ����L�����o�Ă����肷��̂ł��B�t�����X�̐V���ł́A����ɗނ���L�����������Ƃ�����܂���B
�@���{�ł́A���E�����ʂȈӖ��������Ă��邱�Ƃ͎����悭�킩���Ă��܂��B�t�����X�̎��E�Ɣ�ׂĂ݂�̂͋����[�����Ƃł����A����̃e�[�}����͊O���̂ł�߂Ă����܂��傤�B
�@�Ƃ������A�t�����X�l���炷��ƁA�ǂ����āA�����������̂��ƂŎ��ȂȂ���Ȃ�Ȃ��낤�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�������A�t�����X�l�͓��{�̃T�����̋�������藧�Ă�m��܂��c�c�c�B
�@ |
|
�@�@�@�g�����A������h���Ȃ��H
�@���l�Ƃ��ẮA�ߌ��I���������A���̌����ɋ���������܂��B�f�p�ȋ^��ł����A���������ǂ����Ĕނ�̓T�������炨�������K�v���������̂ł��傤�B�V����ǂ�ł���A���ꂪ�ǂ�Ȍ��ʂ��������悭�킩���Ă����͂��ł��B
�@�ǂ������{�l�ɂ́A�����̌��E�Ƃ������̂�S�����A�u���ׂĂ��X�O�Ɂc�c�B�c�c�łȂ���C���v�Ƃ����Ƃ��낪����݂����ł��B����̓N���W�b�g�ɑ�\�������ɔ��B�����M�p���x�̂������ŁA�N�����e�Ղɉ��ł���ɓ������Ƃ������ƂƁA�K�v�̂Ȃ����̂܂Ŕ�������������CM�̍^���ɂ���Ĉ�܂�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������w�i������̂ŁA�T�����ɂ܂Ŏ���o���Ă��܂��̂��Ǝ��͍l���܂��B
�@�������Ă݂�ƁA���{�l�͇������A�����Ƃ����]���Ƃ͗����ɁA���ۋC�ȃL���M���X�V�Ǝv���Ă���t�����X�l���ȏ�Ɋy�V�Ƃ��ƌ��������Ȃ��Ă��܂��B
�@�@�@�ɉh�������炵�����e
�@�t�����X�ł��N���W�b�g�̐��x�͔��B���Ă��܂����A���̒m�����A���{�̃T�����̂悤�Ȗ��ɔ��W����悤���͂���܂���B�t�����X�ł́A�܂��K���ӎ����������c���Ă���̂ł��BOL�≺�������́A�����Ď����̐������u���W�����̂���Ƌ������ȂǂƂ͎v���܂���B�����Ȃ����͔̂���Ȃ��̂ł��B�e�l�������̉���ɉ����āA�������Ȑ��������Ă���̂ł��B
�@���ǃT�����́A���{�̋}���Ȍo�ϔ��W�ɂ���Ă����炳�ꂽ�����̂ЂƂ̂悤�Ɏv���܂��B�݂�Ȃ��ɉh�̉��b�����邱�Ƃ�]����ǁA�e�l�̂��������\�͂��������Ȃ��������Ƃ��A�ߌ��̎n�܂�ł��傤�B
�@�����̊O���l�W���[�i���X�g�́A�T���������݂āA���{�l�͑c�悩��p�������l���������A������`�҂ɂȂ����̂��ƌ��_�������Ă��܂����A���͂����܂Ō�������͂���܂���B�@�����̍��z�̌����ƌ��e�̋�ʂ��ł��Ȃ����z�Ƃ����邯��ǁA�T�����Ƃ��̈����̗U�f�����Ȃ���A����������n�ɑ���������炵�������Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���X�g�F���x�m�q�i�C���X�g���[�^�[�E���l�j
|
|
|
|
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���y�[�W�� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|
|