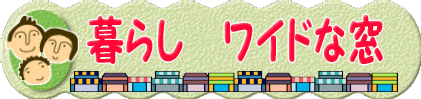 |
| �ҏW�F��c�����@/�@�ҏW�x���F�������G�@/�@���S�F�z�����q |
| �m�n.287�@2014.10.12�@�@�f�ځ@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@���摜�̓N���b�N���g�債�Ă������������B
|
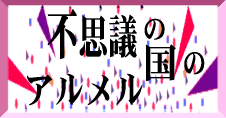 |
 |
�@�@�M�ҁF�A�������E�}���W���m
�@�@�t�����X�l(�����j�E�`�k����g�ݏZ
�@�@�A�e�l�t�����Z��NHK���W�I�̃t�����X��u�t
�@���e�͐����̃t�����X�l�̔ޏ������e�p���ɓ��{��ł������ߖ������ؑO�ɕK���ҏW���ɓ͂������̂ł��B
|
|
�@�@�@�@�����y�����\�\����Љ������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
|
|
�@�@�����Z���Q���̃R�~���j�e�B�[���w�Ƃ��悱�����x�B�D�]�A�ڂ́g�����Łh
�@�@�@�f�ڋL���F���a59�N12���P�����s�{���m��.25�@�����u�I�v
�@�@�@ |
|
|
�@������Ƒ��ڂ̑�|�������Ă���ƁA�ǂ��ւ������̂��Ǝv���Ă������|�A�g���G�̃����o�[�J�[�h���A�Ђ������o�Ă��܂����B����Ƃ�������������B
�@���āA�܂���N�X�V���悤���Ȃ��c�c�B�ł��䂪�Ƃ��s�v�������A�ɂ��Ȃ��Ă͍s���Ȃ����Ƃ��������ǁc�c�B
�@�@�@���|�A�g���G�̔M�C
�@���{�|�p�ɔM�����Ă����F�l�ɘA����āA�㊯�R�ɂ��铩�|�A�g���G�ɏ��߂čs�����̂͂U�N�O�ł����B�s��p�Ȏ����A����S�y��痿�ʼn���A���K���ɂ��Ȃ�����A�t�����X��ɂ͖����������臁�ɂȂ����肵�Ȃ���������Ă����̂́A�n���̊�т̂ق��ɁA�A�g���G�̔M�C������A�܂��a�C���������Ƃ������͋C���C�ɓ���������ł��B
�@����́A��҂�q��Ă̏I������n�N�w�l���͂��߁A������N��w�ɂ킽���Ă��܂����A���ɂ��N���̐l�������������Ă��邱�ƂɁA���͂�����������Ă��܂��B
|
|
�@�����܂��V����̍��A�Ȃ��Ȃ����܂��䂩���ɋ�J���Ă���ƁA�ЂƂ�̂�����������������|���Ă���܂����B
�u�ŏ��͓���ł���B�ł��ˁA���̂悤�ɒ�N�ɂȂ��Ă݂�ƁA�Ⴂ�����ɉ�������n�߂Ă����ėǂ������Ǝv���悤�ɂȂ�܂���B���ł͂��ꂪ���̎�ŁA���̂������ł����Ⴍ������悤�ȋC�����Ă����ł���v
�@���̎��͂����Ȃ�ƂȂ��ނ̌��t���Ă��������ł����B������Ȃ�ł��A�B���̐g�ɂȂ�̂͂܂��܂���̂��Ƃł�����c�c�B�������A���W�I��e���r�ō���Љ�b��ɂȂ�Ȃ�قǁA���̂����������͉�����Ȃ��Ƃ������Ă��ꂽ�悤�Ɏv���Ă��܂����B
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�ߐH����Ă��g�e��S�~�h
�@���{�ł͑��̍������A�}�X�R�~���l���\���̘V����ۂ��A�Љ�̎�̉��������Ѝ��ƂƂ炦��X���������悤�Ɏv���܂��B�܂��e�l�́A�����Ȃ������̕����I���������̒ቺ��傢�ɐS�z���Ă���悤�ł��B���̕���ł̓��{���{�̑Ή����݂�A���������X���ɂ����Ȃ����܂��B�N�����x����{������Ă��Ȃ�������A��N�ƔN���J�n�̊Ԃɋ̔N��������Ȃ�Ă��ƁA�t�����X�l�ɂ͑S���M�����܂���B
�@�������A��ɑO�ʂɏo�Ă���o�ϓI��肪�A�����ЂƂ̏d�v�Ȗ����B���Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂�A�����̎��ɂ��Ă̖��ł��B�V��̎��R�Ȏ��ԂɁA��������������������̂ł��傤�B���{�l�̓A�C�X�����h�l���Đ��E�꒷���ɂȂ����̂ŁA�ސE�҂Ƃ����J�e�S���[�ɓ�����Ă���A���Ȃ��Ƃ�20�`25�N���߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@�Љ�_�k�i�K�̎��ɂ͖�肪����܂���ł����B��������̈��ނ͂���قǓˑR����ė�����̂ł͂���܂���ł������A�Ƃ̎G�p�Ȃǂ�����@����X���������̂ł��B
�@�������A��������Ȏ���ł͂���܂���B��ʉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ���������܂��A���ɒj���͑ސE�����ɂȂ��Ȃ��K���ł����A�Ƃ̒��şB�ɓ����ꂽ�N�}�̂悤�Ƀu���u�����āA�����܂��]�����Ă���悤�ł��B���͂��́g�e��S�~�h�Ƃ����\���͕��߂����Ǝv���܂��B
�@�@�@�t�����X�̔����͘V�l��w��
�@���N�t�����X�ɋA�������A�����̈�l�Ɠ��{�ɂ��Ęb���@�����܂����B�ނ����{�̂��Ƃ����낢��m���Ă���̂ɂт����肵�āA���������ǂ��ł���Ȓm�����̂��q�˂�ƁA�����́A
�@�u���͑ސE�̐g������A�V�l��w�i���������w�łقƂ�ǖ����j�ɍs�����Ƃɂ�����B���N�̍u�`�̒��ɂ͓��{�̂��Ƃ������Ăˁc�c�v
�@�Ɠ����܂����B�����́A�A�g���G�̂����������Ɠ����悤�ɁA���������Ɖ������������Ă���悤�Ɏ��ɂ͌����܂����B
�@���{�ɂ͂��������^�C�v�̑�w�͖����Ƃ��Ă��A���鏊�ɃJ���`���[�Z���^�[�ƌĂ����̂��Ԑ���ł��B�����A�I�݂ɃJ���t���[�W�����ꂽ�c���������Ɣ��ꂽ��A���ɂł����J���`���[����t���ăn�N��t���悤�Ƃ�������ɂ͋�������邱�Ƃ�����܂����A���ł͂���ł���������Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�@�����g���������ꏊ�ŋ����Ă݂āA�������ЂƂ̏o��̏�ɂȂ��Ă��āA������N��̎Q���҂̊Ԃɐe�r�����܂�Ă��邱�ƂɋC�����܂����B�܂�����̐l�́A���ł���Ԃ������낭�A�܂��ΕׂȊw���ŁA�݂�Ȃ��犽�}����Ă��܂��B |
|
|
|
�@���|�����A�J���`���[�Z���^�[�A���邢�́w�Ƃ��悱�����x�ҏW���̂悤�Ȓn��ɍ������������c�c�A�{���̂Ƃ��뉽�ł������̂ł��B���ǂ������Ȃ̂́A�l�����Ō�܂Ő����鉿�l������̂ɂ���Ƃ������Ƃł��B
�@���Ƃ��ẮA�l���\���̘V��͊�{�I�Ƀ}�C�i�X�ł���Ƃ́A�m�M�������Č����܂���B�o�ϖʂ������Ƃ炦��A�s�s���Ȃ��Ƃ������ł��傤�B�������A�e�l�̐l���߂�Ƃ��A���ތ�̐l���͍ł���M�������Đ�����Ƃ����Ǝv���܂��B�������A�\�ߏ��������Ă����Ƃ��������͂���܂����c�c�B
|
�@�@�@�@�@�@���l����V��̂��߂�
�@���́A�܂��A�g���G�̉�����i���X�V���邱�Ƃɂ��܂����B���N�͂Ȃ�ׂ����Ԃ��݂��ċx�܂Ȃ��悤�ɂ���Ɠ����ɁA�����ق��̂��̂Ɏ���o���Ă݂悤���Ǝv���Ă��܂��B
�@������ƃi�C�[�u�ȍl������������܂��A�Ⴂ���̓��X���V���Ă���̓��X�������Â���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă��܂��B���ɒ������������Ƃ͎v���܂��A�����N���ɂȂ�̂ł�����A���ɔN���ɂȂ肽���Ǝv���܂��B
�@���āA�݂Ȃ���ɂƂ��ĐV�����N�ɁA�����Ȃ����܂����H
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���X�g�F���x�m�q�i�C���X�g���[�^�[�E���l�j
�@ |
|
|
|
|
|
 |
�u�Ƃ��悱�����v�s�n�o�ɖ߂� |
 |
���y�[�W�� |
 |
�u�ڎ��v�ɖ߂� |
|
|
|
|