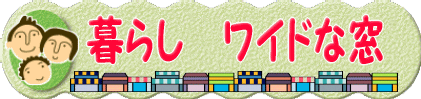 |
| 編集:岩田忠利 / 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |
| NO.286 2014.10.12 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
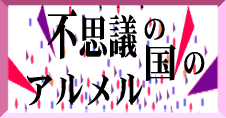 |
 |
筆者:アルメル・マンジュノ
フランス人(女性)・港北区日吉在住
アテネフランセ&NHKラジオのフランス語講師
原稿は生粋のフランス人の彼女が原稿用紙に日本語でしたため締切前に必ず編集室に届けたものです。
|
|
|
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”
掲載記事:昭和59年10月1日発行本誌No.24 号名「椎(しい)」
|
|
|
今回からは、私が見たり聞いたり読んだりしたことについての、自分なりの感想や意見を書いてみたいと思います。
まず第1回目の今回は、日本とフランスで行われている世論調査の結果から……。
意外な結果に私もビックリしました。
意外な調査結果
日本に親しみを感じているフランス人は49%。一方、フランスに親しみを感じている日本人は23%。感じていない人は59%も……。
自分の親の老後の世話をするのは当然であると考えているフランス人は92%なのに、日本人は54%……。
出世したいと思っているフランス人は77%もいるのに、日本人はたったの14%……。
これは、今年の3月、日仏両国の代表的な新聞、朝日新聞とル・モンドが共同で行った世論調査の結果です。私は非常に驚き、なぜこのような結果が出たのか私なりに探ってみたくなりました。
“親しみ”が意味するもの
まず両国民間の親近感について――。日本人の半数以上がフランスに親しみを感じていないなんて、日本で暮らす私には到底信じられません。フランスが日本でかなりの魅力を発揮していると感じさせられるのは日常茶飯事なのですから。
なぜかしらと首をひねりながら、両紙を見比べているうちに、質問に使われている言葉に原因があるのではなかと気付きました。
ル・モンド紙は、「親しみ」を「サンパティ」という言葉で表現していますが、この言葉は、ある人に対してなんとなく好意を持ち、機会があれば付き合ってみたいといった程度のかなり曖昧な意味しか持っていません。
一方、日本語の「親しみ」という言葉は、一層強い意味があるように思えます。間違っているかもしれませんが、この言葉には、ある人に惹かれているが、それは自分とその人に何か共通点があるからだというかなり具休的なニューアンスが含まれているのではないでしょうか。このように考えると、別に驚くことは何も無いのです。
実際、不況だというのに年に5週間もバカンスをとったり、些細なことでストをする、不純で個人主義のフランス人に親しみを感じろと言うほうが土台、無理な話なのです。また、日本政府と正反対の政策をとり、対日貿易では保護主義的姿勢をとっているミッテラン社会主義政権の誕生以来、日本人はフランスをますます遠く感じているのではないでしょうか。
|
|
|
“親孝行”なのはどちら?
次の親子関係でも、親孝行で有名な日本人がフランス人に大分遅れをとる予想外の結果が出ています。
私はこれも言葉の問題に原因があると思います。というのは、親の老後の世話をするという「世話」の意味する内容が、日本とフランスではかなり違っているのです。私が説明するまでもなく、日本で親の老後の世話をすると言えば、親と同居して下の世話までもするということです。
一方、フランス人が考えている「世話」というのは、時々両親の家を訪れたり、近況報告の電話をしたり、クリスマスに自宅に招いたり、孫の顔を見るのを楽しみにしている両親に時々子供を預けたりすることなのです。もし親が寝たきり老人になったりボケたりした時は病院に入れます。家に引きとって素人の自分が面倒をみるよりも、プロの手に任せる方が良いとフランス人は考えるのです。
私自身、母には3年に一度しか会えませんが、絶えず手紙を書いていますし、母の誕生日には必ず電話をします。そして、母は私のことを世界一の孝行娘だと思っていてくれると私は信じています。私の方から言えば、遠く離れてはいるけれども、私は母の世話をしていると思っています。
|
|
“立身出世”は訳せない
第三に生き方に関しても、出世を求める日本人が13%に対してフランス人は77%という驚くべき結果が出ています。どうも、日本人から無責任で怠け者と思われているフランス人の方が、エコノミック・アニマルになってしまっているようです。
しかし、この結果も今までと同じ理由や数字をそのまま受けとれないような気がします。
ル・モンド紙のアンケートでは、「出世を求める」が「人生で成功するために努力する」と表現されていたのです。
アルメル、秋のイメージ
リヨンにいた頃、私にとって秋とは、枯葉と風と灰色の空から降る雨でした。
日本に来てからは、もっぱら旅と穏やかな秋晴れを意味するようになりました。そして今では、秋が私の一番好きな季節です。このように、季節の移り変わりのような単純で明確なことさえも、随分異なった感情を生み出させることがある訳です。
日本人とフランス人のような全く異なる文化を背負った者同士が相手の国を知ろうとする時、誤解が生じる可能性は無数にあります。しかし、双方の努力と忍耐があれば、それは乗り越えられることだと思います。
今回、朝日とル・モンドの共同アンケートの結果から、3点ばかり私が疑問に思ったものを取り上げましたが、このアンケートは、他の多くの項目でも今までの既成観念の誤りを正すことに貢献していたことを付け加えておきます。
イラスト:石橋富士子(イラストレーター・横浜)
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|