裕福だった上丸子地区(川崎市中原区)
当時の上丸子(現在の川崎市中原区の上丸子地区)は、現東京側の多摩川園駅付近の亀甲山や浅間神社のある丘陵から湧き出た泉を利用し米作りに最適な土地だった。この水利のほかに上丸子が栄えた理由は多摩川が西方を流れていたので洪水がなく、あっても直撃の被害が少なかったからだ。
その丘には長さ100㍍にも及ぶ大きな前方後円墳の亀甲山古墳がある。これほど豪勢な古墳を築造させた豪族がこの近辺にはいたのであろう。
上丸子の豪族は当時流行となっていた自己の力を誇示するため京の都から寺社を招致したのだった。上丸子にある日枝神社(当時は山王社)がそれで、滋賀県の比叡山延暦寺に近い坂本日枝大社から平安時代前期の大桐4年(809年)に分封されたもの。1477年(文明9年)には戦勝祈願した上杉顕定がその山王社の賽銭を浅草の浅草寺に寄進した記録が残っている。当時の上丸子がいかに裕福だったかがわかる。
|
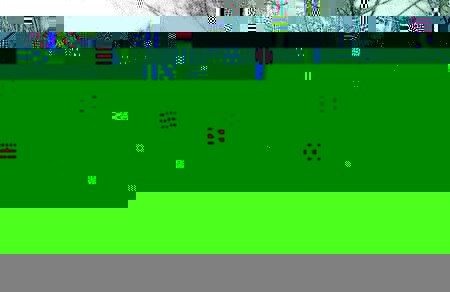
昭和15年2月25日、丸子山王日枝神社社格昇格の儀式
提供:山本五郎さん(同神社宮司) |
|
|
その翌年の文明10年(1478年)、太田道灌が現東京都北区上中里にいた豊島一族を攻めた。敗れた豊島軍は上丸子に逃げてきて、景気のいい上丸子から軍資金、食料、人夫などを集めようとした。しかし、下丸子に陣を敷いた太田軍がいち早く攻め立てたので、2日ともたず豊島軍は小机城(横浜市港北区小机)へと敗走した。
この戦いが多摩川を挟んだ戦いと史書に記載されているが、私は疑問に思う。その理由はこんなことから。
1486年(文明18年)、京都の僧、准后が上丸子を通過し鎌倉に向かう時に書いた『廻国雑記』にこんな和歌を詠んでいる。
東路の まりこ(丸子)の里にゆきかかり 足もやすめず急ぐ暮れかな
この歌のつぎは日吉付近で道に迷って農家に泊まったという記録になり、多摩川に関する記事はない。当時は上記のように西方を流れていた多摩川は川幅広く分流し、徒歩や仮橋で簡単に通過できたので作者の准后には大河としての印象がなかったのだろう。
現在の流れは織田・豊臣の桃山時代からか?
では、いつ多摩川は現在位置になったのか?
小田原衆所有役帳やその検地帳記録から、現在の流れに変わったのは、ほぼ16世紀であると漠然と推定されている。私は次のように考える。
私は1588年(天正16年)の東海地方大洪水の記録があるので、この洪水により山梨県の笠取山に水源のある多摩川の流れが突然、現在位置に変わったと……。
その根拠は、その翌年、当時の上丸子村の名主・中村五郎兵衛(上丸子天神町の中村椆さんの祖先)が北条氏直に現東京側の沼部村の人と洪水による境界争いの訴状を出しているからだ。名主を武士同様に待遇していた北条氏直は、上丸子側の土地と裁定した書き物が日枝神社に残っている。ちなみに沼部村とは現在の巨人軍野球場に近い田園調布4丁目から田園調布南町、鵜の木近くまで及ぶが、それに対する神奈川県側は上丸子と下沼部が該当する。
上丸子村は太田軍と豊島軍の戦いの戦火で廃墟となり、それから110年間に復興しかけたものの、流れを変えた多摩川の洪水が村を襲った。特に江戸時代には5年に一度の割合で被害を受け、昔の繁栄を取り戻せないまま現代を迎えた。
しかし、昔は一面田んぼや畑だった上丸子地区が再び、21世紀にむけ川崎市の副都心として栄えようとしている。
◇◆◇
史実に基づいてはいますが、この結論には私の独断と偏見もある。こんなことで楽しんでいるのが昨今の私です。
|