|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”
掲載記事:平成8年9月20日発行本誌No.66 号名「榴(ざくろ)」
|
|
|
亀の甲山付近に疎開して
戦時中、戦火を逃れ、生まれ育った神奈川区神奈川からここ港北区新羽町大竹の地に家族揃って疎開してきました。
その時、真っ先に聞かされたのが“亀の甲山”のことでした。広い田んぼを挟んで小高い山が横浜線の小机駅と向かい合い、あたかも亀の甲羅を伏せたような格好をしていることがその名の由来だそうです。
今その名は、鶴見川に架かる橋の名「亀の甲橋」としても残っています。その場所は昭和30年代に山の一部を切り崩し綱島〜小机間を走る東急バスの路線となり、残された山の上には資生堂横浜研究所が建ち、右手眼下には大きなクレーンが数多く動いている新横浜の横浜市国際総合競技場の建設現場。6年後、きっとここでサッカーのワールドカップの試合が開かれ、7万人の大歓声に世界中の目が注がれることでしょう。
|
東横沿線に多い「矢」のつく地名
亀の甲山といえばその昔、太田道灌の小机城攻めのとき、この亀の甲山から鶴見川を挟んで小机城に向けてたくさんの矢が〝矢継ぎ早に″放たれたといいます。
小机城祉のすぐ手前に寄せ手からと城側から雨のようにその矢が落ちたといわれる「矢の根」という地名が残っています。また、「小机はまず手習いの始めにて イロハニホヘト 散りぢりになる」こんな狂歌も土地の古老に聞かされました。
歴史に疎い私ですが、非常に興味深いのが身近な東横沿線にこうした「矢のつく地名」が多いことです。
新羽町の工場地帯の中にも「矢中」という所があり、ここも小机合戦のとき、たくさんの矢が落ちたという話が残っているそうです。そこから200メートルほど離れた新吉田町のバス停貝塚そばの坂倉義章さんの家は屋号を「矢先」と呼び、新羽橋先の太尾堤交差点近くの矢沢酉之助さんの家の屋号は「矢尻」と言うそうです。この2軒の屋号とこの地名を加えると「矢先、矢中、矢尻」で一本の矢となり、それが小机城の手前の「矢の根」へ飛んで行ったのでしょうか。
さらに「矢上」という地名は日吉の旧編集室のあった場所、その名は小学校名や川の名「矢上川」。日吉町の隣町で矢上川が鶴見川へ流れ込んだ合流地点のすこし下流、鶴見区駒岡町には「矢畑」という地点が川岸周辺にあります。その向こう岸が「矢向」で、JR南武線の駅名と鶴見区内の町名。
そこから東へ多摩川を渡ると、その川岸に「矢口」という町名や目蒲線の駅名「矢口渡」が続きます。
こうして小机の矢の根から新羽町の矢中を経て、日吉の矢上〜鶴見区矢向〜大田区矢口までは東南へ矢のように真っ直ぐ。その中間地点の川崎市幸区南加瀬には太田道灌が江戸城の築城を夢見たという伝説がある地「夢見ケ崎」があるのですから、不思議です。
これほど多く、矢のつく地名や屋号が現存している事実やその由来に私は非常に好奇心をかきたてられます。何か関係があるのでしょうか。郷土史に詳しい方、次号でぜひ教えてください。
|
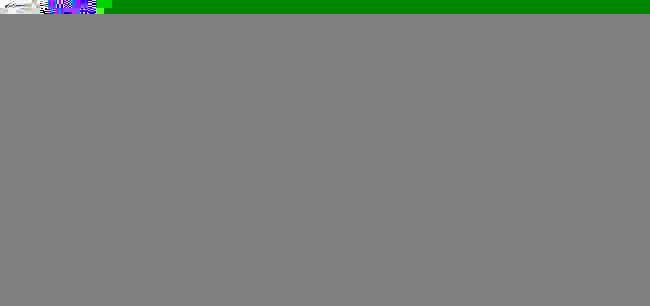
イラスト:石野英夫(元住吉) |
|
|
濁流うずまく鶴見川の氾濫
時ならぬ半鐘のけたたましい音に夢おどろかされました。昭和33年9月28日の夜明け前のことです。
25日朝9時から27日朝9時まで丸3日間降り続いた豪雨(のち、狩野川台風と命名)は「321ミリ横浜気象台開設(明治29年)以来最高」とラジオが告げていました。
その時、雨は止んでいました。突然「サァー」という耳慣れない異様な音……。庭に飛び出すと、まだ薄暗い田んぼのかなたから〝白い一線〟がこちらへ押し迫ってくる。その速いこと……。
「鶴見川の土手が切れたぁ!」警防団員の叫び声で事の重大さを知りました。
濁流は見る見るうちに、小さな土手道を乗り越え、迫ってくる。空が白んだ頃には私の家の前の田んぼは、一面洋々たる湖です。やがて水は道路を越え、何軒もなかった山裾の家は床下浸水となりました。
見慣れた黄金色の穂波は満々たる湖水の下。上流から掛け干しの稲束が流れてきたり、土手向こうの養豚場からは豚舎から運び出される豚の悲鳴が天地にもとどろくばかりに聞こえたり、それを救出する人達の慌ただしい動きが見えたり……。
そんな時でも、農家の人は小舟を仕立てて稲束を拾い集め、その稲束の束ね方で「これは、誰々さんちの稲だ」と見分けたのには敬服しました。
|
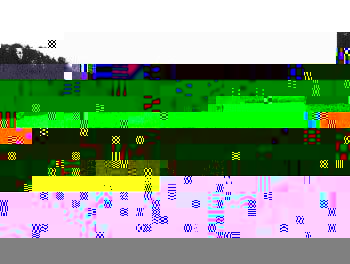
昭和33年9月の狩野川台風で湖のようになった港北区新羽町大竹地区
この写真が稲作水害補償の資料となった
撮影:千葉圭子さん(新吉田町)
|
|
|

写真左と同じ方向を望む現在の風景
左手は亀の甲山、その山の上に建つ新羽高校。中央後方の建物は建設中のサッカーWカップ開催予定の国際総合競技場
|
|
狩野川台風の教訓を生かして
翌朝の新聞は、「家畜はほとんど水死。濁流うずまく鶴見川沿岸」と雨に弱い鶴見川の惨状を報じていました。特に悲惨だったのは河口付近の鶴見区域、家の庇(ひさし)まで没したのが数百軒という有様。すぐ使える家財道具は何一つなく、頼みは救援物資という惨状でした。
この狩野川台風のときの鶴見川氾濫を重視した県や横浜市、川崎市が政府に改修を働きかけてから40年、鶴見川は今ではすっかりきれいになりました。
田んぼの一部は工場地域、河川敷は散策やゲートボール・テニスコートなど老若男女のレクリエーションの場、堤は長いサイクリングロード、あちこちに釣り人やバードウォッチングの人影が見られます。
三味線の音色流せし鶴見川 水面に高きビル映しおり
かつては紅灯のちまたの代名詞とされた綱島の街も、今はスーパーや専門店が並ぶ港北区屈指の商店街に生まれ変わり、奥には立派な住宅地を控えています。
当時何気なく娘が撮ったスナップ写真(上の写真)が農家の稲の水害補償に大変お役に立ち、当時の役員さんに喜ばれたことが昨日のことのように思い出されます。
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|
|