少年期の東横線と南武線
東横線は普通2両連結で、たまに3両だったりすると子供たちは大騒ぎで話題にしたものです。また、「ガソリンカー」と呼んだ流線形のパンタグラフのない電車が現れ,急行になりました。いまで言う気動車だったのです。急行は新丸子では停まらず、どうしても乗りたくて田園調布から日吉までわざわざ無賃で乗り越して新丸子まで戻るといった大冒険の道草をして家に帰ったものです。
あの頃の東横線の電車は、運転席が最前部の左側の小さな個室になっており、乗客用の座席も右側の一番前までありました。ドアも手動式が多く、新型車の正面には「ドアエンジン装置車」という白地の表示が行先表示板の横に付いていました。その行先表示板も行き先ごとに違い、渋谷~田園調布駅間は円形、渋谷~日吉駅間はユニークな「文」の字になっていました。
一方の南武線は1両電車が当たり前で、全部手動のドアでした。ほとんどの駅が無人だったので、車掌さんが車内で切符を切っていました。ホームに降りて発車、“呼び子”を吹き、動き出す電車の開いたドアに飛び乗る姿が格好良くて憧れたものです。
やがて東横線の現在の武蔵小杉駅のあたりに“新駅”ができましたが、南武線との連結駅にはならず、「工業都市」と名付けられました。その頃、南武線の向河原駅も「日本電気前」と改名され、戦時色が強まるのにつれて情緒がだんだん薄れていきました。
小学校卒業間近にわが家は田園調布に戻り、僕は自由ケ丘学園中学に入りました。自転車通学を始めたのも束の間、夏が過ぎると親父が東白楽に家を買い、またまた東横線のお世話になることに。
3両編成の電車は当たり前になり、急行は相変わらず日吉で普通電車を追い越していました。
東白楽の近くには横浜寄りに「新大田町」の駅があり、高台にあったわが家から電車がそこを出るのを見てから家を出ても間に合いました。反町と横浜駅の間のトンネルを出た所に「神奈川駅」があったのも昨日のことのよう。
|
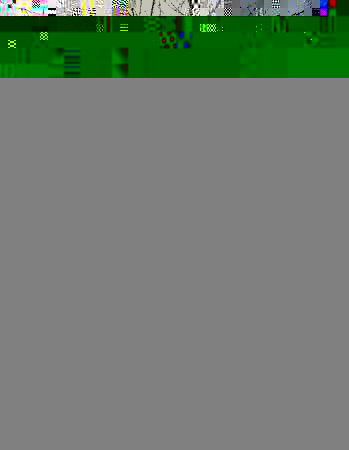
昭和5年(1930)冬、綱島鉄橋を渡る東横線木造1両電車
54人乗り電車は、きょうもガラ空き・・・
提供:松村写真館(綱島西)
|
|
|
通学途中で空襲に遭った戦時中
やがて空襲に明け暮れする時代……。現在孝道山の寺院が建っている丘は「軍艦山」といって見晴らしの良い丘で、背後の松林に続き、浦島丘の高台に通じていました。その松林には米軍機が撒いたと思われる電波妨害用の銀紙のテープがよく引っ掛かっていたのが印象的です。
学徒動員で1年近く蒲田の軍需工場へ通いましたが、そこは昭和20年4月の空襲で全壊。その後、5月末には横浜大空襲でわが家は焼けました。東横線もしばらくの間、渋谷~菊名駅間の折り返し運転となりました。
そんな戦時中でも卒業、入学の試験があり、今度は大岡山の東工大に通うことに。
学内の空地は正門から本館までの広場など一面のイモ畑。授業中にも警報が鳴り、グラウンドの隅にあった風洞実験室も被爆しました。通学途上でも空襲に遭ったことが何度かありましたが、特に恐ろしかったのは2度。
一度は空襲警報で停った元住吉駅での電車の中。乗客は散り散りに逃げましたが、僕はホームのはずれで、コンクリートの柱の陰にあった物置に隠れ、怖いもの見たさと闘いながらの半時間でした。近くの国鉄・新鶴見操車場が攻撃目標らしく、艦載機の急降下爆撃。編隊を崩して次からへと襲いかかってくるのです。
もう一度は電車が綱島駅に向け日吉駅を出て間もなく。突然の爆音で電車は急停車、艦載機の機銃掃射の目標にされていたのです。電車から飛び降り、車体の下に潜り込むのが精いっぱい。反復して機銃掃射を繰り返すのが、接近する爆音と弾道の土煙りでわかりました。今でも同じ場所を通るたび、あの時の情景を思い出します。
戦いは終わり、学校名が変わるたびに駅名も追っかけるように変わりました。府立高校~都立高校~都立大学。第一師範~学芸大学。
新大田町駅、神奈川駅、渋谷駅の次の並木橋駅は焼け落ちたままで廃駅となりました。
連合軍が進駐し、国鉄にならって東横線にも白線の「進駐軍専用車」(写真下)が半車両付くようになりました。国鉄はその車両を後に「婦人子供専用車」として使っていましたが、悪評に負けて止めてしまいました。
◇◆
その後の世の中の変貌は目覚ましい。かつて、3両連結の電車に歓声をあげていた元少年は還暦を数年前に済ませ、駅ごとのプラットホームの長さに溜め息をつく今日この頃です。
|
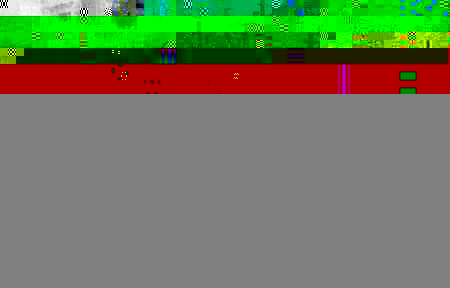
白線の入った東横線進駐軍車両
GHQの命令で昭和21年9月から27年2月まで運行の電車。1車両を3分の1に仕切って白線部分がビロードのクッション付きの進駐軍専用、残りが板張り座席の一般乗客用。撮影場所は代官山駅
撮影:田辺雅文さん(港北区下田町)
|
|
|
|