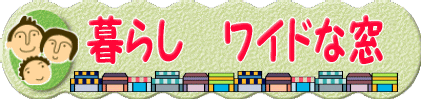 |
| 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |
| 編集:岩田忠利 NO.277 2014.10.08 掲載 |
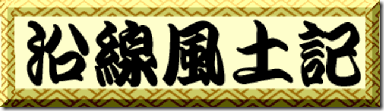 |
  |
古代のわが町・久が原
文・長谷川邦春 (旅館「観月」社長 大田区千鳥)
|
|
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”
掲載記事:平成4年4月15日発行本誌No.53 号名「朴(ほう)」
|
|
|
海岸線だった久が原に千鳥窪貝塚
今から二千年前から一万年前くらいの古い石器時代の人たちは、野山の木や草の実を採ったり、鹿や猪、兎を捕ったり、海の魚や貝などをとって食べ、生活していました。食べた後、捨てた貝塚からは貝殻のほか、鳥や獣の骨・土器・石器のかけらなども出ます。
石器時代の頃、大田区内の山王・馬込・池上本門寺周辺のような25〜35メートルの高台や久が原のような15〜25メートルの低い台地は、武蔵野台地の南端で海岸でした。遠浅で波静かな入江に望む久が原台地は、大昔の人たちが生活するのに最適だったでしょう。
大田区内では、大森・馬込・雪谷・沼部・千鳥窪(久が原の大森第七中学)に大きな貝塚が発見されています。
なかでも千鳥窪貝塚は、千鳥形に湾入した入江の奥にあって、原始時代の簡単な筏か丸木船などの良い船着き場だったと思われます。ですから、縄文時代(中期〜後期)には、かなり多くの集落があったと考えられます。この貝塚からは、石斧・石剣・土偶・岩偶などのほか人骨も10体以上、出土。これらは今でも東大・国学院大・先の七中などに保存されています。
|
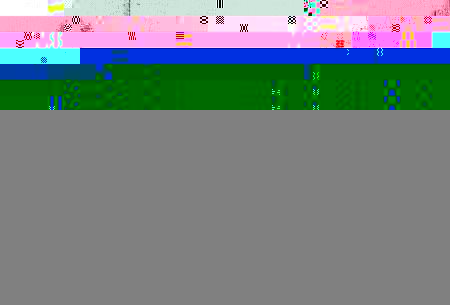
千鳥窪貝塚が発見された大森第七中学グラウンド西隣の現在地
|
|
|
南関東屈指の弥生式竪穴住居跡密集地
今から二千年前頃、その数百年間の弥生時代は、縄文土器のようなゴテゴテした模様のない、すっきりした美しい曲線の固焼き土器を作って用いていました。静岡県の登呂遺跡で見られるような水稲栽培を中心とした農業が行われるようになり、人々の生活は縄文時代に比べると、ずっと安定し、生活上の工夫も一段と進歩しました。当時は鋼矛・銅鐸などの青銅器のほか、鉄剣・鉄矢じりなどの鉄器も少し使用されていました。しかし大部分は石器で鍬や鋤などの農機具は、木製が一般的でした。
こうした時代の弥生式竪穴住居の跡が、昭和2年以来、久が原台地に数多く発見されました。久が原台地には東西から浸蝕された二つの枝谷があって東側の枝谷の奥には「久が原貝塚」(久が原小学校付近)、西側に枝谷の奥には「千鳥窪貝塚」がつくられ、弥生式住居祉群はこれらと重複しています。
とにかくこの遺跡は、台地全域という広さや時間的継続の長さからみても貴重なものといわれ、南関東の代表的な竪穴住居跡の密集地であることがわかりました。海抜156メートルという比較的低い平らな久が原台地、そこはその頃、すぐ下に陸化したばかりの多摩川三角洲で始まった水稲栽培地が近く、とても暮らし良い場所であったと思われます。
住居跡は半地下式で柱穴や炉の跡があり、出土する土器はいわゆる「久が原土器」(土器の標準遺跡)です。表面は朱で塗られ、複雑な幾何学模様の飾りがついた美しい壷形土器です。またほかに獣の骨や米、木製品なども出土しました。
昭和47年発見の横穴古墳7基
今から1400年前ころを古墳時代といいます。歴史上では、大和朝廷が強大となり全国を平定し、大化の改新によって古代統一国家が生まれる頃とほぼ同じ時代。その時代には各地に前方後円や円形の古墳がつくられました。
武蔵野台地の東南端にあたる大田区の台地の斜面には、横穴古墳がよく発見されました。その主なものは、新井宿・山王群・本門寺桐里群・塚越群・鵜の木根岸群と久が原群です。久が原台地の斜面では、昭和43年にも羽子板状の形をした横穴古墳7基が、5メートル間隔くらいにあるのが発見されました。そのうち3基には前室のあったことが認められました。大きさは長軸が5メートル〜7メートルほどで、奈良時代の前期(8世紀)のものでした。
横穴古墳は一般的には多摩川台公園の亀甲山古墳や雪谷の大塚古墳より.少し後の6、7世紀頃のものが大半ですから、久が原の古墳はこの辺に住んでいた普通の人の墓として埋葬されたものと考えられます。
|
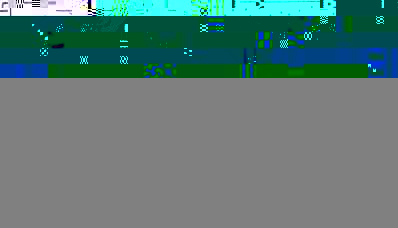
久が原横穴古墳の断面図
|
|
|
一つの横穴は、大体上の図のような構造で、入口には凝灰石質砂岩の切り石が置いてあることが多い。人が這って入れるくらいの狭い通路の奥には、やや広い玄室があり、多摩川砂利を敷きつめた床に、3体から7体の遺体が横たわっているのが普通です。
弥生式の土器より一段と堅焼きで、上薬を使った土師器や須恵器の土器や、まれに真刀や矢尻などが納めれてあることもありますが、人骨だけのことが多いようです。
これは古代、久が原に人が住んでいた歴然たる証拠です。
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|