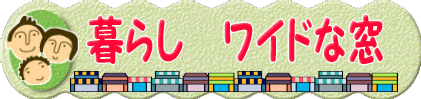 |
| 編集支援:阿部匡宏 / ロゴ:配野美矢子 |
| 編集:岩田忠利 NO.274 2014.10.08 掲載 |
|
★画像はクリックし拡大してご覧ください。
|
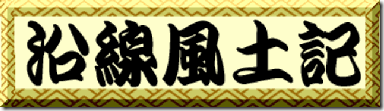 |
  |
|
武蔵小山商店街、激動の歩み
文・木村高雄 (武蔵小山商店街振興組合・青年部部長)
|
|
|
|
|
沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』。好評連載の“復刻版”
掲載記事:昭和63年8月15日発行本誌No.43 号名「枇(びわ)」
|
|
|
地蔵が辻、今は後地交差点
大井町駅から池上通りを南に下ると、鹿島神社の手前に品川区立の品川歴史館がある。ここの展示室の一画に品川用水の模型が展示されている。十文字に交差する細い道、その脇を流れる農業用水がそれで道をくぐる所には堰が作られている。その周囲には畑、その向こうには竹林。のんびりした田園風景が広がる、ただそれだけの小さな模型であるけれど、ここに江戸時代の平塚村字小山の昔日を見る思いがする。
またこの模型に2本の道。碑文谷道と目黒道がぶつかる辻にポツンと石地蔵が立っている。奥沢九品仏浄真寺の開祖珂磧(かせき)上人が毎日奥沢から芝増上寺に修行に通う途中、このあたりで朝日が東の空に昇ることから、上人はこの地蔵を〝朝日地蔵″と呼んだ。
ここが現在の後地(うしろじ)交差点であることは、地元の方ならすぐお分かりだろう。
広がる竹林は寛政1年(1789年)戸越村村内(現品川区小山一丁目)に別荘を持っていた京橋の大商人、回船問屋の山路次郎兵衛勝孝が薩摩藩外持ち出しを禁じられていた孟宗竹のタケノコを密かに手に入れ、庭に移植したことが始まり。これを付近の農家に奨励して特産物として神田市場へ出荷したところ、江戸市民の人気を博した。これが「目黒のタケノコ」といわれ、「品川ネギ」・「大井村のニンジン」などと並んで特殊銘柄と呼ばれるようになったのは周知のとおり。
武蔵小山一帯は春はタケノコ、夏はキウリ・ナス・スイカ・マクワウリ、冬は大根と四季折々の野菜づくりが盛んな純農村地帯であった。この穏やかな風景は、さほど変わることなく明治・大正と続いたのである。
|
|
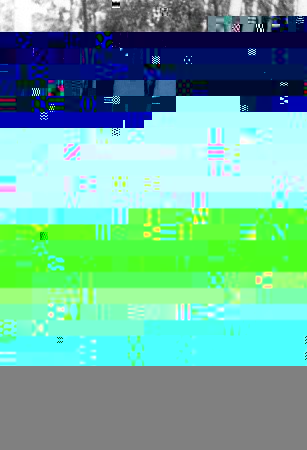
明治38年(1905)、中原街道の平塚橋を通りかかった英国人が撮影したタケノコ掘りの情景
現在地は武蔵小山商店街のアーケード街パルコの南口・出入り口付近
提供:南 博さん(品川区中延2丁目)
|
|
|
荏原のビッグバン(大爆発)
大正末期、荏原の「ビッグバン」ともいうべき人口増加の大爆発が起こる。これは数値が物語る。大正9年(1920年)から昭和5年(1930年)の約10年間に荏原町(戸越・上蛇窪・下蛇窪・中延・小山)の人口は、8522人から一挙に13万2107人へと……。なんと15倍以上に膨れあがったのである。
その要因の第一には渋沢栄一氏らによる〝田園都市構想″の一環である大正12年(1923年)の目蒲線開通とそれに続く大井町線、池上線の開通があげられるが、これと前後して起こる関東大震災がその決定的原因となる。
品川区内は家屋の倒壊はあったものの、火災は2、3件にとどまり、ことに荏原台地の上に位置した小山部落はほとんど無傷であった。加えて純然たる農村地帯であったから地価も安く、市街地建物法の規制も受けなかったために続々と都心部から人が移り住むことになった。
こうして「小山66軒」といわれた村はずれの部落は、瞬く間に新興住宅地に生まれかわり、同時に震災や都市計画による立ち退きで神田・浅草などから引っ越してきた小売商が次々と店を開いて、やがて「小山銀座」と呼ばれる商店街を形成していった。これが今日の武蔵小山商店街の原形である。
この目をみはる驚異的な成長過程からみても、新天地に店を構えた先人たちの開拓精神と商魂がいかに燃えたぎるものであったかを感じずにはいられない。
当時の武蔵小山の街の中心は、中原街道に通じる本通りよりも、西小山方面に向かう小山銀座通りにあった。ところが改正道路(補助26号線)の開通とその整備によって銀座通りは二つに分断され、人の流れも変わり、今やその中心は本通りに移ったようである。
昭和12年、本通りに分立していた商友会・商栄会・四丁目会などの商店会を統合し、人望の厚かった山崎真一氏を理事長に武蔵小山商店街商業組合が創立された。ただ小山銀座会だけは加入しなかった。この発足記念大売出しの5日間は、空前の盛況を極めた。数万枚のポスターが各駅や電車内、都内一円に貼られ、商店街からは宣伝部隊が連日近郊を回った。
当時まだ珍しいアドバルーンをはじめ、軽飛行機に宣伝の大旗をつけてのビラ散布など、華々しい宣伝活動が行なわれた。この結果、街は予想以上の賑わいをみせ、以後武蔵小山の名は都内に広く知られるようになった。
街の満蒙開拓団1030名、生還は僅か13名…
新興商店街の活気も満州事変(1931年)に続く第2次世界大戦突入によって次第に勢いを失っていった。とくに原料を海外に依存する品不足は深刻で、食糧・物資が配給制になるに至っては商売もいっそうままならなくなってきた。軍需工場へ徴用されるか兵役につくか、多くの商店主たちが転廃業を迫られていた。このような商業受難な時に、満蒙開拓団結成の話がもちあがったのである。
軍の甘い誘いもあった。また慢性化した食糧難を救うという興国の自負もあって、不安の中にも夢を馳せ胸を張って満蒙の大地に彼らは出発したのであったろう。
昭和18年の先遣隊に続いて翌19年4月、武蔵小山商店街商業組合理事長・山崎真一氏を団長とする“東京荏原満蒙開拓団”は、縁故者・同業者をも募って家族団員総勢1030名――。一行は武蔵小山駅から日の丸の小旗で送り出された。その心の底からは、十数年前に小山の地に移り住んだ時と同様のフロンティア精神が汲みとれるのである。
ソ満国境の辺地、興安に渡って1年余りの後、ソ連参戦を機に現地民の蜂起に惨たんたる逃避行の末、本土に辿りつけたのは、わずか13名――。ほかの一千有余名は大半が戦死、あるいは自決死の最期をとげた。
こうした筆舌に尽しがたい悲劇の記憶は、戦後新たに武蔵小山に移ってきた人々に紛れ、以前から住んでいる人の心の奥に閉ざされているかにみえるが、彼らの開拓の精神と団結の心は今の商店街関係者の胸中に脈打っている。
開拓団を見送り解体した商店街も、翌年までに壊滅的な戦火に巻き込まれていた。26号線と小山本通りの間の商店はすべで強制疎開(住宅・商店など建物の強制的立ち退き)で破壊され、その対面も昭和20年5月の空襲で中原街道寄りの数店を残し全焼してしまったのである。幸いにも空襲を免がれた銀座通りを除き、武蔵小山商店街はほぼ完全にその姿を失ったのであった。
|
|
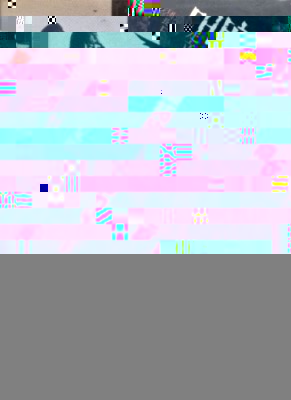
13人の生還者の一人、足立副団長が開拓団の悲惨な最期を報告した本 出版:「曠野に祈る」 恒友社
|
|
|
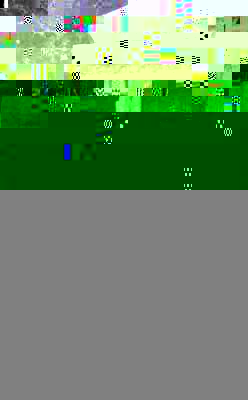
商店街に隣接した朗惺寺にある満蒙開拓団 慰霊碑
|
|
力強く急速な再生、そして躍進
武蔵小山の復興は、その成立時以上に目覚ましいものであった。終戦の翌年、昭和21年には早くも小山本通りと銀座通りを合併し武蔵小山商店街協同組合が発足した。
ツルヤ洋品店の高橋周平氏(第6代武蔵小山商店街振興組合・理事長)は当時の模様をこう語っておられる。
「食糧にも困っている時代だから、道路などは荒れ放題だった。都でも区でも手が回らない。すべて自分たちでやらねばならない。都でアスファルトの残骸をくれるというので、芝浦までトラックで取りに行って、焼夷弾で穴だらけの道にそれを埋めで平らにした。ドブもさらって板をはめた。そうしてやっとまともに歩ける道を作ったものだ。」
こうした一つ一つの努力の積み重ねが、10年後の昭和31年、当時〝東洋一″といわれたアーケード完成に結実するのである。
現在、ドーム型の明るいアーケードが堂々と連なっているが、昭和60年の旧アーケード取り壊しのとき、ちらっと往時の武蔵小山の面影を見たような感慨にふけった方も少なくないであろう。
先人の歩んだ苦難と克服の歴史を顧みるとき、その力強さに心打たれると同時に、人と人の絆の強さに感嘆するのである。
私たちはこの武蔵小山で私たち自身の〝暮らしの開拓者″となって、タケノコのごとくコミュニティーの根を張り、東京一住み良い街にする努力を惜しんではならないだろう。
|
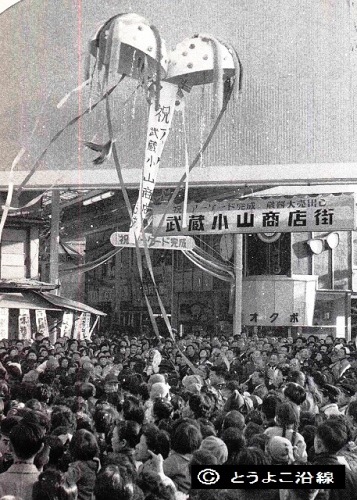
昭和31年12月10日、全長470㍍の第1アーケード完成! 駅前で祝賀式 提供:武蔵小山商店街
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
「とうよこ沿線」TOPに戻る |
 |
次ページへ |
 |
「目次」に戻る |
|
|
|
|